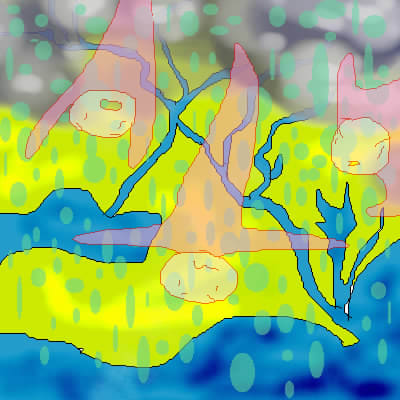Perfume(パフューム)を聴きながら書いています。 …ウソです(笑)。 でもあの彼女達、まったく心には沁み込んでこないのに、それなのに妙に記憶に残る歌をうたうと三人組だなあ、と気になってはいます。男が読んではいけない少女漫画に触れたような感覚。「テクノポップ」なんすか、これ。
ラジオから流れてきた
『星つむぎの歌』という平原綾香の曲をもう一度聴きたくなったので彼女のベストアルバムをレンタルしてきて聴いています。いい曲ですね。東京は春から夏にかけての、星が見えにくい季節になりましたが。
平原綾香さんは『Jupiter』が有名ですね。僕はあの歌声と曲は好きなんですけど歌詞がどうも心にフィットしない。まあそれはいいとして、あれは、クラシックのホルスト『惑星』の曲ですね。今確認してみましたら、その曲をホルスト(イギリス人)が作曲したのは1914年。英国が第一次世界大戦に突入した年です。その組曲の中で「Jupiter(木星)」は「快楽をもたらすもの」という意味なんですって。
じつは僕は『惑星』のこの部分を若いときになぜだかよく口ずさんでいたんです。歌詞はありませんからハミングで。
んーんーんー んんんんんんんんんんーんーんーんー んんーん♪
僕はクラシックはほとんど聴かなかったのですが、たぶん、
富田勲のシンセサイザーの曲を聴いていて、その影響ですね、『惑星』をハミングしていたのは。富田勲さんは、沢山の有名な曲がありますが、TVの『ジャングル大帝』の曲が馴染み深い。
あー あー あー あー ♪
僕は10年くらい前、NHK「みんなの歌」で流れていた太田裕美さんの『僕は君の涙』を聴いて、その曲がとても好きになりました。
その頃の僕は実家にいて、働く以外はめし食って詰将棋をつくって眠って、あとは川を眺めていました。いつも目の前で
鶺鴒(セキレイ)が2、3羽シッポをピコピコ動かしながら川にすむ虫を探していました。セキレイって飛ぶときはばたばたと一生懸命はばたくんですが、そのわりにうまく飛べていないようにみえる。かれらは、夫婦だったのか、きょうだいだったのかわかりませんが、ずいぶん仲が良さそうに見えました。
そんなときに聴いた『僕は君の涙』は、こんな内容の曲です。
小さな女の子がいます。そのコが泣いて、涙がこぼれ落ちます。落ちたその涙のつぶである「僕」は雨とともに川に流れ、川下へと旅をして行きます。やがて海に出ます。それから水蒸気になって空にのぼり雲になります。雲は風にのって山のほうまで運ばれ、そこで雨となって大地に降ります。雨は大地の渇きを潤してさまざまなものを洗い流します。そして「僕」は、大地の中にすいこまれ葡萄の木の根に吸い上げられて、やがてブドウの実となります。ブドウの実はワインに変わり、あの「女の子」のもとへ。「女の子」は成長して大人の女性となっていました。そこでも泣いていた彼女は、ワインを飲んで元気に。そして「女の子」は、結婚しお母さんになり…。
そんな話です。僕はこの話のように、川の水が流れて海へ出て、やがて山に戻ってくる… そういう話が、どうも、すきなのです。(彼女の中に入った「僕」は、その後、オシッコに…。いけません、そんなこと考えちゃいけません!)
この曲はたしか太田さんの作詞作曲だったと思います。
太田裕美さんは「酒豪としても有名である」とWikipediaにありました。太田さん、ワインの飲みすぎにご注意を。(スマン、よけいなお世話じゃ。)
ところで、東京では、意外なほど
ウグイスの声をよく聴きます。去年、僕は20回以上は聴いています。こんなにもウグイスが鳴くのはおかしいと思い、「そういうグッズ」(ウグイスの鳴き声が流れてくる機械)が販売されていて地味に流行っているのでは、と疑いはじめていたところでした。
2週間前、今年最初のウグイスの声を聴きました。ずいぶん近いように思われたので、よし、ほんもののウグイスかどうか確かめてやろうと思い、声の出所をさがしました。すると…
居たのです。木の枝をちょこちょこと飛び移っているウグイスが。ええ、電気ウグイスではありませんでした。(すまん、ウグイス。うたぐって悪かった。)
しかし、そうすると、このウグイスたちは、鳴かない季節もやはり東京に住んでいるのです。どんなふうに暮らしているのでしょうね。