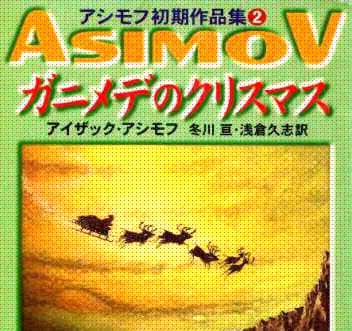イギリスのチャレンジャー号(深海探査船)のことを書いたので、それでは海の底へ潜る旅にでかけよう…ということで、『海底二万マイル』である。作者はフランスの作家ジュール・ベルヌ。
上の画はノーチラス号。 これは1954年公開の映画を観て。この映画はディズニーの最初の長編映画である。
ベルヌがこの世界中の海底を潜水艦で大冒険するこのダイナミックな小説を書いたのは、1870年。 世界の深海を調べてまわるというチャレンジャー号探検の出発は1872年。 「深海」という未知の世界への空想の飛翔――ジュール・ベルヌの夢想と、イギリスの学者達の壮大な探査計画とが、ほぼ同じ時期に重なっていることを、僕はたいへんおもしろいと思うのである。 両者の共通項は‘科学’である。
この最新の潜水艦ノーチラス号の船長はネモ船長だ。 「ネモ」と名乗ったその男は、国籍不明で大金持ちの発明家、海を愛し、陸のものは決して食さないというへんな奴である。そもそも「ネモ」というのは「だれでもない」(ラテン語)の意味なのだ。
1867年11月8日、ノーチラス号のその旅は始まった。
〔 …船長はふたたび言った。「パリの子午線で東経137.15度、北緯は30.7度、すなわち日本の海岸から約50キロほどのところです。本日、11月8日の正午より、われわれの海底探検旅行は、はじまります。」 〕
1867年といえば、日本では幕末である。(坂本龍馬が暗殺されたのがこの年だ。)
その日本の近海がこの旅の出発点となっている。
ノーチラス号は、太平洋の海の底を泳ぎ、サメの群れに会い、オーストラリアでは珊瑚、インド洋セイロン島では真珠を観る。そして紅海に…。
この小説には、ノーチラス号の旅の地図が付いている。 それによれば、この潜水艦は1868年2月にインド洋から紅海に入りそこから地中海へと進んでいる。 …あれ? するとスエズ運河を通ったわけ? いやそうではない。 というかそもそも1868年にはスエズ運河はまだ工事途中で未完成なのである。ではノーチラス号はどうやって地中海へ行ったのか? 実はネモ船長はここを抜ける秘密のトンネルを海底に見つけていたのだ!
さらにこの鉄製巨大オウム貝(ノーチラス号のことだ)の旅は続く。
スペイン沖で沈没船の財宝を見つけ、そこから南下して南極をめざす。途中マッコウクジラに会い、南極大陸の地を踏みアザラシやセイウチと遊び、氷に閉じ込められるという絶体絶命のピンチを切り抜けたあとは、大西洋を北上…。 そして――カリブ海。
〔 4月18日、約50キロをへだてて、マルティニーク島とグアドループ島とが見えた。ちらっとわたしは、それらの島々の高峰を望んだのである。 〕
そしてその2日後に、ノーチラス号の旅のクライマックス、あの大ダコとの闘いになるのである。
〔 4月20日のこの恐ろしい光景を、われわれはだれしも、忘れてしまうことはできなかったろう。わたしはこれを、はげしい感動をもって書いた。 〕
巨大潜水艦の物語といえば、欠かせないのがこの「大ダコとの闘い」のシーンである。(ただし、映画版ではイカだった。なぜだろう?)
その原型はここにあるわけだが、なぜベルヌはこれを思いついたのか?
おそらくは、ジュール・ベルヌはそういう『絵』をどこかで観ていたのだ。どうやら船が巨大なタコに襲われて沈んだという話はむかしからあり、そういう伝説が『絵』になっているのを彼ベルヌは子どもの頃にみていたようである。
そして上にあるように、ノーチラス号と大ダコの闘いの場所というのは、あのマルティニーク島の近海だったのである。
マルティニーク島については、このブログではすこし書いた。 ラフカディオ・ハーンが興味をもって訪れ(1887~1889年)、画家ゴーギャンがスケッチに行き(1889年)、「クーロンの法則」の発見者シャルル・ド・クーロンが軍人として赴任した(1760年代)というフランス領の小さな島である。 この島は、火山の爆発とラム酒でも有名なようだ。
ノーチラス号はメキシコ湾流にのって北海にすすみ、ノルウェーの大渦「メールストルム」に捕まる。それは捕まったらゼッタイに脱出不可能な伝説の大渦巻きなのだ!!
この「メールストルム」のアイデアは、エドガー・アラン・ポーの小説『メールシュトレームに呑まれて』によるものである。
そしてこの海底の壮大な20000マイルの旅はついにここで終焉をむかえる。
だが、この物語を記した「わたし」たちは、たすかる。どうやってたすかったのか、それはわからない。
気がつくと、自分達は生きていて、しかし、ノーチラス号とネモ船長はどうなったか、だれも知らない。 まるで海底の旅は、夢だったかのように…すべては記憶の中にのみ…。
そして玉手箱を開けると中から煙が出てきて白髪に… え?
さて、続けて、ノーチラス号の動力源(電池である!)の話を書こうと思っていたのだが…、すでにずいぶん長文になってしまったので、ここまででやめておこう。
[追記] 原題では『海底二万マイル』ではなくて「二万リュー」だそうです。「リュー」(フランス語)って距離の単位は英語では「リーグ」、これは「マイル」の約3倍の距離で、約5.5キロほど。ですから原題にしたがうと正しくは『海底11万キロメートル』となるはずのところ。つまり『海底二万マイル』の日本版の題名では、距離的にでたらめになっているようです。いつのまにかそれが定着してしまい、「間違っているけど、ま、いいか、」ということでしょうね。
「11万キロメートル」というのは、地球の直径がおおよそ13万キロなので、そうとうな距離ですが、もちろんこれは海の深さではありません。ノーチラス号の、日本近海からノルウェー沖までの推進距離です。(でも本の地図をみると11万キロよりもっと長い気がするのですけど。)
[さらに追記] ↑ まちがい! 地球の直径は「13万キロ」ではなく、「1.3万キロ」でした!
そうするとノーチラス号の旅「11万キロ」は、地球を約3周ほどの距離となります。 (いやいや、恥ずかしい間違いでした。)
上の画はノーチラス号。 これは1954年公開の映画を観て。この映画はディズニーの最初の長編映画である。
ベルヌがこの世界中の海底を潜水艦で大冒険するこのダイナミックな小説を書いたのは、1870年。 世界の深海を調べてまわるというチャレンジャー号探検の出発は1872年。 「深海」という未知の世界への空想の飛翔――ジュール・ベルヌの夢想と、イギリスの学者達の壮大な探査計画とが、ほぼ同じ時期に重なっていることを、僕はたいへんおもしろいと思うのである。 両者の共通項は‘科学’である。
この最新の潜水艦ノーチラス号の船長はネモ船長だ。 「ネモ」と名乗ったその男は、国籍不明で大金持ちの発明家、海を愛し、陸のものは決して食さないというへんな奴である。そもそも「ネモ」というのは「だれでもない」(ラテン語)の意味なのだ。
1867年11月8日、ノーチラス号のその旅は始まった。
〔 …船長はふたたび言った。「パリの子午線で東経137.15度、北緯は30.7度、すなわち日本の海岸から約50キロほどのところです。本日、11月8日の正午より、われわれの海底探検旅行は、はじまります。」 〕
1867年といえば、日本では幕末である。(坂本龍馬が暗殺されたのがこの年だ。)
その日本の近海がこの旅の出発点となっている。
ノーチラス号は、太平洋の海の底を泳ぎ、サメの群れに会い、オーストラリアでは珊瑚、インド洋セイロン島では真珠を観る。そして紅海に…。
この小説には、ノーチラス号の旅の地図が付いている。 それによれば、この潜水艦は1868年2月にインド洋から紅海に入りそこから地中海へと進んでいる。 …あれ? するとスエズ運河を通ったわけ? いやそうではない。 というかそもそも1868年にはスエズ運河はまだ工事途中で未完成なのである。ではノーチラス号はどうやって地中海へ行ったのか? 実はネモ船長はここを抜ける秘密のトンネルを海底に見つけていたのだ!
さらにこの鉄製巨大オウム貝(ノーチラス号のことだ)の旅は続く。
スペイン沖で沈没船の財宝を見つけ、そこから南下して南極をめざす。途中マッコウクジラに会い、南極大陸の地を踏みアザラシやセイウチと遊び、氷に閉じ込められるという絶体絶命のピンチを切り抜けたあとは、大西洋を北上…。 そして――カリブ海。
〔 4月18日、約50キロをへだてて、マルティニーク島とグアドループ島とが見えた。ちらっとわたしは、それらの島々の高峰を望んだのである。 〕
そしてその2日後に、ノーチラス号の旅のクライマックス、あの大ダコとの闘いになるのである。
〔 4月20日のこの恐ろしい光景を、われわれはだれしも、忘れてしまうことはできなかったろう。わたしはこれを、はげしい感動をもって書いた。 〕
巨大潜水艦の物語といえば、欠かせないのがこの「大ダコとの闘い」のシーンである。(ただし、映画版ではイカだった。なぜだろう?)
その原型はここにあるわけだが、なぜベルヌはこれを思いついたのか?
おそらくは、ジュール・ベルヌはそういう『絵』をどこかで観ていたのだ。どうやら船が巨大なタコに襲われて沈んだという話はむかしからあり、そういう伝説が『絵』になっているのを彼ベルヌは子どもの頃にみていたようである。
そして上にあるように、ノーチラス号と大ダコの闘いの場所というのは、あのマルティニーク島の近海だったのである。
マルティニーク島については、このブログではすこし書いた。 ラフカディオ・ハーンが興味をもって訪れ(1887~1889年)、画家ゴーギャンがスケッチに行き(1889年)、「クーロンの法則」の発見者シャルル・ド・クーロンが軍人として赴任した(1760年代)というフランス領の小さな島である。 この島は、火山の爆発とラム酒でも有名なようだ。
ノーチラス号はメキシコ湾流にのって北海にすすみ、ノルウェーの大渦「メールストルム」に捕まる。それは捕まったらゼッタイに脱出不可能な伝説の大渦巻きなのだ!!
この「メールストルム」のアイデアは、エドガー・アラン・ポーの小説『メールシュトレームに呑まれて』によるものである。
そしてこの海底の壮大な20000マイルの旅はついにここで終焉をむかえる。
だが、この物語を記した「わたし」たちは、たすかる。どうやってたすかったのか、それはわからない。
気がつくと、自分達は生きていて、しかし、ノーチラス号とネモ船長はどうなったか、だれも知らない。 まるで海底の旅は、夢だったかのように…すべては記憶の中にのみ…。
そして玉手箱を開けると中から煙が出てきて白髪に… え?
さて、続けて、ノーチラス号の動力源(電池である!)の話を書こうと思っていたのだが…、すでにずいぶん長文になってしまったので、ここまででやめておこう。
[追記] 原題では『海底二万マイル』ではなくて「二万リュー」だそうです。「リュー」(フランス語)って距離の単位は英語では「リーグ」、これは「マイル」の約3倍の距離で、約5.5キロほど。ですから原題にしたがうと正しくは『海底11万キロメートル』となるはずのところ。つまり『海底二万マイル』の日本版の題名では、距離的にでたらめになっているようです。いつのまにかそれが定着してしまい、「間違っているけど、ま、いいか、」ということでしょうね。
「11万キロメートル」というのは、地球の直径がおおよそ13万キロなので、そうとうな距離ですが、もちろんこれは海の深さではありません。ノーチラス号の、日本近海からノルウェー沖までの推進距離です。(でも本の地図をみると11万キロよりもっと長い気がするのですけど。)
[さらに追記] ↑ まちがい! 地球の直径は「13万キロ」ではなく、「1.3万キロ」でした!
そうするとノーチラス号の旅「11万キロ」は、地球を約3周ほどの距離となります。 (いやいや、恥ずかしい間違いでした。)