
熱力学には第1法則と第2法則とがある。
熱力学の第1法則とは「エネルギー保存の法則」のことで、これを19世紀にきっちり表現し整理したのがドイツ・ベルリン大学のヘルムホルツという人。日本の長岡半太郎はこの人のところに留学した。当時のドイツ物理学界を仕切っていた大親分がヘルムホルツだ。
「エネルギー保存の法則」とはつまり、エネルギーというものは姿かたちを変えるけれども(たとえば熱エネルギーが運動エネルギーに変化する)、全体としてはその「総量」は不変だよ、と言い切ったのである。
それなら、「エネルギーの総量が不変」であるなら、うまく考え工夫すれば、「永久機関」が発明できるのではないか、ということになる。
たとえば、石炭を燃やしてその熱エネルギーを蒸気の圧力エネルギーに変えるのが「蒸気機関」だが、それを機関車では車輪の回転運動に変える。それによって機関車は「仕事」をするのだが、その際に車輪自体が「熱」をもつ。その「熱」をもういちど回収して使うことができれば、効率がよい。仮に100パーセントその無駄に逃げていく「熱」のエネルギーを回収できれば、もう石炭は不要になって、その機関車は永久に動き続ける。「夢の永久機関」だ。
19世紀のヨーロッパの物理学者たちは、そんなことが可能なのかどうか、考えていた。 また、できないとしたら、それはなぜなのだろう、などと。
結局、「夢の永久機関」は無理だ、と(理論的にはっきりと)わかった。それが熱力学の第2法則だ。
その熱力学第2法則を「エントロピーは増大する、そしてこれは不可逆反応である」と表現したのが、ドイツの物理学者クラウジウスである。 彼こそが「エントロピー」という言葉を物理学の世界に持ちこんだ人物だ。
要するにこの法則は、「エネルギー(熱)は分散して、自然に元に戻ることは絶対にない」ということである。 だから「永久機関」はつくれないのだと理論的に証明された。

以上は、熱力学のやさしい本に紹介されていることである。一応説明しとくと、「エントロピーが増大する」とは、粒子やエネルギーが広がって平均化していくことである。
たとえば透明な水に青色インクをたらすと、インクは広がっていって薄まる。「エントロピーの増大」である。しかし元にはもどらない。つまり「不可逆」である。
しかしこの「エントロピー」という考えは、はじめはうんなるほどとわかっても、考えているとそのうちにだんだんわからなくなる。それなのに科学のいたるところに「エントロピーは増大する」という表現が出てきて困るのである。
上のブルーバックスの本の裏表紙にもこうある。
『定義は簡単だけれども、もうひとつよく解からないエントロピー』 そうなんだよな。
たとえば時間が流れる。それを逆の方向に、つまり過去の方向には戻せない。それは「世界はエントロピーが増大する方向にしか流れず、不可逆だから」なのである。
宇宙は膨張している。それも「エントロピーは増大する」という法則に当てはまる。もちろん、不可逆反応である。
そんなに「エントロピー」が大事ですか、なんでエントロピーがどうのといちいちうるさいんですかっ! なんて気分にもなる。
まあいい。 受け入れりゃいいのだ。
「エントロピー」は増大するんだ。 それでいい。
さてここからは別のはなしで、なにかの本に書いてあることではなく、‘僕の空想’です。
なんのことを書くかといえば、神経症、依存症(中毒)のことを書こうと思うのですが、僕はこれらのことについて、以前から理解しようと時々本を読んでみたりしましたが、あまりよくつかめなかった。医学用語というのは医者のためのものですからね。それでも気になるテーマなので(自分や社会の理解のために)、自分なりに考えて、それが次のようなイメージとなったわけです。
こころの中には一つの巨大な「ホール(穴)」があるのではないでしょうか。
まずそういうイメージからはじめます。
そしてその「ホール」のむこうからこちらに向けてて‘流れ’がある。その‘流れ’とは、生命力の‘流れ’です。「むこうからこっち」のながれが、エントロピーの“正”の方向のながれであり、これが自然なながれです。私達は産まれた時からずっとこの生命の‘流れ’に乗って生活しています。
ところが、何かの理由で(その理由には人それぞれのものがあると思いますが)、こころの一部が、その生命の‘流れ’を逆行しようとします…その状態を、「ノイローゼ」というのではないでしょうか。(ノイローゼとは神経症のことです)
生命の‘流れ’は、「ホール」のむこうからこっちにながれている。ところが、なぜか、ある種の人は、エントロピーの法則に逆らって、逆にすすむ。そうなりやすい体質の人が世の中にはいるのではないだろうかと思います。(自分もいくらかその体質をもってる一人だと思うのです。だから時間を逆行して19世紀のことなどに興味をもつ…。) 本人の意思ではなく、体質として、そうなるのです。まるで「ホール」が彼(または彼女)を吸い込むように。
そして「ホール」に近づくにしたがって、“異常”なことが起こるのです。(そういう場所なのだ。) 確率の低い偶然が連続して起こったり、予知夢を見たり…。ユング心理学はこれらを「共時性(シンクロニシティ)」と名付けて表しました。 (ユングの見た夢はほんとすごいですよね。)
しかし、そんな体質で生きることは苦しい。なにしろ、人間は“正”の方向に進むようにできています。人間社会もそうなっています。人間の幸福は、その“正”の‘流れ’に沿って生きることだろうと思います。
それでも「ホール」は、“負”のちからで、彼(彼女)を引き寄せる。なんとしても“正”の方向に前向きに生きたい彼(彼女)は、その“負”のちからに負けまいと、「何か」にしがみつく。
その「何か」が、アルコールであったり、薬物であったりすると、アルコール依存、薬物依存となる。仕事依存、恋愛依存、甘味依存、ゲーム依存もある。依存するものはなんでも可能性があります。(これらには「刺激物」という共通項がある。) そして責任ある立場の人ほど、社会人らしくあろうとするために、“負”の流れに負けないために、何かに依存する可能性が高くなるわけです。
しかしそれらは、一時的な避難の効果しかないようです。 一方で「ホール」の引っぱるちからは連続的…休みなしなので困ります。ですから、「依存」の頑張りもやがて限界がくるのですね。
だから頑張る人は何かに「依存」して“負”のエントロピーからくる苦しみを回避し、回避する手段を持たなかった(選ばなかった)人は、「神経症」の苦しみを受け入れる。「依存」していた人が「依存」をやめたら、やっぱりそこから苦しみと向きあわなきゃならなくなる。回り道している分だけ、また「苦しみ」に慣れていない分だけ、「依存タイプ」の人の方が、あとが大変ではなかろうか。
しかし、では、どうすればよいのか? なにものにもしがみつかず、その“負”のエントロピーのちからにどうやって対抗すればよいのか?
僕が思うに、対抗する方法はない、と思う。 対抗することをあきらめる以外にない…。(ほんとうにそうなのか?) ちからを抜いて、なるようになれ、とすれば、案外、どこかで落ち着くのではないか。(←これが僕の考える中で唯一の希望なのだ! 嗚呼!)
いやいや、そんな単純なものではないかもしれない。「ホール」のむこうは、狂気の世界かもしれない。 じゃあどうすれば…??
ようするに…それ以上はわからないということです(笑)。
ということで、この話はここでお仕舞いにしましょう。
わざわざ「エントロピー」という言葉を使って書かねばならぬ内容ではなかったですが… まあ、使ってみたかったのです。 (使ってみたかった「エントロピー」~♪)
物理の世界では、エントロピーは“正”の方向にしか流れないこととなっていますが、しかし…
オーストリア・ウィーン生まれの物理学者ボルツマンは、エントロピーの概念を、「原子」というまだ発見されていなかった粒子の運動として空想して、それを統計的に処理して表す計算方法を見つけた。
このボルツマンの考え方は、元々は、イギリスのJ・C・マックスウェルのはじめたものである。そもそも「熱」とは何だろう? それは「原子」の運動エネルギーだ…。
そのマックスウェルは、しかし、自分のつくったその考え方が根本的にもつ「問題点」を自ら指摘している。
それが「マックスウェルの悪魔」である。
熱力学を統計的に考えていくと、確率的にこうなる――というながれの論理になる。そうすると、99.999…%はOKだが、わずかに、熱力学第2法則つまりエントロピー増大の法則に違反する可能性が、(ほんのわずかではあっても)残ってしまう…、「絶対に不可逆である」とその法則ではうたっているのに。 未来の「可能性」が100億通りもあったとしたら、そのうち1通りは、「分散した熱が(偶然に)集まって元に戻る」なんてことも起こりうるということになるのではないのか? 統計的手法のそういう「あやふやさ」に天才マックスウェルは気づいていたのである。
「こんなヤツ(悪魔)がいたら、熱力学の法則は成り立たなくなる、それは困るんだよなあ…」と。
コイツが、“負”のエントロピーをこっそりと運びこむやんちゃボーイである。
そんな悪魔がいるんですかねえ…、僕のなかにも?










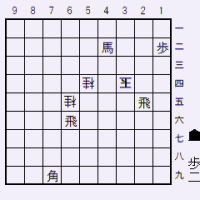
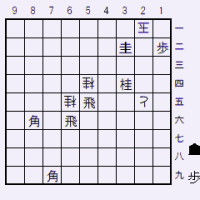
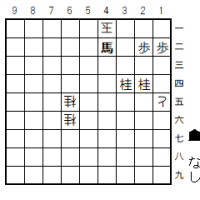
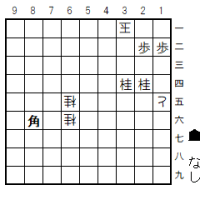
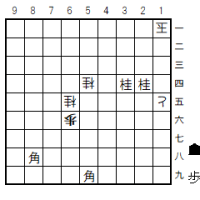
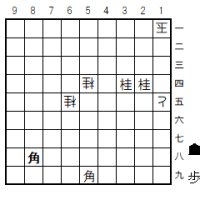
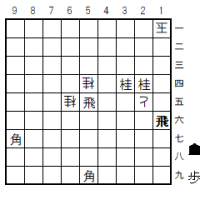
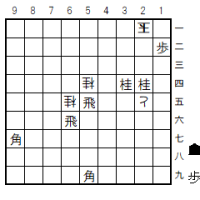
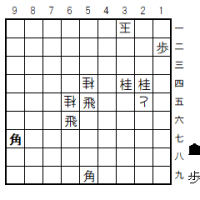
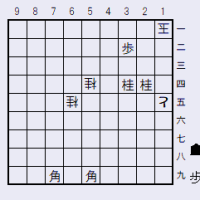





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます