2012年6月14日(木) 大飯原発の再稼働
5月6日未明に、国内の全原発(廃炉4基を除く50基)が停止した事態を受けて、当ブログに
全原発停止 (2012/5/12)
の記事を投稿し、当面の方策について私見述べて、早、1か月以上になる。
この間、夏場の電力需要期等を前にして、各方面の多くの動きがあった。政府としては、当面の焦点である大飯原発の再稼働に向けて、関係自治体の説得を重ねた。一方、不足が見込まれる電力会社管内での、具体的な節電策の検討、関西広域連合の集まり、などや、国会の場でも、原発事故を巡る対応等の検証も進められた。
夏場の数か月に限定して原発を再稼働する大阪市等の案、原発の是非について都民が投票するという条例案の話、今後のエネルギー政策の方向に対する選択肢案 等も示された。
更に、原発事故の当事者である東電が、電気料金の値上げ案を発表したことで、電力事業者の選択なども話題となり、一層、錯綜している。
こんな中、大飯原発の立地自治体である福井県知事の要請を受けた形で、さる6月8日夜、野田総理が、国民に向けて、原発の再稼働の必要性を訴える記者会見を行ったことで、状況は変化しつつあるようだ。
本ブログで、原発関連を取り上げるのは、久しぶりだが、漸くにして、地に足の付いた、具体的な動きが出て来たことで、やや、ホッとしているところである。
この総理の発表は、内容的には、新たな事項は殆ど無く、以前と、余り変わってはいないのだが、説明手続きが、丁寧であったことや、都市部の電力需要を賄うのに貢献している、と認めて貰った事なども、地元としては、心情的に嬉しかったこともあるだろうか。
原発の安全性については、県独自の専門家による安全委員会としても、承認したことは、不信感が消えない、国レベルの言う安全性に、客観性を持たせる点でも大きな意味がある。
一両日中に、大飯町として正式に容認する方向のようで、それを受けて、西川福井県知事が、野田総理に、直接、同意の旨を伝えると言う。4月には、再稼働に同意する意向を示していた大飯町としては、苦しい電力事情への協力で貢献する一方で、雇用の場の確保や、自治体への財政的な支援も欲しかったのであろうか。
関係自治体の同意・了解が得られれば、政府として、最終的に、GOサインを出すこととなろう。


福井県の原発立地状況 (原発銀座! 黒印が現用) 大飯原発(手前が3,4号機)
ただでさえ厳しい経済状況にある現在、一日も早く原発を再稼働して、必要な電力エネルギーを確保し、社会生活や経済活動の活性化につなげていきたいものだ。
大飯原発の2機を再稼働しても、関電管内の電力不足は
15%→8%
程度となるだけで、節電が厳しく要求される状況は、無くなりはしないようだ。
従来の規制組織(安全・保安院)で進めて来たストレステストについて、新組織が発足すれば、今後どのように扱われるようになるかは、やや不明だが、保安院のサイトによれば、原子力安全委員会の確認が終わったのは、現時点では大飯原発3,4号機だけだが、それに続く原発として、四国電力の伊方原発3号機に関して、保安院が終了し、原子力安全委員会で確認が進められている。
一方、5月に入って、一次テスト終了の報告書も、新たに、3件提出されており、リストに載って再稼働に向けて準備が進められている原発は、22基に昇っている。
今後は、大飯原発を皮切りに、停止中の原発の再稼働の方向が検討される事となるだろうか。
今回の福島第一原発の事故の経験を踏まえれば、特に、心情的には、原発は怖い、もう、原発は使いたくない、というのが、大半の国民の思いだろう。
でも、一方、理性的に考える時、原発なしで、この夏場以降の需要期は乗り切れるのか、ここ2~3年の、社会や産業や生活は大丈夫か、気になるところだ。勿論、長期的な日本のエネルギー政策の方向性も、重要だ。
当面の需要に対して、新エネルギーによる供給の見通しがまだ見えないだけに、節電の工夫だけでは、限界があり、社会全体が、草臥れて、萎縮する一方になってしまう可能性もある。
総理も言っているように、今回の再稼働は、あくまで暫定的なものだが、当面のエネルギーの不足を補い、化石燃料に対する輸入リスクなど、不測の事態に対する備えも考慮すれば、当面、出来るだけ余裕を持たせながら原発を稼働し続けるのが妥当であろう。夏場だけ原発を動かすという、中途半端な慌しい案は、取るべきではない。
前から言っているように、原発を再稼働させて、数年間様子を見ながら、この間得られる多くの知見も加えて、その後の方向づけを行っていけばよい、と、少し、気持ちを楽にして対処したいものだ。
改めて、停止している原発を、再稼働した場合、果たして安全性は大丈夫なのだろうか。
地元の専門家委員会も、言っているように、安全対策として、行われた、あるいは、行われようとしている諸対策は、現時点で分っている限りの、広範な知見が盛り込まれていて、必要とするミニマムは確保されている、と言うことだ。
即ち、ミニマムとは、各地の原発に、今後、福島第一を襲ったと同じレベルの、地震や津波が来た場合、びくともしないわけではなく、まだまだ、不十分な点はあるのだが、今回の事故の様な、全電源喪失状態に至って、炉心損傷の事態や、爆発事故を起こす事態は、回避できるのだ。最も恐れる最悪の事態には至らないような電源設備の配置等がなされ、非常時の訓練も行われている、ということだ。
言われているように、新たな規制組織の発足は、秋頃になるし、2次ストレステストについても、今後の課題だ。又、3年ほどの時間がかかる下記の様な、長期的な対策
・免震棟の建設
・防波堤のかさ上げ
・除染フイルター付きベント
等も、残されており、今後の重要な課題である。
現時点で、100点満点の安全対策を期待する余り、それが出来ない限りは稼働は認めない、などと言うのは、理想論に偏っており、要求する一方だけで、現実を直視しない姿勢と言えようか。
今回の総理の意見表明についてNHKは、“国論を二分する中で”、との形容詞を冠した。
原発については、原発自身の方向づけや、当面の再稼働について、明確な方向が固まっている訳ではないが、国論を二分している、との表現は妥当だろうか。自分としては、大変驚いた言い方ではある。
何事にも、反対意見があるのは正常なことだが、自分は、国論が2分している、とは思わない。
然らば、NHKは、国論をほぼ一つにするには、どうすればいいと考えているのだろうか。どのような提案を持っているのだろうか、聞きたいものだ。
政府の方向を支持すべきだ、等とは言わないが、公共放送を建前とするマスコミとして、社会の木鐸としての誇りをもつのなら、国家の方向性について、当面する原発の再稼働について、具体策は示さないまでも、示唆することは、出来る筈である。












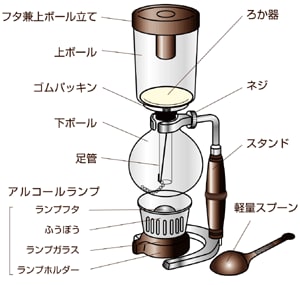









 シラン(拡大)
シラン(拡大)






