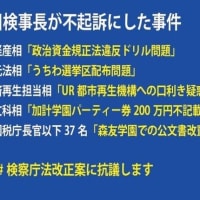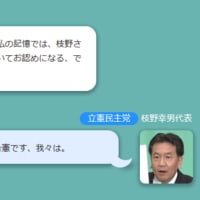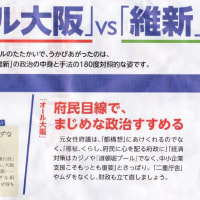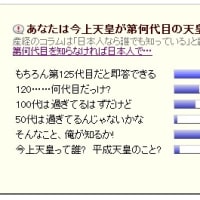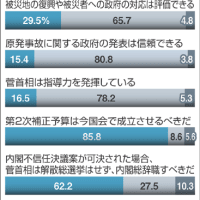先日、古書市で見かけて購入した。
著者の瀧川政次郎(1897-1992)は、法制史学者で、東京裁判で嶋田繁太郎の副弁護人を務めた人物。
本書の旧版は、占領終了直後の1952年に上巻が出版され、翌年に下巻が出版された。
この新版は、奥付によると、1978年の1月に上巻が、同年2月に下巻が出版されたとある。
さらに、2006年には1冊本として慧文社から出版された。これは現在も購入できるようだ。
本書の存在は、東京裁判関連の論考で時々出てくるので以前から知っていたが、読む機会はなかった。
東京裁判批判の古典と言えるだろう本書ではどのような主張がなされているのか、興味をもって読んでみた。
上巻には、まず「新版への序」があり、「旧序」、そして本編へと続いている。
しかしその主張は、こんにちでもよく見る東京裁判批判のオンパレードという感じで、やや辟易した。
曰く、
・「文明の裁き」を名乗るが、戦勝国による報復でしかない
・事後法による裁きであり、正当性はない
・欧米の白人による人種偏見の産物である
・わが国の戦争は侵略ではなく自衛戦争であった
・ハル・ノートは最後通牒であり、わが国は米国に開戦に追い込まれた
等々。
著者は、「新版への序」では、私がまるで評価していない林房雄の「大東亜戦争肯定論」について、「私の太平洋戦争史観と同一」「東京裁判に対する正しい認識」と述べている。
しかし、考えてみれば、東京裁判で弁護側に立った著者からそうした主張が出てくるのは当たり前で、それがこんにちまで続く東京裁判批判の源流となっているのだろう。
ただ、その筆致はかなり荒い。
これが法律家の文章かと思うほど、感情的に書かれている。
以前、やはり東京裁判で弁護人を務めた清瀬一郎の『秘録 東京裁判』を読んだことがある。同書にも同趣旨の裁判批判があったと思うが、その時にはこんな荒さは感じなかったように記憶している。
あまり感心しないで読み進めていった。
ところが、上巻の半ば過ぎに、こんな箇所があるのが目を引いた。米国人弁護人が国家弁護よりも個人弁護に重点を置いたのに対し、日本人弁護人は個人弁護よりも国家弁護に重点を置く者が多かったという点を説明する中での記述である。
(引用文中の〔 〕内は、ルビ、または引用者による説明である。太字は引用者による。以下全て同じ)
著者は、戦前・戦中期のわが国の在り方について、必ずしも肯定しているわけではないのではないか。当時の軍や政府の指導者層について、むしろかなり批判的な人物なのではないかと気がついた。
上巻の「あとがき」には、こんな記述もあった。
どうも、冒頭に挙げたような、こんにちよく見る、古典的かつ単純な東京裁判批判だけの本ではないようだ。
東京裁判批判本としてはかなり特異な主張が見られるので、当ブログで紹介することにした。
(続く)
著者の瀧川政次郎(1897-1992)は、法制史学者で、東京裁判で嶋田繁太郎の副弁護人を務めた人物。
本書の旧版は、占領終了直後の1952年に上巻が出版され、翌年に下巻が出版された。
この新版は、奥付によると、1978年の1月に上巻が、同年2月に下巻が出版されたとある。
さらに、2006年には1冊本として慧文社から出版された。これは現在も購入できるようだ。
本書の存在は、東京裁判関連の論考で時々出てくるので以前から知っていたが、読む機会はなかった。
東京裁判批判の古典と言えるだろう本書ではどのような主張がなされているのか、興味をもって読んでみた。
上巻には、まず「新版への序」があり、「旧序」、そして本編へと続いている。
しかしその主張は、こんにちでもよく見る東京裁判批判のオンパレードという感じで、やや辟易した。
曰く、
・「文明の裁き」を名乗るが、戦勝国による報復でしかない
・事後法による裁きであり、正当性はない
・欧米の白人による人種偏見の産物である
・わが国の戦争は侵略ではなく自衛戦争であった
・ハル・ノートは最後通牒であり、わが国は米国に開戦に追い込まれた
等々。
著者は、「新版への序」では、私がまるで評価していない林房雄の「大東亜戦争肯定論」について、「私の太平洋戦争史観と同一」「東京裁判に対する正しい認識」と述べている。
しかし、考えてみれば、東京裁判で弁護側に立った著者からそうした主張が出てくるのは当たり前で、それがこんにちまで続く東京裁判批判の源流となっているのだろう。
ただ、その筆致はかなり荒い。
これが法律家の文章かと思うほど、感情的に書かれている。
以前、やはり東京裁判で弁護人を務めた清瀬一郎の『秘録 東京裁判』を読んだことがある。同書にも同趣旨の裁判批判があったと思うが、その時にはこんな荒さは感じなかったように記憶している。
あまり感心しないで読み進めていった。
ところが、上巻の半ば過ぎに、こんな箇所があるのが目を引いた。米国人弁護人が国家弁護よりも個人弁護に重点を置いたのに対し、日本人弁護人は個人弁護よりも国家弁護に重点を置く者が多かったという点を説明する中での記述である。
(引用文中の〔 〕内は、ルビ、または引用者による説明である。太字は引用者による。以下全て同じ)
初めて市ヶ谷法廷の金網を張った控室で嶋田被告に面会したとき、この提督が、
瀧川さん、私はわれわれ海軍の者どもが明治以来長い間努力して建設してきた日本の海軍が、他国を侵略するための海軍であったと言われることが心外でたまらないんです。この申し開きをするために私は生き永らえているのです。どうか瀧川さん、日本の海軍のために弁護して下さい。この嶋田一身の弁護などということは、お考えくださらなくて結構です。と言われたので、大いに感激した。私はそれまでの長い間、大たい教壇生活を送ってきた人間で、弁護士を開業したのは、東京裁判に関係して以来のことである。故に私に弁護士としての自覚などありようはなく、私はただ日本国民の一員としていわれなき検察団の起訴状を撃破してくれようというのが、私の東京裁判に関係した動機であった。私が東京裁判に関係した当時の感情を率直に告白すれば、われわれは東京裁判の被告となった二十五人のうち、殊に軍関係の被告たちに対しては、大して同情をもてなかった。今や連合軍に捕われの身となって、家族に面会するにも弁護人の手を煩わさねばならなくなったこれら被告人たちは、われわれ弁護人に対して至極鄭重であるが、彼らは戦争中いったいわれわれ法律家をどう見ていたか。この人たちは世が世であれば、われわれ法律家を木の端とまでもみなかった人たちではなかったか。自然科学者は、戦力増強に貢献するから、その卵である理工科の学生は生かしておかなければならぬ。何かあれば軍を批判したがる法科経済科のやつどもは、戦争の役に立たぬどころか、国家の蠧賊〔とぞく〕である。そんな徒輩は早く前線へつれていって殺してしまった方がよい、という考えで、学徒動員を行い、われわれの子弟をして『聞けわだつみの声』の哀歌を遺さしめたのは、どこのどやつか。それを思うと、われわれは腹の底まで煮えくりかえる。「責め一身に」と陛下に御迷惑をかけないようにしようという彼らの心底は殊勝である。しかし、それほど陛下の御為を思うなら、なぜ陛下が我が赤子とまで愛重せられるわれわれの子弟を一銭五厘の葉書と同じように取扱ったのか。「軍馬は一頭最低二百円するから、一銭五厘の葉書一枚でいくらでも集まるお前たちより大切だ」と、よくも面と向かってヌケヌケとほざいたな。そんな不届きな将校がおぬしたちの部下の全部であったとは言わぬが、まさかおぬしたちもそんなことは知らぬとは言い切れまい。われわれはそんな不届きな将校でも、同朋だと思えばこそ、弁護に立つのだ。同邦人に対して罪万死に当る人間でも、敵国人によって裁判せられ、処罰されるということは、いわれなきことである。故にわれわれは、その個人の弁護にも懸命の努力を捧げねばならぬ。そうは考えるものの、私としては個人弁護にはどうしても力が入らない。国家弁護に重点を置こうとした弁護士諸君の考えも、大たいこれと同じようなものではなかったか。(上巻 p.104-106)
著者は、戦前・戦中期のわが国の在り方について、必ずしも肯定しているわけではないのではないか。当時の軍や政府の指導者層について、むしろかなり批判的な人物なのではないかと気がついた。
上巻の「あとがき」には、こんな記述もあった。
武力を持たない国が生きてゆく道は、正義を主張する外にはない。私は今日の日本における国家再建の出発点は、東京裁判を正しく批判することであると思ふ。〔中略〕日本人は須〔すべか〕らく占領される以前の日本人の平常心を取戻して、東京裁判を正しく批判すべきである。〔中略〕しかし、われらの精神的原状回復は、慎重になされなければならない。戦争中の尊大、倨傲に逆戻りすることは、正常心への復帰ではない。われわれ日本人は、むかし「何ものをも忘れず、何ものをも学ばなかった」と非難されたフランス革命当時の保守主義者の愚を再びしてはならない。われわれは、東京裁判の苦い経験から幾多の教訓を学びとらなくてはならない。この際戦争中の極端な右傾思想に逆戻りすることは、この戦争に散華した百万の青年を犬死にさすことである。回復すべきものは、正を正とし、義を義とする国民の正常心である。キーナン検事の尻馬に乗って、軍閥者流を罵倒するやうなことは、もういい加減にした方がよい。東京裁判で罰せられたのは、二十五被告にあらずして、日の丸の旗を打ち振って戦つたわれわれ国民全体である。(上巻 p.224-225)
どうも、冒頭に挙げたような、こんにちよく見る、古典的かつ単純な東京裁判批判だけの本ではないようだ。
東京裁判批判本としてはかなり特異な主張が見られるので、当ブログで紹介することにした。
(続く)