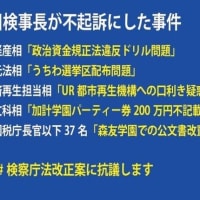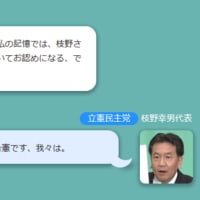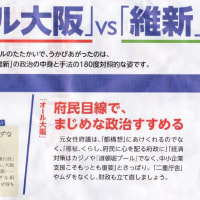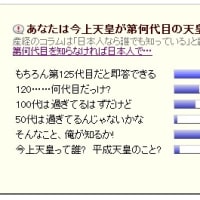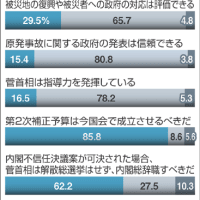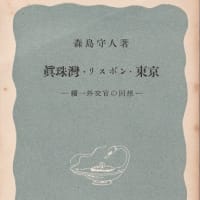先に浅羽通明『右翼と左翼』の感想で少し触れた呉智英のデビュー作『封建主義、その論理と情熱』(情報センター出版局、1981)の改題増補版。現在は双葉文庫に収録されており、読み継がれているようだ。
呉智英は民主主義や人権思想を批判し、「封建主義者」を自称する評論家。そのスタンスはデビュー作である本書から一貫している。といっていわゆる保守系の評論家とはまた異なる立場を取っており、どちらかというと本質的には左翼に近いと私は見ている。またマンガ評論でも多大な業績を残している。
以前は愛読していたが、数年前から見方が変わり、現在はあまり評価していない。
本書は2年ほど前に処分してしまって手元にはないのだが、一度述べてみたかった本なので、記憶とメモに基づいて感想を記す。
序章で、イラン革命の例を挙げ、民主主義的思考の限界を示し、呉智英はこう述べる。
《これから私は、常識とされてきた思考の公理を封建主義の視座から次々にひっくり返していく。学校の授業や教科書で教えられ、新聞や雑誌に掲載されている封建主義への非難が近代の迷妄にすぎないことを確証していく。
自由や平等は民主主義に固有なものではなく、むしろ、封建主義のほうが実体のある自由や平等を考えている。また、植民地主義・侵略主義と最も果敢に闘ったのも封建主義である。
(中略)
そして曇りなき目で封建主義が眺められるようになった時、行きづまりを露呈させている各種の現代思想にくらべ、封建主義がはるかに可能性に満ちた思想であることが明らかになるのである。》
しかし、呉智英のこの意気込みは実現されたとは言い難い。
この人は、民主主義を批判する手段として封建主義を標榜しているだけであり、実際には民主主義の改良者としての役割を果たしているにすぎないのではないかということは以前から漠然と考えていたが、小谷野敦が『バカのための読書術』(ちくま新書、2001)で呉智英を評価しつつも批判し、「隠れ左翼」と指摘しているのを見て、ますますその思いを強くした。
本心は民主主義の改良ではないかもしれない。しかし彼にはその知識を動員して民主主義の限界を批判することはできても、有効な代案を出すことには成功していない(仇討ち復活など、全く有効ではない)。
若いころに読んだときには気付かなかったが、2年ほど前に読み返したとき疑問に思った。
そもそも「封建主義」とは何か?
「封建制度」というものはある。「封建的」という言葉もある。しかし「封建主義」という言葉はあるか?
呉智英は、なんと『広辞苑』に「封建主義」の項目はない!と驚いた上で、こう述べる。
《つまり、定義しにくい、もしくは、定義に値しない曖昧な概念だと封建主義は考えられているわけである。
(中略)
「封建主義」の通常の印象に最も近いものが「封建的」という語で、その説明には、「封建制度に特有の性格を持っているさま。俗には、専制的で目下の者の言い分を聞こうとしないさまなどにいう」とある。この説明の前半部分は、辞書によくある同義反復型の説明にすぎず、本来の説明は、むしろ後半部分なのだが、さて期待して見てみると、「俗には」という断り書きのある解釈しかない。ここに、『広辞苑』が「封建主義」という言葉を採り上げず、「的」というどんな言葉にもとっつけることができる曖昧なかたちのほうを採用した賢明さが現われている。それは「封建主義」と明確に言いうるようなものはなく、ソレ的なものが、一般に何となく通用している現状を反映しているからだ。》
この文章は何だろう。最初は定義しにくいから載っていないと言い、後では封建主義ではなく封建的が通用しているという。 そもそも「封建主義」という言葉は81年当時実際に使われていたのか? feudalism もism だから封建主義と訳せないことはないが、普通は封建制度と訳すのではないか。自由主義や共産主義と並んで封建主義というものがあるかのような呉智英の説明は苦しい。
そのあと、『新明解国語辞典』では、「封建主義」も「封建的」も載っていて同じような説明がなされているとあるが、私は、「封建主義」という語は、「封建的」と同義の、悪い意味で使われる一種の俗語であり、広辞苑が採用していないのも理解できないわけではなく、それをオリジナルな思想としてとらえるのは呉智英の独創ではないかと考えている。
呉智英自身、あとでは次のように述べている。
《ここで一つ、あたりまえのことながら往々にして忘れられていることを指摘しよう。封建制度なるものは、たしかにあった。しかし、主義といえるような「主義」としての封建主義は、封建時代にはなかったはずだ。》
そのとおりである。誰が忘れているというのだろう。封建時代にはおろか、近代以降にもあったと言えるかどうか、私は疑問である。
さらに呉智英はこのように述べる。封建主義は民主主義のネガである。民主主義を進めていくに当たって、古い現実をひっくるめて「封建主義」という名称を与えた。しかし、民主主義に欠点はないのか。それがあきらかになれば、封建主義は単なる民主主義のネガではなく、「新しき封建主義」の可能性が現われてくるはずである、と。
確かに、民主主義にも欠点はあるだろう。それが明らかになることで「新しき封建主義」の可能性が現われるという理屈がよくわからない。
民主主義の欠点は、修正民主主義として克服されるのではないか。仮にその過程で「古い現実」を参考にすることがあったとしても、それは参考にすぎない。「新しき封建主義」を提唱するならば、それは民主主義を否定するところから始まらなければならないはずだ。つまり、君主による専制や、奴隷制を含めた身分制を肯定し、思想や宗教の自由や、生存権を否定する立場を取るはずだ。ところが、呉智英の主張はそのようなものではない。
「自由と平等は、封建主義で解決できる」という見出しの箇所がある。
例えば、言論の自由は、①衆知を集める、②異なる意見への寛容、③反政府的言論というように分けられるが、これらはいずれも民主主義特有のものではないという。
平等についても、イスラエルの問題、リベリアの黒人奴隷輸出のように、民主主義では解決できない現象があるという。
だからといって、封建主義がどう有効なのか、どう民主主義より優れているのかは明らかにされていない。そうした点が非常に不満だ。
また、次のような記述がある。
《こういった研究やマンガ〔深沢註:竹内好、島田虔次による儒教再評価、白川静『孔子伝』、諸星大二郎『孔子暗黒伝』〕を知ってから、私は、儒教を中心にして仏教・道教をも加味した封建主義にはっきりと目覚めた。》
《そもそも、無意味に“個”の犠牲を強いる因襲的な家族主義・ムラ主義なんていうものは、封建主義とは関係ないのだ。『論語』陽貨篇にこうある。子曰く、郷源は徳の賊なり》
どうも、呉智英の言う封建主義とは、儒教を中心にして仏教・道教をも加味したものであるらしい。
しかし、「無意味に“個”の犠牲を強いる因襲的な家族主義・ムラ主義」が「封建的」なものであるというのは、一般的な理解だろう。
ならば、呉智英は「封建主義」と言うよりも、単に「東洋思想」という言葉を用いるべきではないか。あるいは「呉智英主義」でもいい。封建主義の復権を掲げると称する一方で、封建主義とは本来そのようなものではないと、社会通念とは異なった独自の解釈を示すのは、フェアでないと思う。
「すべからく」の誤用の指摘や、「支那」を差別語とする見方の否定、新聞報道が「弁護士」などの職業はそのままなのに「大工さん」は「さん」付けすることなど、昔、本書から学んだことは数多いし、影響も受けている。
しかし、年を経てから読み返すと、著者の主張の根本的な部分に、疑問を覚えざるを得ない。
また、著者は確かに博識なのだが、その主張の全てが妥当とは言い切れないこともようやくわかってきた。
呉智英は民主主義や人権思想を批判し、「封建主義者」を自称する評論家。そのスタンスはデビュー作である本書から一貫している。といっていわゆる保守系の評論家とはまた異なる立場を取っており、どちらかというと本質的には左翼に近いと私は見ている。またマンガ評論でも多大な業績を残している。
以前は愛読していたが、数年前から見方が変わり、現在はあまり評価していない。
本書は2年ほど前に処分してしまって手元にはないのだが、一度述べてみたかった本なので、記憶とメモに基づいて感想を記す。
序章で、イラン革命の例を挙げ、民主主義的思考の限界を示し、呉智英はこう述べる。
《これから私は、常識とされてきた思考の公理を封建主義の視座から次々にひっくり返していく。学校の授業や教科書で教えられ、新聞や雑誌に掲載されている封建主義への非難が近代の迷妄にすぎないことを確証していく。
自由や平等は民主主義に固有なものではなく、むしろ、封建主義のほうが実体のある自由や平等を考えている。また、植民地主義・侵略主義と最も果敢に闘ったのも封建主義である。
(中略)
そして曇りなき目で封建主義が眺められるようになった時、行きづまりを露呈させている各種の現代思想にくらべ、封建主義がはるかに可能性に満ちた思想であることが明らかになるのである。》
しかし、呉智英のこの意気込みは実現されたとは言い難い。
この人は、民主主義を批判する手段として封建主義を標榜しているだけであり、実際には民主主義の改良者としての役割を果たしているにすぎないのではないかということは以前から漠然と考えていたが、小谷野敦が『バカのための読書術』(ちくま新書、2001)で呉智英を評価しつつも批判し、「隠れ左翼」と指摘しているのを見て、ますますその思いを強くした。
本心は民主主義の改良ではないかもしれない。しかし彼にはその知識を動員して民主主義の限界を批判することはできても、有効な代案を出すことには成功していない(仇討ち復活など、全く有効ではない)。
若いころに読んだときには気付かなかったが、2年ほど前に読み返したとき疑問に思った。
そもそも「封建主義」とは何か?
「封建制度」というものはある。「封建的」という言葉もある。しかし「封建主義」という言葉はあるか?
呉智英は、なんと『広辞苑』に「封建主義」の項目はない!と驚いた上で、こう述べる。
《つまり、定義しにくい、もしくは、定義に値しない曖昧な概念だと封建主義は考えられているわけである。
(中略)
「封建主義」の通常の印象に最も近いものが「封建的」という語で、その説明には、「封建制度に特有の性格を持っているさま。俗には、専制的で目下の者の言い分を聞こうとしないさまなどにいう」とある。この説明の前半部分は、辞書によくある同義反復型の説明にすぎず、本来の説明は、むしろ後半部分なのだが、さて期待して見てみると、「俗には」という断り書きのある解釈しかない。ここに、『広辞苑』が「封建主義」という言葉を採り上げず、「的」というどんな言葉にもとっつけることができる曖昧なかたちのほうを採用した賢明さが現われている。それは「封建主義」と明確に言いうるようなものはなく、ソレ的なものが、一般に何となく通用している現状を反映しているからだ。》
この文章は何だろう。最初は定義しにくいから載っていないと言い、後では封建主義ではなく封建的が通用しているという。 そもそも「封建主義」という言葉は81年当時実際に使われていたのか? feudalism もism だから封建主義と訳せないことはないが、普通は封建制度と訳すのではないか。自由主義や共産主義と並んで封建主義というものがあるかのような呉智英の説明は苦しい。
そのあと、『新明解国語辞典』では、「封建主義」も「封建的」も載っていて同じような説明がなされているとあるが、私は、「封建主義」という語は、「封建的」と同義の、悪い意味で使われる一種の俗語であり、広辞苑が採用していないのも理解できないわけではなく、それをオリジナルな思想としてとらえるのは呉智英の独創ではないかと考えている。
呉智英自身、あとでは次のように述べている。
《ここで一つ、あたりまえのことながら往々にして忘れられていることを指摘しよう。封建制度なるものは、たしかにあった。しかし、主義といえるような「主義」としての封建主義は、封建時代にはなかったはずだ。》
そのとおりである。誰が忘れているというのだろう。封建時代にはおろか、近代以降にもあったと言えるかどうか、私は疑問である。
さらに呉智英はこのように述べる。封建主義は民主主義のネガである。民主主義を進めていくに当たって、古い現実をひっくるめて「封建主義」という名称を与えた。しかし、民主主義に欠点はないのか。それがあきらかになれば、封建主義は単なる民主主義のネガではなく、「新しき封建主義」の可能性が現われてくるはずである、と。
確かに、民主主義にも欠点はあるだろう。それが明らかになることで「新しき封建主義」の可能性が現われるという理屈がよくわからない。
民主主義の欠点は、修正民主主義として克服されるのではないか。仮にその過程で「古い現実」を参考にすることがあったとしても、それは参考にすぎない。「新しき封建主義」を提唱するならば、それは民主主義を否定するところから始まらなければならないはずだ。つまり、君主による専制や、奴隷制を含めた身分制を肯定し、思想や宗教の自由や、生存権を否定する立場を取るはずだ。ところが、呉智英の主張はそのようなものではない。
「自由と平等は、封建主義で解決できる」という見出しの箇所がある。
例えば、言論の自由は、①衆知を集める、②異なる意見への寛容、③反政府的言論というように分けられるが、これらはいずれも民主主義特有のものではないという。
平等についても、イスラエルの問題、リベリアの黒人奴隷輸出のように、民主主義では解決できない現象があるという。
だからといって、封建主義がどう有効なのか、どう民主主義より優れているのかは明らかにされていない。そうした点が非常に不満だ。
また、次のような記述がある。
《こういった研究やマンガ〔深沢註:竹内好、島田虔次による儒教再評価、白川静『孔子伝』、諸星大二郎『孔子暗黒伝』〕を知ってから、私は、儒教を中心にして仏教・道教をも加味した封建主義にはっきりと目覚めた。》
《そもそも、無意味に“個”の犠牲を強いる因襲的な家族主義・ムラ主義なんていうものは、封建主義とは関係ないのだ。『論語』陽貨篇にこうある。子曰く、郷源は徳の賊なり》
どうも、呉智英の言う封建主義とは、儒教を中心にして仏教・道教をも加味したものであるらしい。
しかし、「無意味に“個”の犠牲を強いる因襲的な家族主義・ムラ主義」が「封建的」なものであるというのは、一般的な理解だろう。
ならば、呉智英は「封建主義」と言うよりも、単に「東洋思想」という言葉を用いるべきではないか。あるいは「呉智英主義」でもいい。封建主義の復権を掲げると称する一方で、封建主義とは本来そのようなものではないと、社会通念とは異なった独自の解釈を示すのは、フェアでないと思う。
「すべからく」の誤用の指摘や、「支那」を差別語とする見方の否定、新聞報道が「弁護士」などの職業はそのままなのに「大工さん」は「さん」付けすることなど、昔、本書から学んだことは数多いし、影響も受けている。
しかし、年を経てから読み返すと、著者の主張の根本的な部分に、疑問を覚えざるを得ない。
また、著者は確かに博識なのだが、その主張の全てが妥当とは言い切れないこともようやくわかってきた。