



氏子狩帳によれば、おじの祖先は良材を求めて木曽谷から伊那谷へと移り、明治の初めに松本の地に定住したのだという。そこは、小さな川が城の外堀へと流れ込む場所であり、轆轤を回す動力を確保するのに適していたらしい。いかに惟喬親王の勅許があるといったところで、深山とはいえ自由に木を切ることが許される時代ではなく、漂白の民からも租税を徴収すらため定住をある面強要されもしただろう。それで住み着いたのが、徳川の世に定住者を支配した大名の住まいの境界べりだというのも皮肉な話である。その場所で、2代の木地師の家業が潰えたのは、5年ほど前のことである。江戸の中ごろ(?)までは完全に足跡をたどれる木地師の伝統が、ここで途絶えたのである。ことによると、1000年くらい、あるいはもっと古く奈良・飛鳥の時代に遡る、伝承された技であったかもしれない。それが今の時代になくなるとは、大変なことだと自分も感じた。
高度成長期には、白樺細工のこけしを考案し、胴の部分だけを轆轤で削ってそこに絵と文章を記したお土産を考案した。文は確か、「山を想えば人恋し 人を想えば山恋し」だった気がする。おりからのディスカバージャパンの旅行ブームで、とぶように売れたらしい。しかし、その仕事が面白かったか、満足していたかといえば、どうもそうではなかったと思われる。おじは字も絵もうまかったが、受け継いだ轆轤の仕事こそしたかったのだ。晩年は、売ることを考えず思いついた作品の製作に精を出した。売ることを考えずというより、気に入った作品は非売品となった。そうした作品がいくつもあったので、写真をとり作者のコメントをつけた図録にしたらどうかと考えた。しかし、そのときにはコメントを考えるだけの余力はおじの体力にはなかった。撮影した写真は私の手元に保存されたまま、作品は屋根裏のダンボールの中に眠っている。
『脊梁山脈』は、信州木地師(こういう言葉があるかどうか知らないが、乙川氏の造語だろうか)の後を東北までたずね、古代史に木地師の先祖を探すという物語である。主人公は深山を歩いて木地師の足跡を墓でたどり、図録を完成させている。物語の中とはいえ初志を貫徹した主人公にひきかえ、中途半端に聞き書きをしたままになっている自分を申し訳なく思う。作品の中から心ひかれる部分をひいてみよう。
天保の飢饉で行きつめた彼らは南下するかわりに脊梁山脈を越えようとして、多くが力尽きたのだろう。縦長の墓碑には戒名を刻んだものと無銘のものがあって、小さいものは子供の墓のようであった。再訪は考えられない山中で野石に刻んだ菊花は一族の誇りであり、永遠の供養であったに違いない。死別の哀しみは乗り越えるしかないが、強い同族意識で結ばれながら、居留と漂白の相克から命懸けの旅の途中で離散するのも徙移の民の宿命であろう。山脈の向こうに豊かな生活が待っているとは限らないが、生き延びて墓碑を建てた人たちは越えていったと感じた。手が届きそうなところに分水嶺の尾根が見えているからであった。北限の木地師たちも同じ活路を選んだに違いないと思った。
尾根から尾根へと漂白する木地師の暮らしは、どんなものだったのだろうか。まして飢饉となれば平地でも人は死に絶えるのだから。いつか、南木曽から清内路を通って伊那へ抜けたことがあった。そのとき一緒だった木曽福島の生駒勘七先生から、山の中に茗荷が生えていたら、そこは木地師の住処の跡だ。木地師は移動するときに、茗荷の根を持っていって家のそばに植えるのだと教えてもらった。 今となっては、漂白の民の暮らしは想像もできない。
写真はおじの作品の一部である。最初は、小説の中に何度か登場する百万頭である。その他の作品は、おじは生前こんなことをいっていた。轆轤で削っているいるうちに、その木にあった形が自然にできてくる。まるで、木の中に形が眠っているとでもいいたいようだった。手仕事の極意なのだろう。










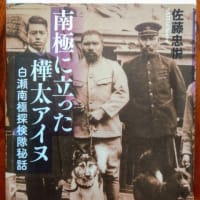

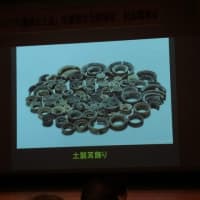


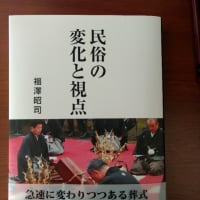




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます