表題は小熊英二が芳川弘文館のPR誌「本郷」に書いているタイトルです。この頃の雑誌『民文化人類学』に、日本人の人類学者が母国語(日本語)で自国の文化について書いた論文は海外では評価されず、海外の人類学者が英語で日本について書いた論文は評価されている。自国文化について母国語で書かれた論文が、英語でないというだけで英語圏(多くの研究者が英語圏)の研究者に正当に評価されないのは理不尽だが、それが現実で、学問の国際化といって英語で論文を発表すればいいというのは真の国際化とは言えないが、悲しいことにそれが現実だ。といった、英語資本主義に抗したくても、世界の英語圧力にはかなわないという趣旨の文がありました。それを、もう少し学会の外にいる人間にもわかりやすく書いてくれたのが、表題の小熊の文章でした。
さらに、「英語化」の波が押し寄せている。申請を行ない、有期雇用先を探すのに、ドイツ語しか書けないのでは、選択幅が大きく狭くなる。そのため、みんな英語で論文を発表し、英語で申請書を書く。それをすれば、スイスやイタリア、アメリカやシンガポールで、契約先が見つかるかもしれない。アメリカの大学で学位をとったり、研究員生活を経験したりした人も多い。
そこで問題がある。日本の研究者で、日本を研究対象にしている人、たとえば歴史学や民俗学の研究者には、英語ができず、理論も学んでいない人がいる。当然ながら、そうした人が、日本国外の日本研究で位置を占めるのはむずかしくなってくる。人間だけでなく、日本語で発表した論文も同様である。
その結果、おきているのが、「日本研究におけるジャパン・パッシング(日本虫)」である。つまり、英語圏の日本研究が、日本語圏の日本研究を無視して、自己回転するようになってきているのだ。小熊英二「研究者サバイバル時代ー英語化する欧米学界ー」『本郷』№124
何ということでしょう。学問のグローバル化とは何をもたらしてくれるのでしょうか。これからは、日本史も民俗学も英語で論文を書かないと、業績として認められない時代となるのでしょうか。私たちのような、地方で地方の民俗学をしている者とは異質の「ミンゾクガク」がそこにあるように思われます。英語を使えない負け犬の遠吠えだといわれれば、そのとおりなのですが。










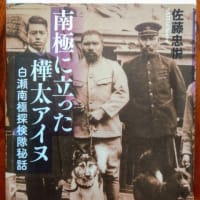

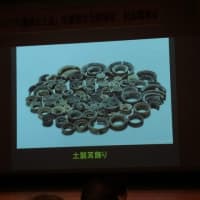


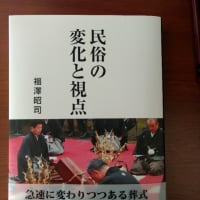




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます