Parasophiaという国際芸術祭が京都でやっている。市内数ヶ所に展示があって、メイン会場は京都市美術館。興味のあった崇仁小学校の展示は金土日のみだったので、とりあえず京都市美術館から行ってみることにした。良い天気だけれど、夕方からは雨の予報。
友人がスタッフをしているので、どんな感じか先に聞いた情報によると、市美の展示は映像作品が多く、ほんとうに全部を見ようとすると1日がかりとのことだった。
美術館の展示で映像を見るのが苦手だ。ブースに足を踏み入れたところからそれを見ることになるので、だいたい途中から見始めて、終わってもう一度見始めたところまでを見る体感は、仕方ないという諦めを予め含んでいる。だって映像自体が作っている時間をちゃんと見られない。だから余程興味をそそられなければ見る集中力を持てず、通り過ぎる。
でも映画館ではなくて美術館で展示するという方法を選んでいるからには、映像の時間自体を着席させて最初から最後まで見せたいという訳ではないということか。展示されていてもほとんどただ前を通り過ぎてしまう絵や彫像があることと同じことだろうか。でも美術館のような展示空間に映像作品を展示するときに鑑賞者の体がどうあるべきかについて、何か策が足りない気がする。
この会場下見の段階で作家が見つけた大きなガラスの展示ケースに収まる2体の彫刻がいいと思った。この場所で展示をするということを出発点にしている作品に興味深いものが多かった。
いちばん興味深かったのは、作家による作品ではなく、京都市美術館の普段は立ち入れない地下スペースに入れたことだった。地下は急に空気が冷え、数台のプロジェクターでこの美術館建造からの解説が投影されている。
戦後一時米軍に接収されていた時期があると知った。地下には靴磨きの英字の看板が残っている。
中ではバスケットボールをしたりもしていたらしい。
痕跡をめぐるおもしろさには、歴史の裏付けがある分、体感に厚みもある。既にある痕跡を改めて見る機会と導線をアートの文脈でつくることには明瞭な意味と意義があるし、そういうことをツアーパフォーマンスとしてやっている演出家もいる。
例えば、体を痕跡と捉えたときにその痕跡を改めて見るおもしろさということからアプローチできないだろうかと考えていた。
友人がスタッフをしているので、どんな感じか先に聞いた情報によると、市美の展示は映像作品が多く、ほんとうに全部を見ようとすると1日がかりとのことだった。
美術館の展示で映像を見るのが苦手だ。ブースに足を踏み入れたところからそれを見ることになるので、だいたい途中から見始めて、終わってもう一度見始めたところまでを見る体感は、仕方ないという諦めを予め含んでいる。だって映像自体が作っている時間をちゃんと見られない。だから余程興味をそそられなければ見る集中力を持てず、通り過ぎる。
でも映画館ではなくて美術館で展示するという方法を選んでいるからには、映像の時間自体を着席させて最初から最後まで見せたいという訳ではないということか。展示されていてもほとんどただ前を通り過ぎてしまう絵や彫像があることと同じことだろうか。でも美術館のような展示空間に映像作品を展示するときに鑑賞者の体がどうあるべきかについて、何か策が足りない気がする。
この会場下見の段階で作家が見つけた大きなガラスの展示ケースに収まる2体の彫刻がいいと思った。この場所で展示をするということを出発点にしている作品に興味深いものが多かった。
いちばん興味深かったのは、作家による作品ではなく、京都市美術館の普段は立ち入れない地下スペースに入れたことだった。地下は急に空気が冷え、数台のプロジェクターでこの美術館建造からの解説が投影されている。
戦後一時米軍に接収されていた時期があると知った。地下には靴磨きの英字の看板が残っている。
中ではバスケットボールをしたりもしていたらしい。
痕跡をめぐるおもしろさには、歴史の裏付けがある分、体感に厚みもある。既にある痕跡を改めて見る機会と導線をアートの文脈でつくることには明瞭な意味と意義があるし、そういうことをツアーパフォーマンスとしてやっている演出家もいる。
例えば、体を痕跡と捉えたときにその痕跡を改めて見るおもしろさということからアプローチできないだろうかと考えていた。














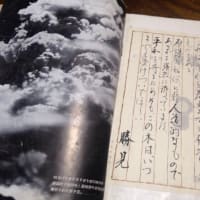
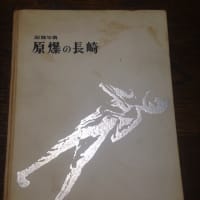




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます