捕鯨問題を唯一取り上げ続けて来てくれていた産経が、太地の苦悩の歴史を書いてくれています。
何と、一時は消滅の危機に見舞われながら、アメリカへの移民で乗り切ったという苦難の歴史もあるそうです。
その歴史が、太地に乗り込むシーシェパード達にも案外優しい目を向けているのだそうです。
産経ニュースより 2018.12.28
【明 治150年】第5部 地方(2)捕鯨文化守る太地 移民先の迫害が生んだ「寛容」
日本政府が国際捕鯨委員会(IWC)からの脱退を決めた。商業捕鯨が約30年ぶりに再開され、活気を期待する地方もある。 熊野灘を臨む捕鯨の町、和歌山県太地町もその一つだ。
11月上旬、太地町の岬で警察官の注視のもと、米国人の女性活動家がカメラを漁船に向けていた。捕鯨に圧力をかけているの だ。IWC脱退で監視は強まるとみられる。
2010年、捕鯨漁師を批判的に描いた作品「ザ・コーヴ」が米アカデミー賞を受賞して以来、町には世界各国から反捕鯨の活 動家が集まるようになった。
のどかな港町である太地町を活動家が闊歩(かっぽ)し、警察官が監視する。子供たちへの悪影響も懸念された。しかし町民は いたって冷静だ。太地町の宇佐川彰男教育長はこう語った。
「子供たちには外国人が悪いと思ってはいけない、考え方の違いを理解しなさい、と教えています」
教育長が諭すように話す、その背景には太地町の歴史と日本の歩みが関わっていた。
太地町は古式捕鯨発祥の地として知られる。網に追い込んだクジラを銛で仕留める方法で、捕鯨砲を使うノルウェー式捕鯨もあ る。捕獲したクジラは食用だけでなく、ひげは釣り竿に用いるなど余すことがない。
明治11年冬、太地町を悲劇が襲う。荒れ模様の熊野灘へ出航した漁船が遭難し、100人余りの漁師が命を落としたのだ。当 時「家の前を幾日も泣きわめきながら走る妻がいた」と言い伝えられる。甚大な被害をもたらし、古式捕鯨が途絶える端緒になっ た。
一家の稼ぎ手を失い、窮地に追い込まれた太地の人々を救ったのは、明治政府の移民政策だった。
明治24年、榎本武揚が外相に就任すると、外務省に移民課が設置される。国内の食糧問題の解決や日本の海外発展の観 点から、明治維新で海外に目が 向いたと同時に移民事業が本格化したのだ。労働力が余剰になっていた地方からは特に、移民が続出した。九州や中国地方は その中心地となり、米国本土へは 24年から30年間で25万人以上が渡ったという統計がある。
太地の人々も「慈雨を得たように渡航した」(太地町史)。渡航先の米国やオーストラリアでは捕鯨で培った腕を漁業で 生かし、彼らの送金で太地町は 息を吹き返した。第一次世界大戦時は、米西海岸で暮らす太地の人々が作ったシー・フードの缶詰が戦地に送られ、米兵の食 料になった。
しかし、第二次大戦に向かうにつれて米国で排日運動が高まり、迫害を受ける。日本軍の真珠湾攻撃後はスパイの嫌疑が かけられ、ほぼ全員が強制収容所に入れられた。
戦後、移民たちは暮らしぶりが戻るにつれ、故郷へ送金を再開したり、戻って捕鯨漁師になる人も出てきた。明治の遭難 の後、細々と続けてきた沿岸捕鯨の漁師たちは、移民からの資金と人材を得て、南極海での大規模な母船式捕鯨の担い手と なった。太地は捕鯨の町として復活した。
こうした現象は太地にとどまらない。焼け野原から復興を成し遂げたのは、戦前に海を渡った移民の苦労なしでは語れな い。
太地の捕鯨について、理解し合うことをテーマにドキュメンタリー作品を制作した米ニューヨーク在住の映画監督、佐々木 芽生(めぐみ)さんは「太地の人々が外国人をむやみに批判したりしないのは、海外の親類らが差別や迫害を受けた過去を 知っているからだ」と語る。
太地町は現在、移民たちの暮らしぶりを後世に伝える事業を進めている。中心を担う同町歴史資料室の学芸員、桜井敬人 (はやと)さんは日本でアジア各地からの労働者が増え、地方の漁業や農業を支えている現状に着目し、こう述べた。
「(移民をした)自分たちの先祖が迫害され、強制収容所にまで入れられた歴史を知っていたら、日本で今の漁業を支えて いる海外の方々を差別の目で見ることができるだろうか。寛容になれるのではないか」
説明には、明治から育まれた太地のグローバルな視点がにじんでいた。
11月初旬、米西海岸に住む太地からの移民の末裔(まつえい)が太地町を訪れ、伝統の「くじら祭り」を楽しんだ。日本 語を話せない人も多いが、太平洋を隔てた親類は握手を交わした。IWC脱退で新局面を迎えようが、捕鯨文化を守り抜いた 地方の誇りだった。
やはり、先人は凄いですね。どうあっても、日本人は戦後に植え付けられた自虐史観から脱却して先人が築き上げてくれた素晴らしい日本精神を取り戻さなくてはならないです。
それこそが、日本を取り戻す近道です。その道は遠いでしょうが、それを取り戻した時こそ、日本が世界を感化する時代が来るのじゃないでしょうか。それを、世界は待っている。これぞ、日本人に課せられた役目のような気がします。










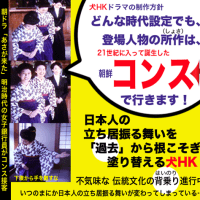
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます