2019.1.14(月) 天気:晴れ
メンバー:szt(CL),fuk(SL),yuka
装備:冬装備一式,わかん
1/13 22:00石下出発→1:30道の駅裏磐梯(泊)
1/14 7:44裏磐梯スキー場P→8:33銅沼→8:54イエローフォール→10:11稜線分岐付近→10:51弘法清水小屋→11:40山頂着→12:00下山開始→13:17火口原付近→15:00頃 基点P
「磐梯山」.この名前を聞くと,はるか昔小さいころのテレビCMに流れていた民謡を思い出す.甲高い声とともに宝の山と謡われていたあの山だ.会津盆地に赴いて晴天に恵まれれば,その姿が眺められる磐梯山.会津地方に住む人にとっては,さしずめわたしの住む街から眺められる筑波山のような存在か?であれば,きっと会津に暮らす方々に愛されているのだろう.会津地方の歴史を考えれば,百名山に数えられるのも至極当然だ.
そんな磐梯山,夏には観光がてら登ったことはあるのだが,登頂時はあいにくガスに包まれてしまった.おかげで麓に広がる猪苗代湖を眺めることは叶わなかった.今回は,体力維持と雪歩きの練習と猪苗代湖の眺めを堪能することを目的に,冬の磐梯山に向かった.
前夜に石下を出発し,道の駅で前夜泊.標高が低いためか,年末年始の八ヶ岳に比べれば寒さはそれほど感じない.6:00に起床し朝食をのんびりすませ裏磐梯スキー場へ移動.スキー場のオープン前に駐車場に到着するが,山に向かうと思われる車はすでに2台停まっている.駐車場整理のおじさんの指示に従って車を駐車し,磐梯山を目指していざ出発.開場前の点検で動くリフトを横目にスキー場脇をスポスポと歩いていく.予報通り雲はなくいい天気.あ~,気持ちイイ.

ゲレンデ脇を登り,振り返れば裏磐梯のいい眺め.
ゲレンデトップに立ったところでハッと思い出す.そういえば朝テントで準備したお湯の入ったテルモスを車に忘れた~!!
ほかのメンバーに確認すると,yukaおねーたまのザックの中からテルモス2つ,500mlのペットボトルの水,500mlのプラスチックボトルのスポーツドリンクが出現.はっ!?ここでも歩荷訓練??どこまで自分に厳しいんだ!?いやいやただただ自分を痛めつけるのが大好きなドM体質orド変態???なんてことを心の中で囁きながら,ありがたく余分な水分を半分こ.これではもうこの山行でyukaおねーたまには頭が上がらない.
ゲレンデトップからイエローフォールまでは予想通りトレースはバッチリついている.まずは凍った銅沼の上を歩きイエローフォール目指してゴー.
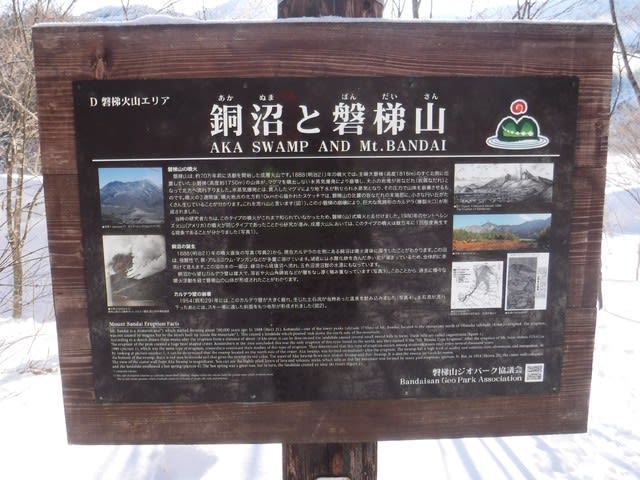
銅沼(あかぬま)の看板.ここからトレースを辿って銅沼の上を行く.

銅沼の上より.朝日がまぶしいです.

銅沼の上より磐梯山方面.う~ん,素晴らしい景色!

あれが噂のイエローフォール.
基点となった駐車場から1時間ほどでイエローフォールに到着.同行したfukさんは何回か冬の磐梯山へ来たことがあるそうで,イエローフォールの発達はまだまだとのこと.確かに滝の氷の規模としては迫力はない.暖冬の影響か?ここまでトレースのおかげで持ってきたわかんなど出す必要は全くなし.天気のいいうちに頂上まで行きたいからありがたいことこの上ない.
イエローフォールからやや左に回り込むように進んでゆくとピンクリボンとトレースがあり,磐梯山へ向かう尾根はわかりやすく進路は明瞭.ここもわかんを出す必要性もなし,ということでツボ足で高度を上げてゆく.

ご覧の通りピンクリボンがなびいている.その後も適度な間隔で目印アリ.

急な尾根を登ってゆき振り返ると桧原湖がよく見える.いい眺めだねぇ..

慣れない雪山歩きで奮闘するyukaおねーたま.ガンバレ~!
傾斜がきつくなった登りを進むこと1時間ほどで稜線へ.そこからは樹木は減ってそれまでとは別の景色が拡がる.風が強いとここら辺からつらくなるだろうが,この日はほぼ無風状態.磐梯山に雲がかかることはあるものの,目標である山頂を捉えることができ気持ちは高ぶってくる.あ~,気持ちいい~~!

標識についたエビの尻尾.見事だねぇ.

これぞ雪山の景色?しかし磐梯山は拝めない.

画になるところで,はいポーズ!

こちらの壁いかかでしょう?のポーズ!登れるところはあるかしら?

うっすらと見える磐梯山.近づいて来ましたよぉ~~!

右手のピークは櫛ヶ峰.あとちょっと~(1回目)!
気持ちの良い晴天の中,11時前に弘法清水小屋に到着.ただ,それまでと比べると段々ガスが多くなってきている印象.なるべくなら晴れ間のあるうちに山頂に行きたいが,初めての本格的な雪山歩きとなったyukaおねーたまは,雪に足を取られて苦戦気味.確かに年末の赤岳は条件良すぎたからね~.それでも弱音は吐かずにここまでやってきた,ご立派です.
ここから先は念のためピッケルを出す.でもアイゼンを履く必要もなさそうなのでツボ足のまま.トレースもそのまま明瞭についているので,ストックとわかんをデポして少しでも軽量化を図る.

10:51,弘法清水小屋.ここで小休止.
弘法清水小屋からピッケルに持ち替えたものの危険を感じる場面は全くと言っていいほどなく,ストックの方が歩きやすかったかなと苦戦しているyukaさんを見て少し反省.
山頂に到達するまでに先行していた単独の2人とすれ違う.振り返るとリフトに乗って登り始めたと思われる人々が視界に入り始める.さすが百名山,祝日ともなれば登山者は多いですなぁ..

山頂まであとちょっと(2回目).
弘法清水小屋から1時間足らずで無事山頂に到着.到達したものの山頂はガスに包まれ念願だった山頂からの景色はいまひとつ.それでも雪に包まれている磐梯山の山頂は別格です.

余裕綽々のfukさん.疲労困憊?のyukaおねーたま.

雪に包まれる山頂の祠.これはこの時期でないとみられないからねぇ.
山頂は風があるものの烈風というほどでもなく,場所を代えれば休めそうなのでせっかくだから頂上で小休止.yukaおねーたまから預かったテルモスを取り出し,さも自分の飲み物を持ってきたかのように,その中身でヌクヌクと温まる.それぞれ行動食も頬張って栄養補給をはかるが,yukaおねーたまがごそごそと取り出したのはコンビニおにぎりの3倍はあろうかという巨大おにぎり..食べられないからとザックに再度忍ばせようと試みている...へっ!?歩荷訓練の隠し玉??あくまでも自分の体をいじめるつもりっすか???何ならオレ食べますよ.ということで,飲料水だけでなく食料まで厚かましく他人のものでお世話になるという展開に...

伝わりづらいかもしれませんが,これコンビニおにぎりの3倍はありました.
小休止を挟んでいると少しだけガスが切れ,麓の景色を眼下におさめることができた.猪苗代湖のすべてが見えたわけではなかったけれど,思いのほか大きなその湖面にチョット感激.思いっきり晴れた日に登って景色を眺めてみたいな~と,再登したい気持ちがちょっぴり湧いてくる.まぁ,いずれ機会があれば参りますまい,と思いつつ12:00に下山開始.

雲の切れ間からの猪苗代湖.チョットだけよ~~.

下山の一コマ.わ~~~~~っ.

ドテッ...ってコテコテの鉄板です..あんたも好きねぇ~.
下山の途中で弘法清水小屋でデポしたストック&わかんを回収.樹林帯をサクサク下り火口原付近へ.ここで今回の目的の1つであるわかん歩行を体験してもらうべく,各人持ってきたわかんを装着する.yukaおねーたまはわかん初体験.買って間もないこともあり履くことすら初めての様子でしたが,慌てず騒がず靴に括り付けていざ歩かん.トレースを外し歩いても,あ~ら不思議歩きやすいじゃありませんか.
トレースを外しても雪の深さは脛程度.ここにこの時期来るのは初めてだからよくわからないけど,きっと雪の量は少ないのかな?それでも初めての練習にはちょうどいいくらいの深さかな??わかんを履いても太刀打ちできない雪ってのもあるからねぇ.

fuk先輩による紳士なわかん指導.戦前の流れを組むスパルタ指導!では決してありません!!

わかんデビューのyukaおねーたま.そのあるき心地はいかに??
スキー場までの帰路は,往路と違いトレースのない雪原や樹林帯を歩く.たまにはわかんを履いてスノーウォーキングってのも良いですな~.

ズンズン進むfukさん.膝,全然問題ないっすよ~!!

時間が経つにつれ磐梯山は隠れてゆく.早く片付けて良かった好かった.

14:36,ゲレンデトップに到着.駐車場まであとちょっと(3回目).
往路で通った銅沼の看板でわかんを外し,ゲレンデトップまで朝歩いたトレースを進む.リフト場のおじさんに下山路を確認しゲレンデ脇をてくてくと歩いて下山.リフトに乗るスキーヤー&ボーダーの視線を浴びつつ駐車場に到着してこの日も無事終了した.
下山後,民謡”会津磐梯山”をネットで聞いてみる.何か違うな~とさらにネットで検索を進めて,昔TVで流れていたCMの動画を発見し視聴する.あぁ,これだ~と思って納得.その画面に現れたのは,雪に囲まれたお屋敷の景色.このCMを観て”磐梯山”=”雪”が刷り込まれ,冬の雪の磐梯山に登りたいと思っていたのだねと,疑問が氷解したのだった.
雪の百名山,今年はもう少し別の所も狙ってみよう.あとどのくらい行けるかな?
szt










































































































































































