昼のNHKローカルニュースでは「すくなかぼちゃ順調に育つ」というリード。「少ない」かぼちゃとは何のことかと注目してみると、飛騨の伝統野菜「宿儺かぼちゃ」の成長の様子をレポートしたものだった。
黄色い花が咲いて、蔓には30センチほどのかぼちゃの実が垂れ下がっている。へちまのような細長い形が特徴というとおり、高山・丹生川の農家で撮影されたTV画面からみるかぎりは、ヘチマとしか見えない。
春先の天候不順で播種が遅れたが生育状態は例年並だという。かぼちゃは、50~80cmの長さ、2kg~5kgの重さにまで成長。緑のまだら模様入って表面は滑らか。果肉は鮮黄色、糖度が高いため、スープやデザート、煮物に使用されることが多いとWIKIにある。7月中旬には収穫が始まり10月頃まで続き、年間100トンほどが名古屋や大阪に出荷されるという。
このかぼちゃは、元来が高山辺りの自家用の野菜として栽培されていたものを、2001年に「宿儺かぼちゃ」と名づけて地元特産としたもの。現在、飛騨地方のおよそ200軒の農家が栽培しているという。
おかしな名前だと思ってWIKIを探ると、飛騨地方に伝わる「両面宿儺」という鬼神伝説に因るとあった。野見宿禰や武内宿禰のように、宿禰(すくね)という呼称が大和朝廷期に現れるが宿儺(すくな)もこれと同じだろうか。
宿儺については、旧飛騨街道沿いに様々な伝承があって、高山地方では、「仁徳帝のころ、飛騨国に現れた宿儺は、身長十八丈、一頭両面、四肘両脚を有する《救世観音》の化身である」というのだ。
世の人々を苦しみの中から救う観音様の化身だというのだからまことに有難いのである。そんな由緒ある宿儺の名前をつけられたかぼちゃ。夏ばての予防には霊験あらたかなのかもしれない。特徴あるひょうたん型が野菜売り場に出現するのを早くみたいものである。
黄色い花が咲いて、蔓には30センチほどのかぼちゃの実が垂れ下がっている。へちまのような細長い形が特徴というとおり、高山・丹生川の農家で撮影されたTV画面からみるかぎりは、ヘチマとしか見えない。
春先の天候不順で播種が遅れたが生育状態は例年並だという。かぼちゃは、50~80cmの長さ、2kg~5kgの重さにまで成長。緑のまだら模様入って表面は滑らか。果肉は鮮黄色、糖度が高いため、スープやデザート、煮物に使用されることが多いとWIKIにある。7月中旬には収穫が始まり10月頃まで続き、年間100トンほどが名古屋や大阪に出荷されるという。
このかぼちゃは、元来が高山辺りの自家用の野菜として栽培されていたものを、2001年に「宿儺かぼちゃ」と名づけて地元特産としたもの。現在、飛騨地方のおよそ200軒の農家が栽培しているという。
おかしな名前だと思ってWIKIを探ると、飛騨地方に伝わる「両面宿儺」という鬼神伝説に因るとあった。野見宿禰や武内宿禰のように、宿禰(すくね)という呼称が大和朝廷期に現れるが宿儺(すくな)もこれと同じだろうか。
宿儺については、旧飛騨街道沿いに様々な伝承があって、高山地方では、「仁徳帝のころ、飛騨国に現れた宿儺は、身長十八丈、一頭両面、四肘両脚を有する《救世観音》の化身である」というのだ。
世の人々を苦しみの中から救う観音様の化身だというのだからまことに有難いのである。そんな由緒ある宿儺の名前をつけられたかぼちゃ。夏ばての予防には霊験あらたかなのかもしれない。特徴あるひょうたん型が野菜売り場に出現するのを早くみたいものである。











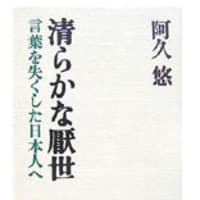






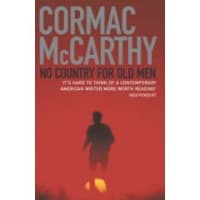
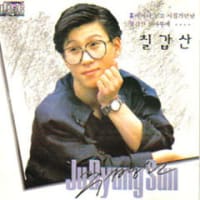
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます