「ユリイカ」という雑誌です。タイトルの横を見ると小さく「詩と批評」と書いてあります。そういう雑誌だったんですね。名前は聞いたことがあるけれど、内容は全く存じ上げませんでした。
その「詩と批評」の雑誌の今月号がなぜか桂米朝師匠の特集号でした。最近、本はもっぱらネットで買ってたんですが、先週久しぶりに天満橋のジュンク堂に行き、演劇・歌舞伎・文楽・落語の棚を見たら、この雑誌が置いてありました。おそらく、もともとの定位置(文芸?の棚)に置いてあったら手に取ることもなかったと思いますが、米朝師匠の特集と言うことで落語の棚にも置いてくださっていたようです。おかげで見逃すことなくgetできました。
私もまだ全て読めていないんですが、なかなか充実しています。
ざこばさん、米團治さんのインタビューあたりは、あちこちで聞いたり読んだりしていますが、月亭可朝さんとか上岡龍太郎さんまで引っ張り出してきて、米朝師匠を語るっていうのはずいぶんと珍しいような気がします。結構読み応えがありました。
「米朝一門の師弟愛/中川周」っていうのは米朝師匠のお孫さん(三男さんのお嬢さん)で、大学の卒業論文として教育者としての米朝師匠を取り上げられたそうで、その卒論が掲載されています。かなりレアですね。吉坊さんは吉朝さんのお弟子さんですが、米朝師匠のところで内弟子修業をされています。文章、お上手です。最後はほろりとさせられました。
高座で演じる落語家という面だけでなく、いろいろな切り口で米朝師匠を偲んでいらっしゃいます。編集者に米朝師匠の大ファンって方がいらっしゃったんでしょうか。「愛」が感じられる特集でした。面白い雑誌だと思います。ぜひ! です。
です。
大阪の雑誌「上方芸能」の次号が米朝師匠の追悼号になるそうなんですが、東京の雑誌に負けてはいけません。ガンバレ!
その「詩と批評」の雑誌の今月号がなぜか桂米朝師匠の特集号でした。最近、本はもっぱらネットで買ってたんですが、先週久しぶりに天満橋のジュンク堂に行き、演劇・歌舞伎・文楽・落語の棚を見たら、この雑誌が置いてありました。おそらく、もともとの定位置(文芸?の棚)に置いてあったら手に取ることもなかったと思いますが、米朝師匠の特集と言うことで落語の棚にも置いてくださっていたようです。おかげで見逃すことなくgetできました。
私もまだ全て読めていないんですが、なかなか充実しています。
米朝師匠の特集ページの内容です。
【“桂米朝”という時代】
師匠と勉強 / 桂ざこば 聞き手=編集部
落語家の名前 桂米朝の家に生まれて / 桂米團治 聞き手=編集部
米朝さんと正岡容と私たち / 大西信行
聞き納め桂米朝噺 / 加藤武
『上方風流』のこと / 山田庄一
桂米朝さんの想い出 やるべき事は総てやりつくした人 / 権藤芳一
米朝山脈 / 織田正吉
【噺家とひとびと】
上方落語の吹き返し / 月亭可朝 聞き手=編集部
眠らないママ / 廓正子
二人の盟友 桂米朝と吉鹿之司 / 金森三夫
「口碑文芸」を愛した「文化遺族」 / 乙部順子
八十八翁の笑み / 桂吉坊
米朝一門の師弟愛 / 中川周
米朝アンドロイド / 石黒浩
米朝師匠追悼 / 雲田はるこ
【落語の学究】
上岡龍太郎、桂米朝を語る / 上岡龍太郎 聞き手・構成=戸田学
四代目桂米団治と桂米朝 / 豊田善敬
笑福亭松鶴と桂米朝 / 戸田学
稀有の人・桂米朝師の学問 / 延広真治
桂米朝の構図 / 和田尚久
桂米朝師を考える一視点 浄瑠璃本研究の立場から / 神津武男
形而上学的桂米朝論 桂米朝と井筒俊彦 / 山内志朗
「精妙なうそ」の人 桂米朝へのオマージュ / 森本淳生
眠れる落語、眠れない落語 「土橋万歳」雑感 / 中田健太郎
【現世の行きかた】
■現世の行きかた 桂米朝略年譜 / 編=豊田善敬・戸田学
【“桂米朝”という時代】
師匠と勉強 / 桂ざこば 聞き手=編集部
落語家の名前 桂米朝の家に生まれて / 桂米團治 聞き手=編集部
米朝さんと正岡容と私たち / 大西信行
聞き納め桂米朝噺 / 加藤武
『上方風流』のこと / 山田庄一
桂米朝さんの想い出 やるべき事は総てやりつくした人 / 権藤芳一
米朝山脈 / 織田正吉
【噺家とひとびと】
上方落語の吹き返し / 月亭可朝 聞き手=編集部
眠らないママ / 廓正子
二人の盟友 桂米朝と吉鹿之司 / 金森三夫
「口碑文芸」を愛した「文化遺族」 / 乙部順子
八十八翁の笑み / 桂吉坊
米朝一門の師弟愛 / 中川周
米朝アンドロイド / 石黒浩
米朝師匠追悼 / 雲田はるこ
【落語の学究】
上岡龍太郎、桂米朝を語る / 上岡龍太郎 聞き手・構成=戸田学
四代目桂米団治と桂米朝 / 豊田善敬
笑福亭松鶴と桂米朝 / 戸田学
稀有の人・桂米朝師の学問 / 延広真治
桂米朝の構図 / 和田尚久
桂米朝師を考える一視点 浄瑠璃本研究の立場から / 神津武男
形而上学的桂米朝論 桂米朝と井筒俊彦 / 山内志朗
「精妙なうそ」の人 桂米朝へのオマージュ / 森本淳生
眠れる落語、眠れない落語 「土橋万歳」雑感 / 中田健太郎
【現世の行きかた】
■現世の行きかた 桂米朝略年譜 / 編=豊田善敬・戸田学
ざこばさん、米團治さんのインタビューあたりは、あちこちで聞いたり読んだりしていますが、月亭可朝さんとか上岡龍太郎さんまで引っ張り出してきて、米朝師匠を語るっていうのはずいぶんと珍しいような気がします。結構読み応えがありました。
「米朝一門の師弟愛/中川周」っていうのは米朝師匠のお孫さん(三男さんのお嬢さん)で、大学の卒業論文として教育者としての米朝師匠を取り上げられたそうで、その卒論が掲載されています。かなりレアですね。吉坊さんは吉朝さんのお弟子さんですが、米朝師匠のところで内弟子修業をされています。文章、お上手です。最後はほろりとさせられました。
高座で演じる落語家という面だけでなく、いろいろな切り口で米朝師匠を偲んでいらっしゃいます。編集者に米朝師匠の大ファンって方がいらっしゃったんでしょうか。「愛」が感じられる特集でした。面白い雑誌だと思います。ぜひ!
 です。
です。大阪の雑誌「上方芸能」の次号が米朝師匠の追悼号になるそうなんですが、東京の雑誌に負けてはいけません。ガンバレ!












 の襲名披露のことをふれた段もありました。楽しみに読ませていただきます。
の襲名披露のことをふれた段もありました。楽しみに読ませていただきます。





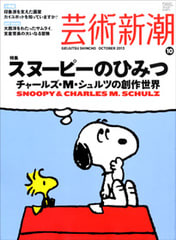

 。
。





