濵田研吾さんの「脇役本」を読みました。
内容紹介です。
最初、このタイトルを見たとき、脇役の役者さんたちを紹介した本だろうと思い、ネットで注文、届いたのを見ると「脇役の役者さんたちが書いた本を紹介する本」でした。ちょっと想像していたのと違うなぁ、読めるかしらと一瞬不安に思いましたが、それは杞憂、さくさく楽しく読めました。本を紹介するってことは役者さんも紹介しているので、ま、そんなに外れてはいませんでした。
こちらの本、元々は平成17年に発刊されたそうで、それの増補文庫版として今年ちくま文庫から出ました。
著者の濵田研吾さん、1974年生まれ、私よりも10歳以上お若い方なんですが、チョイスしている役者さん、かなりシブイです。私でも見たことがない人が取り上げられていて(もちろん濵田さんもリアルタイムでご覧になっているわけではなくビデオとか本とかでお知りになったようです)、マニアック感ありました。でも、私はそういうマニアックなところ、好きです。
この本の「脇役」の定義?が、濵田さんが「脇役のうまい役者」「気になるバイプレイーヤー」と思っていらっしゃる役者さんなので、滝沢修や三津田健、志村喬、芦田伸介なんかも入っています。テレビや映画の脇役って、新劇の劇団の人たちが資金稼ぎに出てるってパターンが多いので、この本でも文学座、俳優座、劇団民藝の役者さんが結構取り上げられていて、元・演劇女子高生だったワタクシはちょっと“遠い目”になってしまいました。
で、急に文学座が見たくなって、来月見に行こうかと、文学座大阪支持会にお願いしました。支持会って劇団の後援会みたいな組織で、花の女子高生時代、杉村春子先生に会いたくて、入ってたことがあります。その時ちょうど文学座創立四十周年で、その記念誌がどうしても欲しくて、父にねだって買ってもらいました。その本、まだ持ってます。文学座はもう創立八十周年を迎えているそうで、私が入っていたのは40年も前ってことになります。“40”っていう数字に我ながらビックリしました。自分がすっごい年寄りのような気がしてきました。
話が逸れました。役者さんたちですが、自叙伝や芸談、軽いエッセイみたいなのが多いのですが、たまに役者とは全然関係のない「こけし」や「盆栽」、「寿司」の専門書みたいなのもあります。その道のプロフェッショナルっていう役者さんもいらっしゃったようです。あとは「まんじゅう本」と呼ばれるジャンルの本、ご本人がお亡くなりになった後に、遺族や関係者がその人のことを書いた本を制作、それを一周忌とか三回忌とかに配られた本のことをさすそうです。もちろん、私家版、自費出版なので一般に出回ることはなく、古本屋さんで出てくるそうです。私家版と言っても、文集のようなちゃっちいモノではなく、きちんと装丁してあり、題字とか素材とか凝ってるモノも多いみたいです。この本では白黒なので、もひとつその良さがわからないのが残念でした。
この本に紹介されている本って、基本、古本です。読みたいのがあれば、古本屋さんで探さないといけません。それがチト面倒です。そんなにマメなほうではないもので…。まだまだ取り上げられていない役者さんがたくさんいらっしゃるので、ぜひ、第二弾、第三弾をお願いしたいものです。
濵田さんのそれぞれの役者さんたちに対する“愛”が感じられ、いろいろな発見もあり、楽しい本でした。 です。
です。
内容紹介です。
旧作映画や往年の舞台で活躍した名脇役たち。かれらに関するたくさんの著書を古本の山から見つけ出す。知られざる素顔や、専門家顔負けの意外な分野での研究、波乱にとんだ生涯などを紹介する。加東大介、志村喬、古川緑波、芦田伸介、徳川夢声、浪花千栄子、伊藤雄之助、岸田森、若水ヤヱ子など七十数人のバイプレーヤー、二百数十冊の本が大集合。単行本を大幅増補。
最初、このタイトルを見たとき、脇役の役者さんたちを紹介した本だろうと思い、ネットで注文、届いたのを見ると「脇役の役者さんたちが書いた本を紹介する本」でした。ちょっと想像していたのと違うなぁ、読めるかしらと一瞬不安に思いましたが、それは杞憂、さくさく楽しく読めました。本を紹介するってことは役者さんも紹介しているので、ま、そんなに外れてはいませんでした。
こちらの本、元々は平成17年に発刊されたそうで、それの増補文庫版として今年ちくま文庫から出ました。
著者の濵田研吾さん、1974年生まれ、私よりも10歳以上お若い方なんですが、チョイスしている役者さん、かなりシブイです。私でも見たことがない人が取り上げられていて(もちろん濵田さんもリアルタイムでご覧になっているわけではなくビデオとか本とかでお知りになったようです)、マニアック感ありました。でも、私はそういうマニアックなところ、好きです。
この本の「脇役」の定義?が、濵田さんが「脇役のうまい役者」「気になるバイプレイーヤー」と思っていらっしゃる役者さんなので、滝沢修や三津田健、志村喬、芦田伸介なんかも入っています。テレビや映画の脇役って、新劇の劇団の人たちが資金稼ぎに出てるってパターンが多いので、この本でも文学座、俳優座、劇団民藝の役者さんが結構取り上げられていて、元・演劇女子高生だったワタクシはちょっと“遠い目”になってしまいました。
で、急に文学座が見たくなって、来月見に行こうかと、文学座大阪支持会にお願いしました。支持会って劇団の後援会みたいな組織で、花の女子高生時代、杉村春子先生に会いたくて、入ってたことがあります。その時ちょうど文学座創立四十周年で、その記念誌がどうしても欲しくて、父にねだって買ってもらいました。その本、まだ持ってます。文学座はもう創立八十周年を迎えているそうで、私が入っていたのは40年も前ってことになります。“40”っていう数字に我ながらビックリしました。自分がすっごい年寄りのような気がしてきました。
話が逸れました。役者さんたちですが、自叙伝や芸談、軽いエッセイみたいなのが多いのですが、たまに役者とは全然関係のない「こけし」や「盆栽」、「寿司」の専門書みたいなのもあります。その道のプロフェッショナルっていう役者さんもいらっしゃったようです。あとは「まんじゅう本」と呼ばれるジャンルの本、ご本人がお亡くなりになった後に、遺族や関係者がその人のことを書いた本を制作、それを一周忌とか三回忌とかに配られた本のことをさすそうです。もちろん、私家版、自費出版なので一般に出回ることはなく、古本屋さんで出てくるそうです。私家版と言っても、文集のようなちゃっちいモノではなく、きちんと装丁してあり、題字とか素材とか凝ってるモノも多いみたいです。この本では白黒なので、もひとつその良さがわからないのが残念でした。
この本に紹介されている本って、基本、古本です。読みたいのがあれば、古本屋さんで探さないといけません。それがチト面倒です。そんなにマメなほうではないもので…。まだまだ取り上げられていない役者さんがたくさんいらっしゃるので、ぜひ、第二弾、第三弾をお願いしたいものです。
濵田さんのそれぞれの役者さんたちに対する“愛”が感じられ、いろいろな発見もあり、楽しい本でした。
 です。
です。














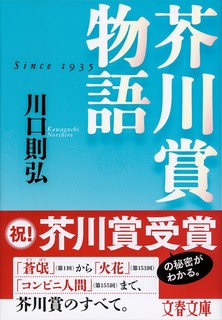





 銀座
銀座
 の対談が掲載されているということで急遽取り寄せました。定価が税込み100円で、本屋さんで買ってもよかったのですが、岩波書店のWebsiteに行くと「見本誌進呈」というボタンがあったので、思わずポチッとしてしまいました。
の対談が掲載されているということで急遽取り寄せました。定価が税込み100円で、本屋さんで買ってもよかったのですが、岩波書店のWebsiteに行くと「見本誌進呈」というボタンがあったので、思わずポチッとしてしまいました。



 、当然っちゃ当然のことなんですけど。孝夫さん
、当然っちゃ当然のことなんですけど。孝夫さん

 です。
です。







