目次と連絡先 私のfacebook 動画集 動画集2 大西つねき れいわ ② 山本太郎 兵頭
ニュースドットコム 物語1 物語2 恐怖!安倍内閣 小畑(幸) 「日本の風景」 前月
リテラ デモクラシータイムス 田中宇 海外記事 杉並から情報発信 動画 根っこ勉強会
政治も経済も情報である①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪
「世界史年表」 世界史A 世界史B 宇宙 宗教 地球 日本人
ニュースドットコム 物語1 物語2 恐怖!安倍内閣 小畑(幸) 「日本の風景」 前月
リテラ デモクラシータイムス 田中宇 海外記事 杉並から情報発信 動画 根っこ勉強会
政治も経済も情報である①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪
「世界史年表」 世界史A 世界史B 宇宙 宗教 地球 日本人

塩田と下駄の町、松永町(動画1分)
昭和37年まで広島県立松永高校は、現在の松永駅の南の線路沿いにあった。学校の南側はグランドがあり、その南側には塩田が続いていた。私は中学校(大成館)では野球部に所属していたし、当時は松永市であり、地域の松永中学校や精華中学校にも多くの仲間がいた。高校では仲間と一緒に野球ができると楽しみにして、高校入学式の前から野球部に所属して春季練習に参加した。しかし、入部者は同じ中学の仲間一人しかいなく、楽しみがなくなったので、入学後には退部してしまった。高校の部活動で青春を謳歌した経験がないのが残念だが、今でも野球部に在籍していたら、どんな高校時代が送れただろうと、ちょぴり青春を懐かしむこともある。
高校は卒業後、現在地に移転し、当時グランドの南側にあった塩田は廃止され、高校と塩田の跡地は今では新しい松永の市街地として賑わっている。なお、1966年(昭和41年)5月1日に松永市は福山市と合併し、私は大学、就職と故郷を離れていたので、青春時代と言えば、松永市と塩田に隣接していた松永高校が強く印象に残っている。
福山市となり、現在は通学範囲も拡大した。私の時代は自転車通学はあったが、松永駅に隣接しながら、通学に松永駅を利用する高校生のことは考えられなかった。最近では選挙の投票場所を駅構内に設置することを考えているところもあるようだが、駅から徒歩20分、乗車駅までと乗車時間を含めて、毎日、通学する高校生に、高校の立地条件の自然環境を活用したカリキュラムは用意されているのだろうか?遠方に通学するに必要な学習環境や宿泊施設等への配慮はなされているのだろうか?時代が変わるということは、あらゆる生活環境も変わることであり、私たちは時代とともに充実した生活を送れているだろうか?
どこもそうであろうが町が大きくなると、地域の仲間意識は希薄になる。地域の溝掃除や草刈りを含めて、共同作業に協力する住民が減少した。下水道の完備等、公共施設の改善の必要があるにしても、地域住民の繋がりが希薄になっていくような気がする。私は歩行困難で一人で外出できなくなり、私自身が地域に貢献できなくなって申し訳ないと思っている。しかし、聞くところによると、子供会まで希望者のみで運営されているそうだ。何を配慮されているのか知らないが、自主参加は大人の意識であり、地域に馴染んだ子供と地域から疎外された意識を持つ子供が育つのではないかと心配だ。地域の問題として、便利な社会になっていくにつれ、個人の確立と共同作業の尊重の問題は、これからの重要課題になると思う。

市街地化した松永駅南側から用水路(羽原川)と北側(丘の上の大成館中学校)を見る

ここで江戸時代からの松永の塩田と下駄の町の歴史を簡単にまとめておきたい。関ヶ原の戦い以降、安芸ほか山陽・山陰8か国(112万石)を領有していた毛利家は防長2か国(29万8千石)に減領され、安芸・備後50万石が福島正則によって領有されたが、そのうち安芸および備後北部・西部は浅野長晟(42万石)に、備後南部と備中国西南部(現在の笠岡市や井原市の大半)は徳川家康の従兄弟の水野勝成(10万石),①,②に分割(1619年)された。
松永湾の干拓は福山藩士本庄重政,②,③により1660年から着手され、1667年に塩浜とし塩田の基礎がつくられた。そして、明治に入ると塩水を煮詰めるための燃料となる木材の輸送用水路のそばで、下駄屋の主人丸山茂助,②が塩を運ぶ船の帰路の空荷に着目して、「塩が下駄を生む」ことになる。
参考:塩田として誕生した、福山市松永町
承天寺の周辺地図

住民たちに守られているお地蔵様(動画1分)
四国巡礼八十八カ所は有名だが、江戸時代を境に起きるお遍路の庶民への広がりは四国に限ったことではなく、伊勢・西国・坂東・東北など、全国各地の霊場へ巡礼する様になる。また、「お地蔵さんのお遍路」もある。松永にも住民たちに守られているお地蔵様,(地蔵さん巡り)があるが、その由来については江戸時代に開発された塩田と関係があるようだ。福山藩士である本荘重政が松永塩田築造の際、潮崎神社を現在地に遷座し、塩浜の鎮守とし、「それまで松永の産土神は隣村の神村(現 神村町)の八幡宮だったが、当社遷座後は、塩浜で塩業に携わる人の産土神となった」と言うから「お地蔵さん巡り」も本荘重政氏の影響が大きかったのではないかと思う。
初稿 2019.10.9










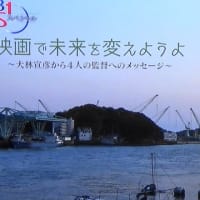



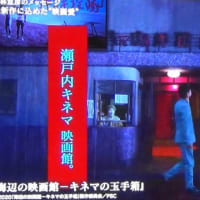
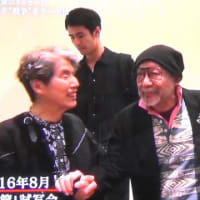

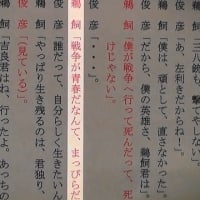



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます