経済はお金が循環することにより繁栄する。だから消費税により、民間のお金の循環の一部を政府が吸い上げるのはおかしい、そう素朴に思っていたら、「大西つねき」先生が、「消費税(動画)」や「お金の発行のしくみ(動画)」を、きちっと説明していただいた。
1.金本位性の廃止
お金は金や銀と交換可能な貨幣と考えてきたが、1971年8月15日にニクソンが発表した金互換性の廃止宣言みよるドル・ショック(ニクソン・ショック)によって、金本位性は崩壊し、同年末のスミソニアン協定では固定相場制の維持を図ったが、世界経済の変動を押しとどめることはできず、1973年から変動相場制に移行し、ブレトン=ウッズ体制は終わりを告げた。なお、この日が8月15日であったことから、第2の敗戦(日本の敗戦:1945年8月15日)と言われているそうだ。第2の敗戦は、日本や欧州の戦後復興に伴う、アメリカ経済の相対的弱体化を示すもので、金互換性の廃止はある意味では、アメリカの敗戦とも言えよう。
参考:ドル・ショック(ニクソン・ショック)
スミソニアン協定
ブレトン=ウッズ体制
大西つねき「日本から世界を変える動画/お金のあるべき姿」
変動相場制 ①歴史的背景 ②経済制度はどう変わったか 変動相場制の帰結
食糧価格とマネー資本主義 (2)金融の役割 (3)金融工学の発展
マイナス金利に驚くよりも日銀当座預金に未だに0.1%の金利を付けていることに驚く
日本銀行時系列統計データ検索サイト
アメリカ連銀と日銀の不換紙幣への捉え方の違い
2.お金の原点
その後、変動相場制によりマネー資本の暴走が始まり、「お金が全て」と考えている経済関係者の見ていた(見ている)世界は破綻し、お金よりも「自然と人間」を大切にする里山資本主義,(2)が見直される時代が来ている。お金については、NHK番組「ヒューマン~なぜ人間になれたのか」は、人間が生まれた歴史を興味深く教えてくれる。その中で第4集 そしてお金が生まれたから、お金のことを考えると面白い。
参考: NHK フェイス「里山資本主義~革命はここ」 (動画)
里山資本主義とローカルアベノミクスとは (動画)
参考:藻谷浩介+NHK広島取材班『里山資本主義』を読む
アベノミクス1年 お金第一主義(浜田氏)と里山資本主義(藻谷氏)の論争(動画)
日本経済"未来型モデル”を求めて 里山資本主義の世界の動き(動画)
NHKスペシャル:ヒューマンなぜ人間になれたのか
第1集 旅はアフリカから始まった(動画)
第2集 グレートジャニーの果てに(動画)
第3集 大地に種をまいたとき(動画)
第4集 そしてお金が生まれた(動画)
人類誕生・未来編
第1集「こうしてヒトが生まれた」(動画)
第2集「最強ライバルとの出会い そして別れ」(動画)
第3集「ホモ・サピエンス ついに日本へ!」(動画)
3.消費税
それでは大西先生の消費税から勉強しよう。どこまで理解できているか自信はないが、私の常識を疑うことには意義があろう。そして、それがあなたの常識を疑うことにも参考になれば嬉しい。しかし、ここに私なりに理解したことを公表することは責任を伴うので、公表後、大西先生に誤りはチェックしていただき、このブログで報告したい。
まず、消費税は消費者が支払う税金だと思っていたが、売る側に掛けられる税金だと教えられた。販売することで生じる利益、人件費、仕入れ金額の合計の販売金額から、仕入れ金額を差し引いた部分を付加価値という。経済とはモノに価値を付けて流通させることであり、この付加価値に対して消費税を払う。消費税は取引により発生する仕組みであり、消費者が納める税金ではない。
そうすると、消費者と事業者の間だけでなく、事業者と事業者の間の取引にも消費税は発生する。デフレのように消費者の購買意欲が低下すると、売り手側も販売価格を低下させて売ろうとする。業者は利益を確保したいために、人件費を抑えるか削減する(雇用方法を変える)。ここに商品と人との間に悪循環が始まる。また業者間でも、売り手と買い手の力関係で強い方が取引価格を決める。大企業が強くて、下請けの中小企業に負担が押し付けられる。ここに消費税は人の購買力と給料を低下させ、経済の循環を阻害するだけでなく、人を不幸にする税金であることが理解できる。
4.お金の発行のしくみ
大西先生は消費税で国の借金は返済できないと言う。それは100%ウソだと言う。そこで「お金の発行のしくみ」について勉強してみよう。
「政府の借金は1100兆円、国民の全てのお金も1100兆円。借金が無くなると、国民のお金も無くなる」とは、どういうことだろう。
我々が使うお金(貨幣、紙幣)は日本銀行が発行しているのではなく、財務省から独立した独立行政法人「国立印刷局」が、コンピューターネットワーク上にある電子情報を貨幣として使えるようにするために製造している。日本銀行から市中に払い出された通貨の総量を通貨流通高というが、2017年の大晦日、一般家庭や企業、金融機関などで年越しした銀行券(お札)の残高は、合計で107兆円だった。2018年度予算は約100兆円だ。政府は民間企業の業務と同じで、予算額を貨幣で配分しているわけはない。我々は貨幣をお金だと信じているが、お金はコンピュータに情報としてあり、それが増え続けて、政府の借金を1100兆、国民の全てのお金も1100兆円と増やしている。
参考:「国内のお金の流通量は101兆、国の借金は1000兆円」
・・・日本の貿易黒字のことには触れられていないが、後で考えよう。
5.お金はどこで生まれる?
それでは何故、お金は増え続けているのか。お金を生むのは日銀ではなく民間銀行だそうだ。民間銀行は「受け入れている預金等の一定比率(法定準備率)以上の金額を日本銀行に預け入れること」を義務付ける準備預金制度の下に、自由にお金を融資することができる。この制度は、もともと金融緩和・引締めの手段として決められたものだが、その機能を失い、1991年10月を最後にこの制度の法定準備率(1991年10月以来一定(1.2%))は変更されていない。日銀はその理由を「日本銀行の潤沢な資金供給により、多くの金融機関が法定準備預金額を超える『超過準備』を有することが常態化」したためと説明しているが、大西先生は1991年10月以来一定(1.2%)の「法定準備率以上のお金を日銀に上納すれば、残りのお金を民間銀行は自由に融資できる」と説明している。日銀は「法定準備預金額」を維持することはできるが、それ以上のお金を生み出すことはできないはずだ。
6.お金は電子情報として生まれる
お金は大西先生が説明されるように、民間銀行でしか生まれない。しかも、そのお金はコンピュータの電子情報として生まれる。電子情報であっても民間の帳簿は貸方、借り方のプラスマイナスはゼロになる。しかし、政府の発行した電子情報は税金で回収する部分があっても、2018年であれば約100兆円の一部を回収しているだけだ。残りは電子情報に残り増え続ける。増え続けているのは、政府によって生まれたお金なのだ。政府の予算は電子情報での貸し借り。これを毎年、国民が返済するとプラスマイナスゼロでお金は増えない。しかし毎年の政府の予算は、税金によっては全額は回収されないので、残りの部分のお金は増加する。これに貿易黒字でドルで蓄積されている使えないお金も貯まっている。貿易黒字の問題は後に考えるとして、「政府の借金は1100兆円、国民の全てのお金も1100兆円。借金が無くなると、国民のお金も無くなる」とは、お金は電子情報として増加しているが、コンピュータの電子情報のお金はプラスマイナスゼロで相殺されて消える。しかし、貿易黒字のドルは円に交換できないので、電子情報としてのお金も増え続けているということだ。
ここに2018年10月5日に公表された「マネタリーベースと日本銀行の取引(2018年9月)」を紹介しておく。世の中に出回っているお金は、流通現金(「日本銀行券発行高(紙幣)」+「貨幣流通高(硬貨)」)である。また、日銀当座預金は法定準備金制度の準備金であり、、市中には出回らない。最近は約110兆円の現金が市中で流通している。
―――――――――――――――――――――――――――――――
18/7月 8月 9月
(月末残高・億円) 2018/Jul. Aug. Sep.
―――――――――――――――――――――――――――――――
日本銀行券発行高 1,046,013 1,047,502 1,047,162
貨幣流通高 47,760 47,862 47,920
日銀当座預金 3,936,015 3,924,273 3,954,799
―――――――――――――――――――――――――――――――
マネタリーベース 5,029,788 5,019,637 5,049,881
―――――――――――――――――――――――――――――――
参考:マネタリーベース統計とは何ですか。
マネタリーベース=「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」+「日銀当座預金」
7.貿易黒字の行く先
財務省貿易統計(図)によると、貿易額は1960年代後半から増加し、1981年から2010年までの約30年間は黒字を続けてきた。しかし、2008年、お金のことしか考えない実体のないマネー資本主義はリーマンショックで世界金融恐慌を引き起こし、それまで増加していた貿易額は減少し、2010年から2014年までは日本の貿易収支も赤字となった。しかし、2015年から再び黒字になっている。貿易はドルで決済されるので、30年間の輸出超過により、ドルは毎年約10兆円蓄積したことになる。このドルは円に変換できないので、ザックリ計算すれば300兆円が蓄積していることになる。日本は財政危機どころか世界一の使えないお金を持った金持ち大国なのである。心配すべきは赤字による財政崩壊ではなく、現在の持続不可能な金融システムの崩壊なのである。
大西先生が実践したいのは、地方通貨の様な持続可能な金融システムに現在のシステムを転換すること。それには世界の人の常識を変えねばならない。明治維新から150年、江戸末期の常識と今では大きく違っている。「歴史は勝者によりつくられる」というが、科学的根拠のある知見は別にして、政治・経済の常識も勝者によりつくられている。常識には誰にも否定できないような科学的知見もあるように、経済の常識は、誰も否定できない「お金の量=価値の量」とすべきである。
貿易黒字も持続不可能な金融システムを動かしている勝者に使わせないで、国民の幸福のために使わねばならない。日本は地球から見れば一つの地方であり、「円」を地方通貨として使う方法を考えることが第一だが、毎年、使うことができない貿易黒字は100年~150年先を見通した事業に使う方法もあろう。
今の政治と経済のリ-ダーは、今の金融システムは持続不可能であることを理解していないばかりか、その崩壊を加速させている。規模拡大によるコストダウンが常識とされているが、これを目標にしている人たちは、金融崩壊の被害を一番大きく受け、自然の恵みに生き「里山資本主義」を実践している人達は生き残るであろう。
参考:大西つねき「日本から世界を変える動画/お金のあるべき姿」 「国家経営のあり方(現在の問題点)」 「国家経営のあり方(未来の国家)」 「集団的自衛権について
8.常識を疑うことが、未来を拓く
京都大学の本庄先生がノーベル賞を受賞された。その先生が常識を疑え、教科書にもウソがある、学術論文も疑って読めと強調されている。先生は学生の時、進路に弁護士よりも、より多くの人に貢献できる医学の分野を選ばれた。そして、手術とか人間を人工的に治療することが常識となり、人間が本来持っている免疫の力を使う免疫療法を古い、怪しいと否定されていた医療界に、ノーベル賞という権威で免疫療法を認知させ、常識を転換させた。大西先生も同じだと思う。今の金融システムは人間の生活を破壊している。そのことに人々が気付き「地域通貨」の考え方を「世界通貨」にする動きが出れば、ノーベル賞以上の仕事となる。ノーベル賞をここで取り上げるのは、ノーベル賞受賞はメディアが大きく取り上げ、大西先生の考え方を世界に認知されることを意味するから。世界の常識を変えることは、人類を一歩前進させる偉大な仕事なのだ。
明日は京都で、「大西つねき」さんの講演会があります。
10月7日(日)13:30〜16:30 場所:あわたまKYOTO
〒602-8373 京都市上京区下横町207-1 地図
参加費 1000円(横浜からの大西つねきさんの交通費になります。)
初稿 2018.10.6 更新 2019.3.11 更新(2020.2.23ブログ目次削除)
1.金本位性の廃止
お金は金や銀と交換可能な貨幣と考えてきたが、1971年8月15日にニクソンが発表した金互換性の廃止宣言みよるドル・ショック(ニクソン・ショック)によって、金本位性は崩壊し、同年末のスミソニアン協定では固定相場制の維持を図ったが、世界経済の変動を押しとどめることはできず、1973年から変動相場制に移行し、ブレトン=ウッズ体制は終わりを告げた。なお、この日が8月15日であったことから、第2の敗戦(日本の敗戦:1945年8月15日)と言われているそうだ。第2の敗戦は、日本や欧州の戦後復興に伴う、アメリカ経済の相対的弱体化を示すもので、金互換性の廃止はある意味では、アメリカの敗戦とも言えよう。
参考:ドル・ショック(ニクソン・ショック)
スミソニアン協定
ブレトン=ウッズ体制
大西つねき「日本から世界を変える動画/お金のあるべき姿」
変動相場制 ①歴史的背景 ②経済制度はどう変わったか 変動相場制の帰結
食糧価格とマネー資本主義 (2)金融の役割 (3)金融工学の発展
マイナス金利に驚くよりも日銀当座預金に未だに0.1%の金利を付けていることに驚く
日本銀行時系列統計データ検索サイト
アメリカ連銀と日銀の不換紙幣への捉え方の違い
2.お金の原点
その後、変動相場制によりマネー資本の暴走が始まり、「お金が全て」と考えている経済関係者の見ていた(見ている)世界は破綻し、お金よりも「自然と人間」を大切にする里山資本主義,(2)が見直される時代が来ている。お金については、NHK番組「ヒューマン~なぜ人間になれたのか」は、人間が生まれた歴史を興味深く教えてくれる。その中で第4集 そしてお金が生まれたから、お金のことを考えると面白い。
参考: NHK フェイス「里山資本主義~革命はここ」 (動画)
里山資本主義とローカルアベノミクスとは (動画)
参考:藻谷浩介+NHK広島取材班『里山資本主義』を読む
アベノミクス1年 お金第一主義(浜田氏)と里山資本主義(藻谷氏)の論争(動画)
日本経済"未来型モデル”を求めて 里山資本主義の世界の動き(動画)
NHKスペシャル:ヒューマンなぜ人間になれたのか
第1集 旅はアフリカから始まった(動画)
第2集 グレートジャニーの果てに(動画)
第3集 大地に種をまいたとき(動画)
第4集 そしてお金が生まれた(動画)
人類誕生・未来編
第1集「こうしてヒトが生まれた」(動画)
第2集「最強ライバルとの出会い そして別れ」(動画)
第3集「ホモ・サピエンス ついに日本へ!」(動画)
3.消費税
それでは大西先生の消費税から勉強しよう。どこまで理解できているか自信はないが、私の常識を疑うことには意義があろう。そして、それがあなたの常識を疑うことにも参考になれば嬉しい。しかし、ここに私なりに理解したことを公表することは責任を伴うので、公表後、大西先生に誤りはチェックしていただき、このブログで報告したい。
まず、消費税は消費者が支払う税金だと思っていたが、売る側に掛けられる税金だと教えられた。販売することで生じる利益、人件費、仕入れ金額の合計の販売金額から、仕入れ金額を差し引いた部分を付加価値という。経済とはモノに価値を付けて流通させることであり、この付加価値に対して消費税を払う。消費税は取引により発生する仕組みであり、消費者が納める税金ではない。
そうすると、消費者と事業者の間だけでなく、事業者と事業者の間の取引にも消費税は発生する。デフレのように消費者の購買意欲が低下すると、売り手側も販売価格を低下させて売ろうとする。業者は利益を確保したいために、人件費を抑えるか削減する(雇用方法を変える)。ここに商品と人との間に悪循環が始まる。また業者間でも、売り手と買い手の力関係で強い方が取引価格を決める。大企業が強くて、下請けの中小企業に負担が押し付けられる。ここに消費税は人の購買力と給料を低下させ、経済の循環を阻害するだけでなく、人を不幸にする税金であることが理解できる。
4.お金の発行のしくみ
大西先生は消費税で国の借金は返済できないと言う。それは100%ウソだと言う。そこで「お金の発行のしくみ」について勉強してみよう。
「政府の借金は1100兆円、国民の全てのお金も1100兆円。借金が無くなると、国民のお金も無くなる」とは、どういうことだろう。
我々が使うお金(貨幣、紙幣)は日本銀行が発行しているのではなく、財務省から独立した独立行政法人「国立印刷局」が、コンピューターネットワーク上にある電子情報を貨幣として使えるようにするために製造している。日本銀行から市中に払い出された通貨の総量を通貨流通高というが、2017年の大晦日、一般家庭や企業、金融機関などで年越しした銀行券(お札)の残高は、合計で107兆円だった。2018年度予算は約100兆円だ。政府は民間企業の業務と同じで、予算額を貨幣で配分しているわけはない。我々は貨幣をお金だと信じているが、お金はコンピュータに情報としてあり、それが増え続けて、政府の借金を1100兆、国民の全てのお金も1100兆円と増やしている。
参考:「国内のお金の流通量は101兆、国の借金は1000兆円」
・・・日本の貿易黒字のことには触れられていないが、後で考えよう。
5.お金はどこで生まれる?
それでは何故、お金は増え続けているのか。お金を生むのは日銀ではなく民間銀行だそうだ。民間銀行は「受け入れている預金等の一定比率(法定準備率)以上の金額を日本銀行に預け入れること」を義務付ける準備預金制度の下に、自由にお金を融資することができる。この制度は、もともと金融緩和・引締めの手段として決められたものだが、その機能を失い、1991年10月を最後にこの制度の法定準備率(1991年10月以来一定(1.2%))は変更されていない。日銀はその理由を「日本銀行の潤沢な資金供給により、多くの金融機関が法定準備預金額を超える『超過準備』を有することが常態化」したためと説明しているが、大西先生は1991年10月以来一定(1.2%)の「法定準備率以上のお金を日銀に上納すれば、残りのお金を民間銀行は自由に融資できる」と説明している。日銀は「法定準備預金額」を維持することはできるが、それ以上のお金を生み出すことはできないはずだ。
6.お金は電子情報として生まれる
お金は大西先生が説明されるように、民間銀行でしか生まれない。しかも、そのお金はコンピュータの電子情報として生まれる。電子情報であっても民間の帳簿は貸方、借り方のプラスマイナスはゼロになる。しかし、政府の発行した電子情報は税金で回収する部分があっても、2018年であれば約100兆円の一部を回収しているだけだ。残りは電子情報に残り増え続ける。増え続けているのは、政府によって生まれたお金なのだ。政府の予算は電子情報での貸し借り。これを毎年、国民が返済するとプラスマイナスゼロでお金は増えない。しかし毎年の政府の予算は、税金によっては全額は回収されないので、残りの部分のお金は増加する。これに貿易黒字でドルで蓄積されている使えないお金も貯まっている。貿易黒字の問題は後に考えるとして、「政府の借金は1100兆円、国民の全てのお金も1100兆円。借金が無くなると、国民のお金も無くなる」とは、お金は電子情報として増加しているが、コンピュータの電子情報のお金はプラスマイナスゼロで相殺されて消える。しかし、貿易黒字のドルは円に交換できないので、電子情報としてのお金も増え続けているということだ。
ここに2018年10月5日に公表された「マネタリーベースと日本銀行の取引(2018年9月)」を紹介しておく。世の中に出回っているお金は、流通現金(「日本銀行券発行高(紙幣)」+「貨幣流通高(硬貨)」)である。また、日銀当座預金は法定準備金制度の準備金であり、、市中には出回らない。最近は約110兆円の現金が市中で流通している。
―――――――――――――――――――――――――――――――
18/7月 8月 9月
(月末残高・億円) 2018/Jul. Aug. Sep.
―――――――――――――――――――――――――――――――
日本銀行券発行高 1,046,013 1,047,502 1,047,162
貨幣流通高 47,760 47,862 47,920
日銀当座預金 3,936,015 3,924,273 3,954,799
―――――――――――――――――――――――――――――――
マネタリーベース 5,029,788 5,019,637 5,049,881
―――――――――――――――――――――――――――――――
参考:マネタリーベース統計とは何ですか。
マネタリーベース=「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」+「日銀当座預金」
7.貿易黒字の行く先
財務省貿易統計(図)によると、貿易額は1960年代後半から増加し、1981年から2010年までの約30年間は黒字を続けてきた。しかし、2008年、お金のことしか考えない実体のないマネー資本主義はリーマンショックで世界金融恐慌を引き起こし、それまで増加していた貿易額は減少し、2010年から2014年までは日本の貿易収支も赤字となった。しかし、2015年から再び黒字になっている。貿易はドルで決済されるので、30年間の輸出超過により、ドルは毎年約10兆円蓄積したことになる。このドルは円に変換できないので、ザックリ計算すれば300兆円が蓄積していることになる。日本は財政危機どころか世界一の使えないお金を持った金持ち大国なのである。心配すべきは赤字による財政崩壊ではなく、現在の持続不可能な金融システムの崩壊なのである。
大西先生が実践したいのは、地方通貨の様な持続可能な金融システムに現在のシステムを転換すること。それには世界の人の常識を変えねばならない。明治維新から150年、江戸末期の常識と今では大きく違っている。「歴史は勝者によりつくられる」というが、科学的根拠のある知見は別にして、政治・経済の常識も勝者によりつくられている。常識には誰にも否定できないような科学的知見もあるように、経済の常識は、誰も否定できない「お金の量=価値の量」とすべきである。
貿易黒字も持続不可能な金融システムを動かしている勝者に使わせないで、国民の幸福のために使わねばならない。日本は地球から見れば一つの地方であり、「円」を地方通貨として使う方法を考えることが第一だが、毎年、使うことができない貿易黒字は100年~150年先を見通した事業に使う方法もあろう。
今の政治と経済のリ-ダーは、今の金融システムは持続不可能であることを理解していないばかりか、その崩壊を加速させている。規模拡大によるコストダウンが常識とされているが、これを目標にしている人たちは、金融崩壊の被害を一番大きく受け、自然の恵みに生き「里山資本主義」を実践している人達は生き残るであろう。
参考:大西つねき「日本から世界を変える動画/お金のあるべき姿」 「国家経営のあり方(現在の問題点)」 「国家経営のあり方(未来の国家)」 「集団的自衛権について
8.常識を疑うことが、未来を拓く
京都大学の本庄先生がノーベル賞を受賞された。その先生が常識を疑え、教科書にもウソがある、学術論文も疑って読めと強調されている。先生は学生の時、進路に弁護士よりも、より多くの人に貢献できる医学の分野を選ばれた。そして、手術とか人間を人工的に治療することが常識となり、人間が本来持っている免疫の力を使う免疫療法を古い、怪しいと否定されていた医療界に、ノーベル賞という権威で免疫療法を認知させ、常識を転換させた。大西先生も同じだと思う。今の金融システムは人間の生活を破壊している。そのことに人々が気付き「地域通貨」の考え方を「世界通貨」にする動きが出れば、ノーベル賞以上の仕事となる。ノーベル賞をここで取り上げるのは、ノーベル賞受賞はメディアが大きく取り上げ、大西先生の考え方を世界に認知されることを意味するから。世界の常識を変えることは、人類を一歩前進させる偉大な仕事なのだ。
明日は京都で、「大西つねき」さんの講演会があります。
10月7日(日)13:30〜16:30 場所:あわたまKYOTO
〒602-8373 京都市上京区下横町207-1 地図
参加費 1000円(横浜からの大西つねきさんの交通費になります。)
初稿 2018.10.6 更新 2019.3.11 更新(2020.2.23ブログ目次削除)










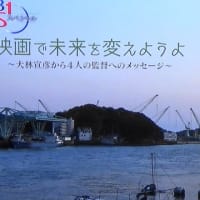



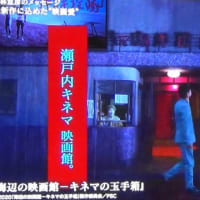
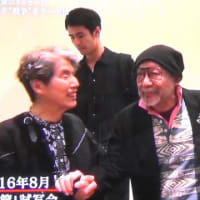

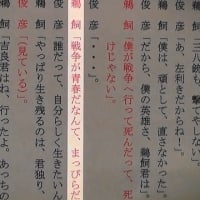



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます