
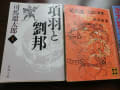

西安は、唐が滅びる10世紀初頭までの2千年間の間に、12の王朝によって通算1120年間という、中国史上で最も長い期間にわたり王朝の都がおかれた地である。この地がこれほど長く王朝の都として栄えてきたのは、その地理的条件に理由(わけ)があるようだ。
西安がある広大な渭河平原(いがへいげん)は、広大な盆地となっている。平原の東西には黄河の支流「渭河」が流れ、北は黄土高原が続いている。南には秦嶺山脈(しんれいさんみゃく)がそびえている。肥沃な土地と豊かな水源、そして山脈による自然の城塞など、王朝の都として多くの好条件が備わった地である。西には六盤山脈がそびえ、洛陽などのある中原の河南省に通じるには、黄河を挟んだ山地・山脈により、けっこう狭い通路となり、そこには「函谷関」(かんこくかん)の関がある。つまり、豊かな水に恵まれた肥沃な土地が広がり、山地・山脈と渓谷に囲まれた防衛しやすい地である。
そして、この地を舞台に 秦の始皇帝や漢の武帝(劉邦)、唐の玄宗皇帝や楊貴妃などの中国史を彩る人物、杜甫や李白などの詩人、日本人留学生の「空海」や「阿倍仲麻呂」などが活躍した。そして、京都の平安京や奈良の平城京は、長安の都をモデルとして造営された。





城壁の上には、売店や貸自転車の店があった。自転車を使って2〜3時間をかけて城壁を1周する人もけっこういるようだ。「唐」の時代の「長安城」の絵地図もあった。唐の時代の長安城は、現在の明時代の西安城よりも少し西側のほうにあったようだ。
中国には「七大古都」と言われているものがある。全て王朝の都がおかれた都市だ。北京市・南京市(江蘇省)・西安市(陝西省)と洛陽市・安陽市・開封市(いずれも河南省)、杭州市(浙江省)の七つの古城である。
ちなみに、西安市は日本の京都市・奈良市・小浜市(福井県)などと姉妹都市の関係を締結している。













城壁を降りて、城内側の南門を出ると休憩所の建物があった。中に入ると「西安・長安城」のことを紹介した映像が流されていた。この南門の前では、国際会議の開催や大事な祝祭日や記念日などに合わせて、「唐」の時代を再現したショーが行われるようだ。







城壁の外に出る。12mの高さの城壁はけっこう高い。城壁は自動車や通行のために逆U字型のトンネル通路が市内に何か所も作られている。



南門付近の堀ばたの城壁が美しい。ホテルに向かって歩いていく。西安城にマッチした外観デザインのホテルだと感じる。





中国では、わずか60年ほど前まで、多くの都市では、そこに住む中国人の人々は城郭の中で暮らしていた。外国からの侵略軍はもとより、各地に割拠した軍閥、盗賊、流民から身を守るためにも、頑丈な城壁に囲まれた城内が最も安全であった。夕方に日が暮れると城門はしめられた。そして早朝に日が昇ると城門が開けられた。城門が閉まってしまうと 城壁の外で野宿をしなければならなくなる。
1949年の中華人民共和国が成立し、平和が訪れると 城はいらなくなった。北京をはじめ 多くの都市では 交通に支障が起きる城壁がとりはらわれたり、壊れても修復せず、どんどんとなくなっていった。街を取り囲んだ城壁の跡は、広い環状道路に生まれ変わることも多かった。
城壁の多くは取り払われたが、門や城内の鍾楼や鼓楼(時を知らせるために、鐘をついたり太鼓をたたくための楼)は残される場合が多かったようだ。特に、文化大革命の10年間の時期は、「古く歴史的な建造物」の破壊が薦められた。このため、城壁の規模周囲が30kmにも及んだ古都・南京の城壁なども多くがなくなった。
文化大革命が終結した1976年。改革開放路線に政治方針が切り替わった。西安の市民は、城壁の修復と再建に向けて市民の多くが参加協力して、城壁の再建修復に取り組んだ。この結果、今の「西安城の城壁」がある。中国で最も完全に「城壁」が大規模に残っているのがこの西安である。世界的にもこれだけ大規模な城郭が完全な形で残っている都市は、他にはないといわれている。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます