(以下、日経ビジネスONLINEから転載)
=======================================
震災で問い直す「高信頼性組織」の条件
災害避難の“常識”も再検証せよ
元吉 忠寛
3月11日に発生した東日本大震災──。地震、津波という自然災害に原発事故という社会災害が重なり合う未曽有の事態は、これまで社会や企業が前提としてきた安全の常識を次々と覆した。3月11日を境にどのような常識が新たに形成されていくのか。それに応じて社会や企業活動の安全マネジメントをどう変えていかなければならないのか。
このコラムでは、自然災害と事故などの社会災害の両方に精通した防災や危機管理のプロを育成する場として日本で初めて誕生した関西大学社会安全学部の教授陣が、社会や企業の安全マネジメントについての新たな考え方や具体策を講義していく。
今回は、災害や学校における危機などのリスクに対する人々の認識や意思決定、行動について研究している元吉忠寛准教授が、心理学の視点から、被災者の避難方法や組織の危機対応、心のケアのあり方などについて提言する。
(構成は、峯村創一=フリーライター)
震災の発生から半年が過ぎ、家を失うなどして避難所で暮らしていた被災者の大半が、仮設住宅で新たな生活を始めている。9月上旬、私は岩手県盛岡市に足を運び、被災者支援のNPO(非営利組織)「SAVE IWATE」の協力を得て、壊滅的な被害を受けた同県沿岸部から避難してこられた被災者の方々のお話をうかがう機会を得た。
彼らが口々に話されたのは、地震被害の少なかった盛岡市に移って日常生活を営むことによって、心の安定を得られたということだ。
もともとは沿岸部の宮古市や大槌町に住んでいた方々だ。被災して約2週間後に、内陸部にある安比高原のホテルへ避難。そこで3カ月半ほど過ごした後、7月下旬からは被災者を対象とした民間賃貸住宅の借り上げ制度を利用して、盛岡市内のアパートに滞在している。
宮古市や大槌町から、避難先の安比高原や盛岡市までは、直線距離にして約70~80キロ離れている。多くの被災者が、自宅近くの避難所に移動し、現在もなお近郊の仮設住宅で暮らしているのと比べると、彼らが経験した避難経路は特別なものだった。
やはり長年にわたって住み慣れた土地であっても、避難所や仮設住宅は特殊な環境であり、日常からかけ離れている。被災者が長くこの状態に置かれたままでは、「惨事ストレス」を解消することは難しい。
「被災者は避難所に入る」という常識を改めよ
「惨事ストレス」とは、大規模な災害で悲惨な光景を直接目撃した人や、間接的に見聞きした人が、その恐怖を思い出したり、助けられなかったという自責の念にさいなまれたりすることに起因するストレス反応だ。
具体的には、不眠や気分の不調、放心状態などの反応が表れる。これを放置すると、「急性ストレス障害(ASD)」、さらに進行すると「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」に発展する恐れがある。
特に、子供たちにとっては、日常からかけ離れた生活が長期にわたって続くことで、惨事ストレスがさまざまな心身の反応となって出てきてしまう。こうした状況は、1日も早く解消されなければならない。
日本の災害対応は、被災者はまず地域の避難所へ避難することが前提になっている。しかし今回のように地域が丸ごと壊滅的な被害を受けた場合は、早い段階で、たとえ距離が遠くても安心して日常生活を送れる場所に移動するべきである。
例えば、盛岡市のような都市部に移れば、日々の食事や買い物、家事、育児などの家庭生活は不自由なく営むことができる。単に何をするにも便利だというだけでなく、精神的にも平安がもたらされる。
いわゆる「災害弱者」と呼ばれる人たちにとっても、やはり不便で困難が多い場所に長期間とどまるより、一刻も早く安全で居心地のよい場所へ移転を進めた方がよい。そうすれば、彼らへの支援の手を差し伸べやすくなるし、現地の復興も推進しやすくなるはずだ。
ただ、地元を離れることで、情報が入りにくくなる懸念はある。自宅の被害が拡大していないか見えなくなるし、コミュニティー内の口コミで共有されているようなきめ細かい情報も入らず、行政の支援情報にも疎くなりかねない。
そうした事態を想定して、地方自治体の中には、地元を離れた被災者にきめ細かな情報を伝達する仕組みを作っているところもある。
例えば、北海道では、被災による道内への避難者に対し、「ふるさとネット」というサービスを提供。避難先の市町村を通じて登録しておくと、その市町村での支援情報はもちろん、出身地に関する情報が電子メールやファクス、郵送などの手段を通して入手でき、教育、福祉、医療に関する相談や、同郷者との交流にも参加できる。
本来は、地域コミュニティーを丸ごと安全な場所へ移転できればよいのだが、物理的な限界があり難しい。このような取り組みを通じて、せめて情報が途絶しないようにすることが大切である。
危機にうまく対応する「高信頼性組織」
今回の東京電力・福島第1原子力発電所の事故では、東電や政府は危機対応のまずさを露呈した。現場の情報がトップに上がらず、トップは判断し決断するスピードに欠け、対応は後手に回った。
私は、いじめや不登校、学級崩壊、非行、犯罪被害など教育現場で起きる「危機」に対する学校の組織的な対応について研究している。その中で見えてくることは、同じような危機に直面しても、それにうまく対応し解決できる学校と、適切に対応できずに被害を拡大させ、まさに危機的な状況に陥ってしまう学校があるということだ。
また、危機を未然に防止できている学校もあれば、次々と新しい問題が起きて、その対応に追われ続けている学校もある。このような事実は、学校に限らず何らかの組織に属している多くの人が感じていることだろう。いったい両者の違いは何に起因するのだろうか。
それを解く重要な鍵の1つが、「高信頼性組織」の概念だ。もともとは原子力発電所をはじめ、空港の航空管制塔、病院の救急救命棟など、不測の事態に直面し、失敗の許されない現場を対象に研究されてきた組織のあり方である。最近では、学校や一般企業におけるリスクマネジメントにも適用されるようになっている。
危機に直面した高信頼性組織に求められるのは、「正直さ」「慎重さ」「鋭敏さ」「機敏さ」「柔軟さ」といった要素である。とりわけ重要になるのが、「正直さ」と「柔軟さ」だ。
「正直さ」とは、組織の中で嘘や隠しごとがなく、お互いに伝え合うコミュニケーションが成立していることである。減点主義の組織だと、正直さはどんどん失われる。「誰が悪いのか」という犯人捜しに目が向き、自分のミスは覆い隠そうとする。また、人間関係がギクシャクしている組織では、意識が解決の方に向かないで、組織内部の足の引っ張り合いに費やされてしまう。
逆に、自らのミスについて話すことが自分にとって不利にならない組織では、「原因は何か」「どう改善すればいいのか」と前向きな視点を共有できる。これが、危機を未然に防ぎ、危機が発生しても迅速に解決できる組織の特徴の1つである。
もう1つの重要な要素が、「柔軟さ」である。たとえ綿密な対応マニュアルを準備していたとしても、現実は想定通りにはいかないものだ。事態を冷静に判断したうえで、マニュアルだけに頼らない柔軟な対応が求められる。柔軟に決定を変更することも、リスクマネジメントでは重要になってくる。
震災の直後には、「今まで津波警報が出ても大丈夫だったから避難しない」「避難場所はこの施設と定められているから、そこへ避難する」など、過去の経験やルールに縛られたケースが見られた。
また官僚的な組織、特に「お役所」は、非常時でも平常時のルールを適用しようとするため、「避難所にいる被災者の数だけ弁当が用意できなければ、届けられない」といった硬直した対応があり、問題となった。
我々は、非常時には「規範が変わる」ということを知らなければならない。平常時には「ルール違反」とされていることも、非常時には「正しい」ことになり得る。
「柔軟さ」を発揮したヤマト運輸の対応
例えば、被災地におけるヤマト運輸のケースがそうだ。地震発生直後から、同社の地元ドライバーたちが、上司や本社の判断を仰がずに役所と掛け合い、会社の車を使って無償で救援物資の輸送を始めた(出所:ほぼ日刊イトイ新聞―クロネコヤマトのDNA)。
東京でも震災当日、鉄道がストップし帰宅難民があふれた都心で、コンビニエンスストアチェーンのある店舗では、おにぎりが売り切れてしまったために、近所の商店街の専門店からおにぎりを仕入れて売っていたと聞く。
どちらも平常時にはあってはならないことだが、非常時においては人々を救う正しい行動となった。
実際、震災発生から12日後の3月23日には、ヤマト運輸の本社は、現場の判断を追認する形で「救援物資輸送協力隊」を立ち上げ、救援物資を避難所、集落、病院、養護施設などに届ける活動を始めた(出所はこちら)。「高信頼性組織」として必要な「柔軟さ」が発揮された好例と言えるだろう。
心のケアは専門家だけに任せるな
被災地では、「心のケア」も重要な課題だ。心のケアというと、臨床心理士や精神科医師など専門家の出番だと思われがちである。しかし、深刻な症状がある場合を除いて、突然外部から一時的にやってきた専門家に任せるよりも、普段から交流のある周りの人たちが、苦しんでいる人を支える方がいい。
具体的には、被災者の方に、自分の気持ちを素直に話していただけるような環境を作ることだ。話すことによって、自分の気持ちが整理されてくるからである。
「足湯隊」といって、被災者の方に足湯のマッサージをしながら、話を傾聴するというボランティア活動がある。マッサージは心身の緊張をほぐし、ストレスケアに効果的だ。自然な形でちょっとした悩みや不安などを話すことができ、とてもいい方法だと思う。
ただ、地域外から被災地に入って行われている活動であり、それが1回限りで終わってしまうと、かえって後から寂しい思いを味わわせてしまうことになる。できるだけ繰り返し行い、継続していくことが必要だ。
基本的には、地域のコミュニティーの中で解決を図っていくのがいいだろう。例えば、地域内の集会所でお茶を飲みながら話ができるサロンのようなものを整えることが、ストレス軽減につながると考えられる。
ここでも指摘しておきたいのは、心のケアの前に、ストレスのない安全で安心できる場所の確保が先決ということである。まだ避難所にいる間や、自宅にいても余震が起きて不安になるような状況では、「話を傾聴する」のは早すぎる。そういう意味でも、「まずは、地域の避難所へ」という現在の災害避難の“常識”は再検証する必要がある。
心の専門家のやるべき仕事は、一歩引いた立場から全体を見渡し、コミュニティーの中で心のケアができるような環境づくりのお手伝いをすることだ。そして、心のケアを行う支援者が迷った時に、適切なアドバイスを行う。地域の資源を活用しつつ、環境を整えられる専門家が求められている。
安全・安心な社会の構築を目指すここ関西大学社会安全学部の学生たちも被災地を訪ね、想像をはるかに上回る現実と対峙しながら、多くのことを学んでいる。私も、彼らが将来、学識と経験を備えた専門家として貢献できるよう育成に力を注いでいきたいと思う。
=======================================
震災で問い直す「高信頼性組織」の条件
災害避難の“常識”も再検証せよ
元吉 忠寛
3月11日に発生した東日本大震災──。地震、津波という自然災害に原発事故という社会災害が重なり合う未曽有の事態は、これまで社会や企業が前提としてきた安全の常識を次々と覆した。3月11日を境にどのような常識が新たに形成されていくのか。それに応じて社会や企業活動の安全マネジメントをどう変えていかなければならないのか。
このコラムでは、自然災害と事故などの社会災害の両方に精通した防災や危機管理のプロを育成する場として日本で初めて誕生した関西大学社会安全学部の教授陣が、社会や企業の安全マネジメントについての新たな考え方や具体策を講義していく。
今回は、災害や学校における危機などのリスクに対する人々の認識や意思決定、行動について研究している元吉忠寛准教授が、心理学の視点から、被災者の避難方法や組織の危機対応、心のケアのあり方などについて提言する。
(構成は、峯村創一=フリーライター)
震災の発生から半年が過ぎ、家を失うなどして避難所で暮らしていた被災者の大半が、仮設住宅で新たな生活を始めている。9月上旬、私は岩手県盛岡市に足を運び、被災者支援のNPO(非営利組織)「SAVE IWATE」の協力を得て、壊滅的な被害を受けた同県沿岸部から避難してこられた被災者の方々のお話をうかがう機会を得た。
彼らが口々に話されたのは、地震被害の少なかった盛岡市に移って日常生活を営むことによって、心の安定を得られたということだ。
もともとは沿岸部の宮古市や大槌町に住んでいた方々だ。被災して約2週間後に、内陸部にある安比高原のホテルへ避難。そこで3カ月半ほど過ごした後、7月下旬からは被災者を対象とした民間賃貸住宅の借り上げ制度を利用して、盛岡市内のアパートに滞在している。
宮古市や大槌町から、避難先の安比高原や盛岡市までは、直線距離にして約70~80キロ離れている。多くの被災者が、自宅近くの避難所に移動し、現在もなお近郊の仮設住宅で暮らしているのと比べると、彼らが経験した避難経路は特別なものだった。
やはり長年にわたって住み慣れた土地であっても、避難所や仮設住宅は特殊な環境であり、日常からかけ離れている。被災者が長くこの状態に置かれたままでは、「惨事ストレス」を解消することは難しい。
「被災者は避難所に入る」という常識を改めよ
「惨事ストレス」とは、大規模な災害で悲惨な光景を直接目撃した人や、間接的に見聞きした人が、その恐怖を思い出したり、助けられなかったという自責の念にさいなまれたりすることに起因するストレス反応だ。
具体的には、不眠や気分の不調、放心状態などの反応が表れる。これを放置すると、「急性ストレス障害(ASD)」、さらに進行すると「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」に発展する恐れがある。
特に、子供たちにとっては、日常からかけ離れた生活が長期にわたって続くことで、惨事ストレスがさまざまな心身の反応となって出てきてしまう。こうした状況は、1日も早く解消されなければならない。
日本の災害対応は、被災者はまず地域の避難所へ避難することが前提になっている。しかし今回のように地域が丸ごと壊滅的な被害を受けた場合は、早い段階で、たとえ距離が遠くても安心して日常生活を送れる場所に移動するべきである。
例えば、盛岡市のような都市部に移れば、日々の食事や買い物、家事、育児などの家庭生活は不自由なく営むことができる。単に何をするにも便利だというだけでなく、精神的にも平安がもたらされる。
いわゆる「災害弱者」と呼ばれる人たちにとっても、やはり不便で困難が多い場所に長期間とどまるより、一刻も早く安全で居心地のよい場所へ移転を進めた方がよい。そうすれば、彼らへの支援の手を差し伸べやすくなるし、現地の復興も推進しやすくなるはずだ。
ただ、地元を離れることで、情報が入りにくくなる懸念はある。自宅の被害が拡大していないか見えなくなるし、コミュニティー内の口コミで共有されているようなきめ細かい情報も入らず、行政の支援情報にも疎くなりかねない。
そうした事態を想定して、地方自治体の中には、地元を離れた被災者にきめ細かな情報を伝達する仕組みを作っているところもある。
例えば、北海道では、被災による道内への避難者に対し、「ふるさとネット」というサービスを提供。避難先の市町村を通じて登録しておくと、その市町村での支援情報はもちろん、出身地に関する情報が電子メールやファクス、郵送などの手段を通して入手でき、教育、福祉、医療に関する相談や、同郷者との交流にも参加できる。
本来は、地域コミュニティーを丸ごと安全な場所へ移転できればよいのだが、物理的な限界があり難しい。このような取り組みを通じて、せめて情報が途絶しないようにすることが大切である。
危機にうまく対応する「高信頼性組織」
今回の東京電力・福島第1原子力発電所の事故では、東電や政府は危機対応のまずさを露呈した。現場の情報がトップに上がらず、トップは判断し決断するスピードに欠け、対応は後手に回った。
私は、いじめや不登校、学級崩壊、非行、犯罪被害など教育現場で起きる「危機」に対する学校の組織的な対応について研究している。その中で見えてくることは、同じような危機に直面しても、それにうまく対応し解決できる学校と、適切に対応できずに被害を拡大させ、まさに危機的な状況に陥ってしまう学校があるということだ。
また、危機を未然に防止できている学校もあれば、次々と新しい問題が起きて、その対応に追われ続けている学校もある。このような事実は、学校に限らず何らかの組織に属している多くの人が感じていることだろう。いったい両者の違いは何に起因するのだろうか。
それを解く重要な鍵の1つが、「高信頼性組織」の概念だ。もともとは原子力発電所をはじめ、空港の航空管制塔、病院の救急救命棟など、不測の事態に直面し、失敗の許されない現場を対象に研究されてきた組織のあり方である。最近では、学校や一般企業におけるリスクマネジメントにも適用されるようになっている。
危機に直面した高信頼性組織に求められるのは、「正直さ」「慎重さ」「鋭敏さ」「機敏さ」「柔軟さ」といった要素である。とりわけ重要になるのが、「正直さ」と「柔軟さ」だ。
「正直さ」とは、組織の中で嘘や隠しごとがなく、お互いに伝え合うコミュニケーションが成立していることである。減点主義の組織だと、正直さはどんどん失われる。「誰が悪いのか」という犯人捜しに目が向き、自分のミスは覆い隠そうとする。また、人間関係がギクシャクしている組織では、意識が解決の方に向かないで、組織内部の足の引っ張り合いに費やされてしまう。
逆に、自らのミスについて話すことが自分にとって不利にならない組織では、「原因は何か」「どう改善すればいいのか」と前向きな視点を共有できる。これが、危機を未然に防ぎ、危機が発生しても迅速に解決できる組織の特徴の1つである。
もう1つの重要な要素が、「柔軟さ」である。たとえ綿密な対応マニュアルを準備していたとしても、現実は想定通りにはいかないものだ。事態を冷静に判断したうえで、マニュアルだけに頼らない柔軟な対応が求められる。柔軟に決定を変更することも、リスクマネジメントでは重要になってくる。
震災の直後には、「今まで津波警報が出ても大丈夫だったから避難しない」「避難場所はこの施設と定められているから、そこへ避難する」など、過去の経験やルールに縛られたケースが見られた。
また官僚的な組織、特に「お役所」は、非常時でも平常時のルールを適用しようとするため、「避難所にいる被災者の数だけ弁当が用意できなければ、届けられない」といった硬直した対応があり、問題となった。
我々は、非常時には「規範が変わる」ということを知らなければならない。平常時には「ルール違反」とされていることも、非常時には「正しい」ことになり得る。
「柔軟さ」を発揮したヤマト運輸の対応
例えば、被災地におけるヤマト運輸のケースがそうだ。地震発生直後から、同社の地元ドライバーたちが、上司や本社の判断を仰がずに役所と掛け合い、会社の車を使って無償で救援物資の輸送を始めた(出所:ほぼ日刊イトイ新聞―クロネコヤマトのDNA)。
東京でも震災当日、鉄道がストップし帰宅難民があふれた都心で、コンビニエンスストアチェーンのある店舗では、おにぎりが売り切れてしまったために、近所の商店街の専門店からおにぎりを仕入れて売っていたと聞く。
どちらも平常時にはあってはならないことだが、非常時においては人々を救う正しい行動となった。
実際、震災発生から12日後の3月23日には、ヤマト運輸の本社は、現場の判断を追認する形で「救援物資輸送協力隊」を立ち上げ、救援物資を避難所、集落、病院、養護施設などに届ける活動を始めた(出所はこちら)。「高信頼性組織」として必要な「柔軟さ」が発揮された好例と言えるだろう。
心のケアは専門家だけに任せるな
被災地では、「心のケア」も重要な課題だ。心のケアというと、臨床心理士や精神科医師など専門家の出番だと思われがちである。しかし、深刻な症状がある場合を除いて、突然外部から一時的にやってきた専門家に任せるよりも、普段から交流のある周りの人たちが、苦しんでいる人を支える方がいい。
具体的には、被災者の方に、自分の気持ちを素直に話していただけるような環境を作ることだ。話すことによって、自分の気持ちが整理されてくるからである。
「足湯隊」といって、被災者の方に足湯のマッサージをしながら、話を傾聴するというボランティア活動がある。マッサージは心身の緊張をほぐし、ストレスケアに効果的だ。自然な形でちょっとした悩みや不安などを話すことができ、とてもいい方法だと思う。
ただ、地域外から被災地に入って行われている活動であり、それが1回限りで終わってしまうと、かえって後から寂しい思いを味わわせてしまうことになる。できるだけ繰り返し行い、継続していくことが必要だ。
基本的には、地域のコミュニティーの中で解決を図っていくのがいいだろう。例えば、地域内の集会所でお茶を飲みながら話ができるサロンのようなものを整えることが、ストレス軽減につながると考えられる。
ここでも指摘しておきたいのは、心のケアの前に、ストレスのない安全で安心できる場所の確保が先決ということである。まだ避難所にいる間や、自宅にいても余震が起きて不安になるような状況では、「話を傾聴する」のは早すぎる。そういう意味でも、「まずは、地域の避難所へ」という現在の災害避難の“常識”は再検証する必要がある。
心の専門家のやるべき仕事は、一歩引いた立場から全体を見渡し、コミュニティーの中で心のケアができるような環境づくりのお手伝いをすることだ。そして、心のケアを行う支援者が迷った時に、適切なアドバイスを行う。地域の資源を活用しつつ、環境を整えられる専門家が求められている。
安全・安心な社会の構築を目指すここ関西大学社会安全学部の学生たちも被災地を訪ね、想像をはるかに上回る現実と対峙しながら、多くのことを学んでいる。私も、彼らが将来、学識と経験を備えた専門家として貢献できるよう育成に力を注いでいきたいと思う。















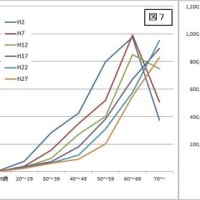
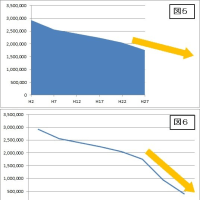
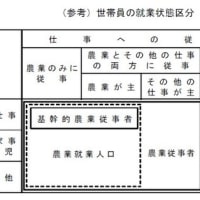
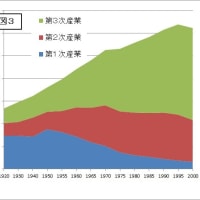
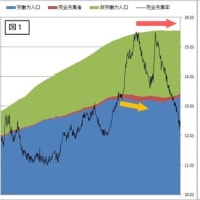
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます