
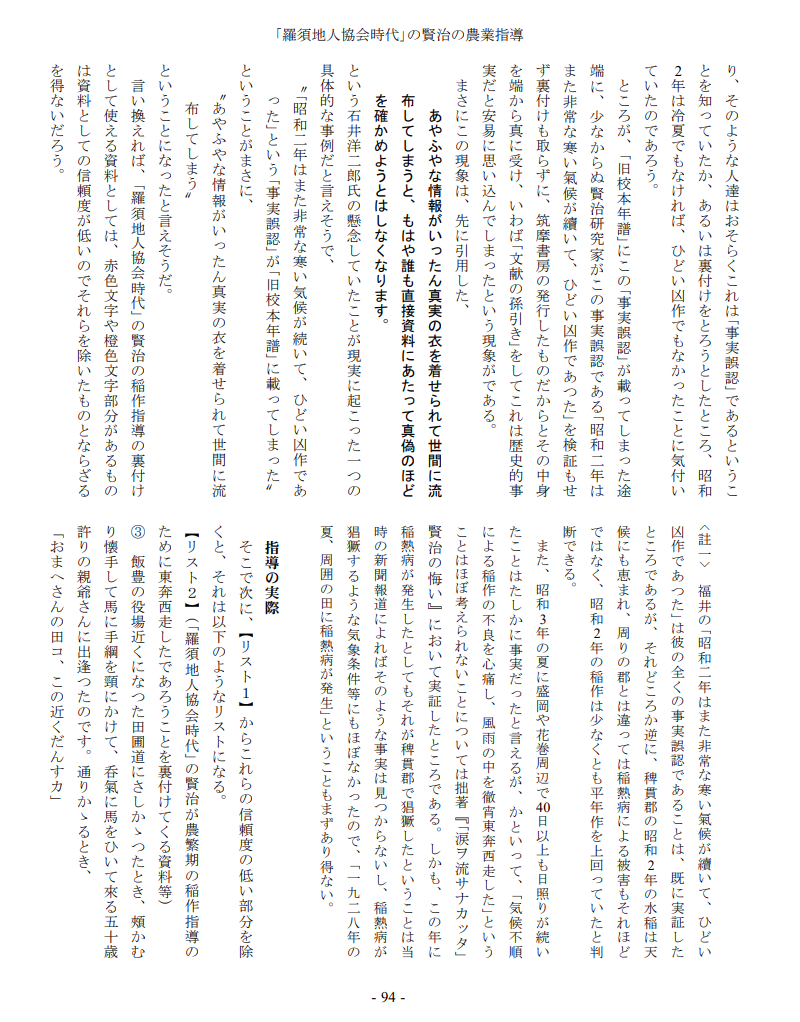



 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ。
“『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ。********************************** なお、以下は今回投稿分のテキスト形式版である。**************************
指導の実際
そこで次に、【リスト1】からこれらの信頼度の低い部分を除くと、それは以下のようなリストになる。
【リスト2】(「羅須地人協会時代」の賢治が農繁期の稲作指導のために東奔西走したであろうことを裏付けてくる資料等)
③ 飯豊の役場近くになつた田圃道にさしかゝつたとき、頰かむり懐手して馬に手綱を頸にかけて、呑氣に馬をひいて來る五十歳許りの親爺さんに出逢つたのです。通りかゝるとき、
「おまへさんの田コ、この近くだんすカ」
雪溶けの水でザンブと浸つてゐた田に手を突込んで、眞黑な土を取り出して、指でこすつてみたり、水洗ひして、掌でよく觀察してをつたやうですが
「去年の稻なじょだつたス」
「…………………………」
「肥料何々やつたス
金肥なじよなのやつたス」
「…………………………」
尚も掌の土をこまごまと調べてをつたのですが、
「それぢア、今年の肥料少し考へだほーよがんす」
「………………………………」
「………………………………」
汚くなつた手をザブザブと無雜作に洗ひ流してゐました。
親爺さんは、
「おまへさん、どこの人だんス」
「近くの町の人ス」
先生はかうして一百姓に、今年の取るべき稻作方法を教へたのですが、懇ろに教へ導いて行く樣子は、誠に快い感じを與へてくれるのでした。気障ではなく、心の奥底から迸る誠意の言葉であつたのです。
<『宮澤賢治研究』(草野心平編、昭和14年)409p~所収
「宮澤賢治先生(照井謹二郎)」>
⑤ 五日間ほどでその相談所を閉ぢましたが、苗が水田に移されて大分經つた頃、賢治さんはこの地方の稻草の状況を視察に來たらしく、ひよつこり教え子の菊田の家に立ち寄りました。
「この邊を濟まないが案内して下さい。」
焦げ穴のあるヅボンにゴム靴を履いた賢治さんは、行く先々でゴム靴を脱いで田の中に入り、手をつゝこんで水溫地中溫を調べ、莖をたはめて稲の強さを計り、その缺點を指摘し、處理すべきことをいひ付けて行きます。その後は九月まで一人で來て、その地方の田を幾囘見廻つたか判りません。大變な責任をもつたものです。
<『宮澤賢治』(佐藤隆房著、昭和17年)、178p>
⑥ 賢治氏は稲作の指導といふよりはもつと根本的な土壌の改良、肥料の設計、勞働の能率等について、農村自體の向上のために非常な努力を拂はれました。齋藤彌惣さんの家にも年々二度位づゝわざわざ出かけて行き、その直接の指導にあたりました。
鍋倉は町から近道を行けば約一里半ですが、賢治氏は志戸平温泉へ行く方の道、つまり縣道を眞直ぐに行つて、途中上根子や二ツ堰の部落の人たちを訪問し、その足で鍋倉へ行きました。鍋倉を終ると、湯口村の隣の湯本村へ行つて、小瀬川部落などを訪問して歸るのであります。…(筆者略)…
賢治氏はそれから齋藤さんと畠へ出て行きそのへんの土を手にとりながら、土壌改良法に就いて、齋藤さんに解り易い言葉を以て叮寧に説明します。
<『宮澤賢治素描』(関登久也著、協榮出版、昭和18年)、3p~>
⑦ 羅須地人協会ができるとともに、宮澤先生のお仕事は、ひろくふかくなつて來ました。花巻の町や、花巻の近くの村に、肥料相談所をつくりました。みんなただで、稻のつくり方の相談所をひらいたのです。そこで相談しただけでありません、來たひとびとのたんぼは秋のとり入れのときまで、見てまはつて、これはああすればよい、これはかうすればよいと、教へたのです。ときには、村村へ行つて、稻作の講演会もひらきます。もちろん、ただの一銭もお金はもらひません。
<『宮澤賢治』(森荘已池著、昭和18年)、175p>
⑩ 単に肥料や土壌のことばかりではなく、出來得るだけ農家自體の内容を聞いて、善處させるやうに智恵を借(ママ)してをりました。…(筆者略)…「齋藤さんとこの苗代は、苗代の位置が惡いし、芝垣も生えて日蔭になるから苗の生長もよくない。併し苗代を變へることはさう簡単にゆかないでせうから、來年はあそこの苗代を先づ半分こちらへ移し、翌年はまたかへてゆくやうにしてごらんなさい。」と親切に教へてくれました。
<『宮澤賢治素描』(関登久也著、眞日本社、昭和22年)>
⑫ 賢治の住んでいる下根子はじめ花巻あたりでは、春に田に種もみをまいてから、四十日目くらいに田植えをする習慣があつたが、賢治は、種もみをまいてから五十日目から、五日間位で植えるようにと教えている。
何故かというと、四十日で植えてしまうと、田によけいに肥料がいるからであると教えている。
「田の草は一箇月のうちにみなとつてしまつて、あとは田んぼの中にはいつてはいけない。稻の根を切つてはいけない。一本でも稻の根を切ると、もう一粒だけ、實の入らない粒が出る。」
と、いふように、まつたくこまかなところまで、ていねいに教えている。
水が冷たいので、どうしても思つたよりも米の収穫の少ないといつて指導をうけにくる農民には、
「苗をうすくまいてね、つよくそだてて、三本くらい一株にしてやつてみて下さい。」
と懇切な指導をしてくれるのである。
田んぼに、硫安を使うひけつを質ねると、
「ああ、それは雜作もないことですね。硫安を土に混ぜ、その土を田にまけば、硫安は土と共に田の底に沈み、田に水のある場合も流れず、まきちらした硫安の効果は充分にあがるわけです。もちろん、田植えをした後の田にまくのですね。」
こうした技術指導が、手にとるように行われたのである。賢治が、花巻近郊の農民から「肥料の神さま」といわれるようになつたことは當然なことであろうとおもう。
<『宮澤賢治 作品と生涯』(小田邦雄著、新文化出版、
昭和25年)、227p~>
⑬ 「齋藤さん、今年の稻の丈は去年よりどうですか。」と聞くと、齋藤さんはあいまいな面持ちをして、「どうもそこまで計つて見たこともありません。」といひますと、賢治氏は面を柔らげ「それは困りますね、農村人が他の文化より遲れてゐるやうにいはれたり、事実割の惡い貧乏に甘んじなければならなかつたりすることは、色々の社會的な關係もありませうが、農村自体がもつと聰明にならなければならない。唯昔からありきたりの習慣制度を守つただけで年月を過ごすやうでは、いつまでたつても、不遇の位置から逃れることは出來ません。それには心を、土壌にも肥料にも天候にも又農業に必要な知識へぴつたりと向けて、一日々々を大事な日として良い方へ向けてゆくより外に仕方がないのです。…(以下略)…」
<『雨ニモマケズ』(小田邦雄著、酪農学園出版部、
昭和25年)、192p~>
⑭「昨年の稲作は案外よくまことに安心いたしました。それはあの天候に対して燐酸と加里が充分入つてゐたのが効いたのでせう。
今年も昨年通りでいゝと思ひますが、なにぶんどの肥料も高くなつてゐますから、もしもつと安くしやうと思へば次の通りになります。但し結局は昨年通りが得でせう。」
◎肥料も大事ですがだんだん深耕してまだまだとる工夫をしませう。
<『雨ニモマケズ』(小田邦雄著、酪農学園出版部、
昭和25年)、205p~>
さてこの【リスト2】には、「羅須地人協会時代」の賢治が、いつ、どこで、誰に対してどんな稲作指導動をしたのかということが全て明らかになっている項目は一つもないとはいえども、少なくとも、それらの要素のうちの複数の要素が具体的である項目ばかりだからその信憑性は低くないと判断できるし、しかもそのような複数の項目があるということから、
「羅須地人協会時代」の賢治は飯豊の「五十歳許りの親爺さん」や鍋倉の齋藤さん、そして石鳥谷の菊田(実は菊池信一のこと)らに対して農繁期にも熱心に稲作指導をしたことがあるとほぼ断定できる。
ということがまず導ける。よって、「羅須地人協会時代」の賢治が農閑期には肥料設計に熱心に取り組んだことがあったということは「塚の根肥料相談所」についての証言等からもともと事実であったと私も判断できていたが、それだけではなく、
「羅須地人協会時代」の賢治は農繁期においても、稲作指導のために東奔西走したとまで言える裏付けは見つからなかったものの、熱心に取り組んだことがあったということはこれでほぼ明らかになった。
ということもまた導かれるだろう。逆に言えば、そのようなことであったということはこれでわかったのだが、それが「羅須地人協会時代」の農繁期全般に亘って行われ、そのために賢治が東奔西走していたのかとなるとそこまでの裏付けは見つからなかったから、
「羅須地人協会時代」の賢治が農繁期に農民たちに対しての稲作指導のために東奔西走したとまでは言い切れない。
ということもまた導かれたと言えるだろう。
******************************************************* 以上 *********************************************************
 “『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ。
“『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ。 “渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)”へ。
“渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

***********************************************************************************************************
《新刊案内》この度、拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』

を出版した。その最大の切っ掛けは、今から約半世紀以上も前に私の恩師でもあり、賢治の甥(妹シゲの長男)である岩田純蔵教授が目の前で、
賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私はいろいろなことを知っているのだが、そのようなことはおいそれとは喋れなくなってしまった。
と嘆いたことである。そして、私は定年後ここまでの16年間ほどそのことに関して追究してきた結果、それに対する私なりの答が出た。延いては、
小学校の国語教科書で、嘘かも知れない賢治終焉前日の面談をあたかも事実であるかの如くに教えている現実が今でもあるが、純真な子どもたちを騙している虞れのあるこのようなことをこのまま続けていていいのですか。もう止めていただきたい。
という課題があることを知ったので、 『校本宮澤賢治全集』には幾つかの杜撰な点があるから、とりわけ未来の子どもたちのために検証をし直し、どうかそれらの解消をしていただきたい。
と世に訴えたいという想いがふつふつと沸き起こってきたことが、今回の拙著出版の最大の理由である。しかしながら、数多おられる才気煥発・博覧強記の宮澤賢治研究者の方々の論考等を何度も目にしてきているので、非才な私にはなおさらにその追究は無謀なことだから諦めようかなという考えが何度か過った。……のだが、方法論としては次のようなことを心掛ければ非才な私でもなんとかなりそうだと直感した。
まず、周知のようにデカルトは『方法序説』の中で、
きわめてゆっくりと歩む人でも、つねにまっすぐな道をたどるなら、走りながらも道をそれてしまう人よりも、はるかに前進することができる。
と述べていることを私は思い出した。同時に、石井洋二郎氏が、 あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること
という、研究における方法論を教えてくれていることもである。すると、この基本を心掛けて取り組めばなんとかなるだろうという根拠のない自信が生まれ、歩き出すことにした。
そして歩いていると、ある著名な賢治研究者が私(鈴木守)の研究に関して、私の性格がおかしい(偏屈という意味?)から、その研究結果を受け容れがたいと言っているということを知った。まあ、人間的に至らない点が多々あるはずの私だからおかしいかも知れないが、研究内容やその結果と私の性格とは関係がないはずである。おかしいと仰るのであれば、そもそも、私の研究は基本的には「仮説検証型」研究ですから、たったこれだけで十分です。私の検証結果に対してこのような反例があると、たった一つの反例を突きつけていただけば、私は素直に引き下がります。間違っていましたと。
そうして粘り強く歩き続けていたならば、私にも自分なりの賢治研究が出来た。しかも、それらは従前の定説や通説に鑑みれば、荒唐無稽だと嗤われそうなものが多かったのだが、そのような私の研究結果について、入沢康夫氏や大内秀明氏そして森義真氏からの支持もあるので、私はその研究結果に対して自信を増している。ちなみに、私が検証出来た仮説に対して、現時点で反例を突きつけて下さった方はまだ誰一人いない。
そこで、私が今までに辿り着けた事柄を述べたのが、この拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』(鈴木 守著、録繙堂出版、1,000円(税込み))であり、その目次は下掲のとおりである。

現在、岩手県内の書店で販売されております。
なお、岩手県外にお住まいの方も含め、本書の購入をご希望の場合は葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として1,000円分(送料無料)の切手を送って下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます