地元の人でも、余程歴史好きか物好きで無い限りよくは知らないであろう場所が、
ようやく日の目を見た。
2013年7月26日、皇太子殿下が岡山行啓の折この場所に立ち寄られた。
皇太子が水に関する研究をされている事と、明治18年頃この地を御幸された明治
天皇繋がりと言うことだ。

その場所は、「倉安川吉井水門」(県指定史跡)である。
倉安川と言うのは、江戸時代の岡山藩主・池田光政が家臣の津田永忠に命じて
造らせた吉井川と旭川を結ぶ幅約7m、延長約20キロにも及ぶ水路で、延宝年間
にたった1年で完成を見ている。

この川は南部に開発された新田への灌漑用水と、岡山城下へ年貢米等を運ぶ
高瀬舟の運河としての二つの機能を持っていた。
また藩主が参勤交代の帰途、この水路を使い岡山城に帰ったと言う記録も残され
ていると言う。

最大の難関は、二つの川の標高が異なることであった。
県の東部を流れる吉井川の標高は5.7m、中央部を流れる旭川の標高は0.6mと、
僅かその差は5mほどであるが、船を通すためには水門を作る必要が有った。
そのため、吉井川側に造られたのが、「倉安川吉井水門」である。

吉井川の堤防側には「一の水門」を設け倉安川側に「二の水門」を設け、その間に
「高瀬廻し」と呼ばれる船溜まりを設け、この二つの門の開閉により水位の調節を行
ったのである。

当時の人々が僅かな標高差を把握し、現在「閘門式(こうもんしき)」と言われる
水位調整の仕組みを知っていたことは土木技術の高さを窺い知ることが出来る。
水門は自然の岩盤を利用して、花崗岩などの切り石を組み上げた堅固な造りで、
川と同様320年を経た今もほぼそのまま残されている。(続)

デスティネーションキャンペーン
晴れの国 おかやま 観光情報はこちら

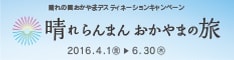

 にほんブログ村
にほんブログ村
ようやく日の目を見た。
2013年7月26日、皇太子殿下が岡山行啓の折この場所に立ち寄られた。
皇太子が水に関する研究をされている事と、明治18年頃この地を御幸された明治
天皇繋がりと言うことだ。

その場所は、「倉安川吉井水門」(県指定史跡)である。
倉安川と言うのは、江戸時代の岡山藩主・池田光政が家臣の津田永忠に命じて
造らせた吉井川と旭川を結ぶ幅約7m、延長約20キロにも及ぶ水路で、延宝年間
にたった1年で完成を見ている。

この川は南部に開発された新田への灌漑用水と、岡山城下へ年貢米等を運ぶ
高瀬舟の運河としての二つの機能を持っていた。
また藩主が参勤交代の帰途、この水路を使い岡山城に帰ったと言う記録も残され
ていると言う。

最大の難関は、二つの川の標高が異なることであった。
県の東部を流れる吉井川の標高は5.7m、中央部を流れる旭川の標高は0.6mと、
僅かその差は5mほどであるが、船を通すためには水門を作る必要が有った。
そのため、吉井川側に造られたのが、「倉安川吉井水門」である。

吉井川の堤防側には「一の水門」を設け倉安川側に「二の水門」を設け、その間に
「高瀬廻し」と呼ばれる船溜まりを設け、この二つの門の開閉により水位の調節を行
ったのである。

当時の人々が僅かな標高差を把握し、現在「閘門式(こうもんしき)」と言われる
水位調整の仕組みを知っていたことは土木技術の高さを窺い知ることが出来る。
水門は自然の岩盤を利用して、花崗岩などの切り石を組み上げた堅固な造りで、
川と同様320年を経た今もほぼそのまま残されている。(続)

デスティネーションキャンペーン
晴れの国 おかやま 観光情報はこちら

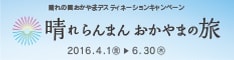





























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます