*****大門口蔦屋*****
蔦屋刊の喜三二と春町の草双紙以前に、蔦重が新吉原大門口(現在の台東区千束辺り)の店で細見の他に黄表紙の刊行に進出したのが1780年(安永9年)で、3年後に日本橋通油町へ移転する前に出版した、初期蔦屋刊草双紙を先に紹介したいと思います。
 啌多雁取帳(うそしつかりがんとりちょう)
啌多雁取帳(うそしつかりがんとりちょう)
1783年(天明3年)出版された草双紙の表紙です。タイトルの下に蔦重のトレードマーク富士山形に蔦の葉が印刷されてあり、その両脇に「大門口 蔦屋」と記してあります。婀娜な姐さんの掌に小さな男がのっている図ですが、絵を担当しているのは忍岡哥麿(後の喜多川歌麿)で、所謂「大首絵」と呼ばれる絵です。これは歌麿の黄表紙デビュー2作めにあたり、歌麿という画号でのデビュー作だということです。
作家は奈蒔野馬乎人(なまけのばかひと)というふざけたペンネームをつけてますが、この人は色々な号をもっていて、志水燕十(しみずえんじゅう)という戯名が有名です。詳細伝が未詳な人物ですが、鈴木庄之助という幕府御家人で1781年(安永末年)から戯作界に登場し活躍した人となっています。更に、蔦屋に出入りしているうちに蔦重と義兄弟の契りを交わした唐来参和(とうらいさんな)と同一人物らしいといわれています。江戸時代は一人に号がいっぱいあって、資料に明確に残っていない人物は写楽のように謎の人物となってしまい困ります。
さて、『啌多雁取帳』のお話ですが、小人に見える男が主人公で、このサイズが人間サイズ。女は大人(だいじん)国の人間です。金十が知人から「氷の張った池では雁が簡単に捕まえられる。雁の足が氷で固まって動けないので手で引き抜いて腰紐にひっかけて取っていたら、氷が解けた雁が飛び立って自分も一緒に空へ舞い上がった。そうして落っこちたところが大人国だった」という話を聞いて、自分もそのようにやってみた。そして大人国へ行き、大人たちに玩ばれる。男は桶屋だったので、壊れた手盥を修理してくれと頼まれが、あまりの大きさに桶の箍(たが)に空高く弾き飛ばされて、江戸の自分の家の前に墜落し、めでたく正月を迎えた。という寓話。
 奈蒔野馬乎人による叙(前書き)
奈蒔野馬乎人による叙(前書き)
さて、この本で私が着目したのは、上の「叙」です。○○印をつけた箇所は「蔦十」と書いてあります。「重」でないのは、複雑なので彫師が当て字で彫ったためでしょう。(こういう当て字は沢山あります)そもそもこのお話の原案は蔦重で、燕十は彼の求めに応じて書いたと明記しています。燕十が参和であるなら、義兄弟になるほど親しい友人の戯作をお膳立てし、新進気鋭の絵師・歌麿(彼も蔦重と縁戚関係にあるといわれている。蔦重は幼い頃喜多川家<蔦屋は屋号>に養子に入っている。歌麿の姓は喜多川。因みに蔦屋は吉原の茶屋で本家の他数件蔦屋がある。)をデビューさせていたという事がわかります。
でもこの話、ロビンソン・クルーソーみたい、、、
蔦屋刊の喜三二と春町の草双紙以前に、蔦重が新吉原大門口(現在の台東区千束辺り)の店で細見の他に黄表紙の刊行に進出したのが1780年(安永9年)で、3年後に日本橋通油町へ移転する前に出版した、初期蔦屋刊草双紙を先に紹介したいと思います。
 啌多雁取帳(うそしつかりがんとりちょう)
啌多雁取帳(うそしつかりがんとりちょう)1783年(天明3年)出版された草双紙の表紙です。タイトルの下に蔦重のトレードマーク富士山形に蔦の葉が印刷されてあり、その両脇に「大門口 蔦屋」と記してあります。婀娜な姐さんの掌に小さな男がのっている図ですが、絵を担当しているのは忍岡哥麿(後の喜多川歌麿)で、所謂「大首絵」と呼ばれる絵です。これは歌麿の黄表紙デビュー2作めにあたり、歌麿という画号でのデビュー作だということです。
作家は奈蒔野馬乎人(なまけのばかひと)というふざけたペンネームをつけてますが、この人は色々な号をもっていて、志水燕十(しみずえんじゅう)という戯名が有名です。詳細伝が未詳な人物ですが、鈴木庄之助という幕府御家人で1781年(安永末年)から戯作界に登場し活躍した人となっています。更に、蔦屋に出入りしているうちに蔦重と義兄弟の契りを交わした唐来参和(とうらいさんな)と同一人物らしいといわれています。江戸時代は一人に号がいっぱいあって、資料に明確に残っていない人物は写楽のように謎の人物となってしまい困ります。
さて、『啌多雁取帳』のお話ですが、小人に見える男が主人公で、このサイズが人間サイズ。女は大人(だいじん)国の人間です。金十が知人から「氷の張った池では雁が簡単に捕まえられる。雁の足が氷で固まって動けないので手で引き抜いて腰紐にひっかけて取っていたら、氷が解けた雁が飛び立って自分も一緒に空へ舞い上がった。そうして落っこちたところが大人国だった」という話を聞いて、自分もそのようにやってみた。そして大人国へ行き、大人たちに玩ばれる。男は桶屋だったので、壊れた手盥を修理してくれと頼まれが、あまりの大きさに桶の箍(たが)に空高く弾き飛ばされて、江戸の自分の家の前に墜落し、めでたく正月を迎えた。という寓話。
 奈蒔野馬乎人による叙(前書き)
奈蒔野馬乎人による叙(前書き)さて、この本で私が着目したのは、上の「叙」です。○○印をつけた箇所は「蔦十」と書いてあります。「重」でないのは、複雑なので彫師が当て字で彫ったためでしょう。(こういう当て字は沢山あります)そもそもこのお話の原案は蔦重で、燕十は彼の求めに応じて書いたと明記しています。燕十が参和であるなら、義兄弟になるほど親しい友人の戯作をお膳立てし、新進気鋭の絵師・歌麿(彼も蔦重と縁戚関係にあるといわれている。蔦重は幼い頃喜多川家<蔦屋は屋号>に養子に入っている。歌麿の姓は喜多川。因みに蔦屋は吉原の茶屋で本家の他数件蔦屋がある。)をデビューさせていたという事がわかります。
でもこの話、ロビンソン・クルーソーみたい、、、














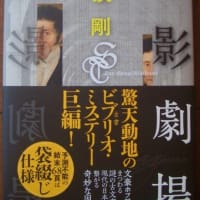

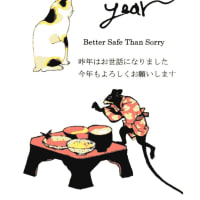
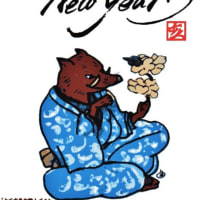
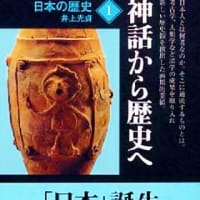






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます