
エレキテル実験図 北尾政美画
1787年刊行 森島中良著『紅毛雑話』より
1787年刊行 森島中良著『紅毛雑話』より
本草学と儒学を学び、長崎への遊学、量程器・磁針器を作り、藩を飛び出して江戸で物産会を成功させ、日本で初めて石綿を発見し火浣布を織り、壊れた摩擦起電機を復元させるなど、江戸後期の殖産政策に大いに貢献しようとした源内先生。
お堅い方面だけでなく、浄瑠璃本や戯作本を書いたり、売れない作家や商売人の手助けをしてやったり、庶民や文芸のためにも尽力した源内先生。
江戸で一世を風靡した有名人・源内先生が、どうして人を殺傷して牢獄へ入れられてしまったのでしょうか。
 ある日、源内先生は某侯の屋敷に関わる事で、大工2人と酒を飲んでいました。何時しか皆泥酔して眠ってしまいした。尿意をもよおして起きた源内先生は、厠から戻って懐に入れておいた設計図を確かめようと手を入れましたが、設計図がありません。辺りを探しましたが一向に見つからないので、寝ていた大工を起こして問い詰めるも、大工は心当たりない、と言います。激情した源内先生は、傍らの刀を取り、彼らに斬りつけました。1人は逃げて命は助かりましたが、もう一人は死んでしまいました。立ち尽くす源内先生の足元に、件の設計図が落ちました。源内先生、厠で設計図を落とさないように帯に挟んでいたのを忘れていたのでした。我に返った源内先生は、牢獄へ入れられ、獄中で病死してしまいました。
ある日、源内先生は某侯の屋敷に関わる事で、大工2人と酒を飲んでいました。何時しか皆泥酔して眠ってしまいした。尿意をもよおして起きた源内先生は、厠から戻って懐に入れておいた設計図を確かめようと手を入れましたが、設計図がありません。辺りを探しましたが一向に見つからないので、寝ていた大工を起こして問い詰めるも、大工は心当たりない、と言います。激情した源内先生は、傍らの刀を取り、彼らに斬りつけました。1人は逃げて命は助かりましたが、もう一人は死んでしまいました。立ち尽くす源内先生の足元に、件の設計図が落ちました。源内先生、厠で設計図を落とさないように帯に挟んでいたのを忘れていたのでした。我に返った源内先生は、牢獄へ入れられ、獄中で病死してしまいました。というのが、どこで知ったのか、私が記憶している顛末です。たぶんテレビの歴史番組か何かの情報でしょう。勘違いで刃傷事件を起こすなんて正気の沙汰じゃない、と思ったら、源内先生ほんとうに気が違っていたそうです。「時代の寵児」の末路がこれか…と素直に事実だと思っていました。
しかし、普通に考えても納得いかない事件です。最近知った情報では、某侯は田沼意次だったとか、何やら陰謀めいた臭いもします。城福 勇氏の『平賀源内』にも要約して書かれてありましたが、参考文献に挙げられていた水谷弓彦(水谷不倒:1858‐1943年名古屋出身の国文学者・小説家。近世文学研究の先駆的人物。)の『平賀源内』第十二末路を読んでみました。
源内研究はかなり早くからされていて、事件について書かれた説もいくつかありますが、大きく分けて2説になるそうです。水谷不倒が引用したのは、曲亭馬琴の『作者部類』に紹介された高松藩家老・木村黙老が記した『聞まゝの記』に書いてあった説の大意と、同じく讃州の儒学者・片山沖堂(ちゅうどう)の『平賀源内伝』の一節。これは、私が記憶していた「某侯の普請が発端」で起きてしまったとするもの(細かい違いはありましたが)。片山沖堂は、黙老の説に「某侯はあるいは田沼意次」と注釈を加えていました。
『作者部類』には馬琴自身の説も書いてあり、平賀鳩渓(源内の画号)の事件の風聞が騒がしかった頃、馬琴は13歳の冬だったと書いています。馬琴が聞いた当時の街談巷説は、員 正恭(まさやす)という人が著した『讃海(たんかい)』や『鳩渓遺事』(著者・鈴木洪←忄共 は南畝の友人だとか)に掲載されている「神田久右衛門町の代地録の写し」に記された大意と、ほぼ同じ内容です。
源内が人を殺害した時の記録だという「代地録の写」に因れば、以下のような筋になります。
 安永8年11月20日夜、半兵衛店讃州の浪人平賀源内宅へ、秋田屋久左衛門の倅・久五郎と松本十郎兵衛家中・丈右衛門が宿泊していたが、翌日子細はわからないが、源内が刀を抜いて突然両人へ手傷を負わせた。丈右衛門は右手の親指を斬られたが裏へ逃げ出ることができた。久五郎は頭の頂天に一刀をあびせられ、表に逃げたが追って来た源内に組み伏せられた。源内が止めを刺そうとした時、どうしたわけか仰向けに倒れたので、その隙に久五郎は辛うじて逃げて長右衛門という者の家の前で休んでいた。長右衛門が中に入れて介抱したが、死んでしまった。22日、入牢。安永9年2月牢死。
安永8年11月20日夜、半兵衛店讃州の浪人平賀源内宅へ、秋田屋久左衛門の倅・久五郎と松本十郎兵衛家中・丈右衛門が宿泊していたが、翌日子細はわからないが、源内が刀を抜いて突然両人へ手傷を負わせた。丈右衛門は右手の親指を斬られたが裏へ逃げ出ることができた。久五郎は頭の頂天に一刀をあびせられ、表に逃げたが追って来た源内に組み伏せられた。源内が止めを刺そうとした時、どうしたわけか仰向けに倒れたので、その隙に久五郎は辛うじて逃げて長右衛門という者の家の前で休んでいた。長右衛門が中に入れて介抱したが、死んでしまった。22日、入牢。安永9年2月牢死。これには事件の原因が書いてないのですが、馬琴が聞いた噂では、「当時の源内は親しい友人にさえ著述の稿本を見ることを許していなかった。そこへ、常に親しくしていた米屋の息子何某が源内宅へ来たが、留守だったため、待っている間に机に置いてあった稿本を何となく見ていた。帰宅した源内がそのことに激怒し、詫びるのも聞かず刀を抜いてしたたか斬りつけた。息子何某は逃げたけれど、治療の甲斐なく死んでしまった。」という次第だったようです。
殺した原因は様々あったそうですが、久五郎は米屋の倅に相違なく、水谷不倒も「大工を傷つけたる前説にあらざることいよいよ根柢固し」と述べています。となれば、大工や設計図(書類)という風説はどこからきたものなのでしょう。
水谷不倒は、この説は源内の出身地で信じられているものなので、藩士(例え足軽出身の下級武士でも)が藩の名を汚すような事件を起こした事実を、さも源内と懇意だった田沼意次との関係に起因していると思わせるように言われていた風説の方を事実と信じて記したのだ、と記述しています。
とはいえ、伝聞の伝聞は不確かなもので、水谷不倒の持論では「源内は一時は田沼侯に寵遇されたが、余りにも才能があるために反って後には忌まれ、遂には疎外されたのを遺憾に思い、絶望の極みで失心したと判断したのだろう。」と述べ、「しかれどもこの問題は、今容易に決定しがたかるべし。」としています。
源内の獄死についても色々な説があり、「入牢を知った田沼侯が一計を案じ、自分の領地遠州相良に匿った。田沼失脚後隠れる所がなくなった源内は出羽庄内に逃げて生涯を終えた。」という一説もあったそうです。庄内には石碑があって、そこに彫ってある文字を調べたら、源内作の浄瑠璃の文句だったとか。そして、これは源内の墓ではないということから、源内は蝦夷へ行った、そこに墓がある、80何歳の源内を見たという人がいる、等々尾ひれが付いていったそうです。
しかしこれらは、源内の親友だった杉田玄白が否定していました。
この時代の法律では、罪人の死体は親類へ引き渡されないので、着ていた衣類や履物を役人に貰い受け、それらを棺に納めて葬式をあげたそうで、玄白は私財を投じて源内の墓を建て、碑銘を撰して墓石に刻んだ、というのが事実だったと水谷不倒は書いてます。
私が記憶していた情報は、色んな説がごちゃ混ぜになった話というのがわかりました。そもそも一番信頼性が高い「代地録の写し」の内容に、被害者が斬られる前に何をしていたのか明白にされていないのが腑に落ちません。被害者が米屋だろうが大工だろうが、源内を激怒させた「何かをした、或は言った」はずで、それが直接の原因として書かれてもいいと思うのですが。














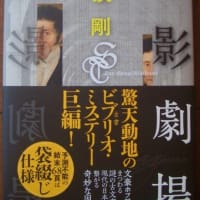

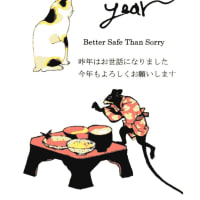
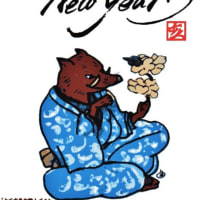
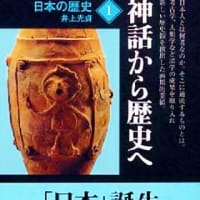






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます