面白い構成の小説である。
まるで論文のように、第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章、第Ⅳ章と区分され、それぞれにタイトルが付けれられている。もちろん内容は紛れもなく小説であるし、その表現も論文調のものではけっしてない。
そのそれぞれの章が、独立した短編小説として読めるようになっているが、かといってまったく別の話ではない。いずれも、有馬章という新聞記者が主人公で、時系列は若干行ったり来たりするが、おおむね彼と、そして時に、彼の周辺の人物の物語である。
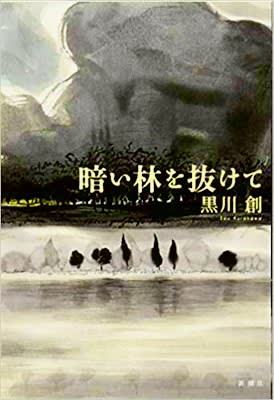
第Ⅰ章冒頭での、主人公の学生時代のガールフレンドが、彼女の視点で語るエピソードが、第Ⅳ章の末尾近くの主人公の側からの回想シーンとしてリフレインされるという円環構造もみてとれるのだが、それは同時にこの小説全体を貫く(と私が思っているだけだが)家族の問題(それはしばしばもっとも近い他者の問題として語られる)、そして、はじめは自分とは距離をもっていたのだが、次第に自分のものとして自覚される死の問題を描く行程でもある。
こんなふうにいうと、なんか重っ苦しい小説のようだが決してそうではない。ストーリーそのものの展開が面白いし、全体を読み通すと、ああ、そうだったのかと主人公のあゆみとそれを取り巻く関係性のようなものがしだいに明らかになってくる過程も謎解き的な意味で面白い。
もうひとつ、この小説を面白くし、その厚みを増しているのは、そこに挿入された多方面にわたる豊富なエピソードの数々である。
最初の言語聴覚士の話は、後に出てくるのALS(筋萎縮性即索硬化症)やホーキング博士の話に繋がるし、香月泰男を思わせるシベリア帰りの画家(時代的にやや違うかも)の話も面白い。
世界大戦の話にも意表を突かれた。第一次世界大戦があって、第二次があったのではなく、逆に、第二次があって、はじめて、あれは第一次だったといわれるようになったというのだが、リアルな歴史の世界はいつもそうなのだろう。フランス革命に参加した人はフランス革命をしようとしたわけではないように。
湯川秀樹と京大物理学研究室の原爆開発研究の過程も面白いが、その湯川が、研究の合間にクラシックの演奏会にでかけ、リストの曲をエタ・ハーリヒ=シュナイダーという女性の演奏で聴くという話がある。その彼女の話もめっぽう面白い。
彼女は、一応ドイツ政府の使節団の一行として1941年に来日するのだが、実際には反ナチを心情とする亡命同然の来日で、そのままドイツへは帰らなかった。

彼女の専門はチェンバロと音楽理論で著作もあるが、日本では、当時はまだあまり知られていなかったチェンバロの普及に努め、各地で、チェンバロやピアノの演奏会を行った。湯川が聴いたのもそのひとつだった。以下は、記録に残るエタの演奏。
https://www.youtube.com/watch?v=kpA_5sZi90Y
https://www.youtube.com/channel/UCIAvrGaHC63uGld64pkMLxw
彼女はまた、かのゾルゲ事件のリヒャルト・ゾルゲとも親交を結ぶこととなり、どうやらその関係は友人の域を越えていたようだ。
最後のエピソードは、滋賀県は朽木村(現・高島市)の高厳山興聖寺を巡る話である。
平安中期、藤原道長の娘、威子と後一条天皇の間にできた第三子の王子が、何らかの事情、おそらく本人の何らかの欠陥により、この地に流され、そこで生涯を終えたという話である。
それだけなら、遠い昔の言い伝えということになろうが、この地を、平成天皇の第二王子・礼宮(現・秋篠宮)が訪れ、住職にある質問をしたというのだ。18歳の折のことだという。何を質問したのかはあえていうまい。

これら多彩なエピソードを提供し、小説は終わる。その多様さは、作家・黒川創の知的関心の在り処とその豊かさを示して余りあるものがある。
それを読むだけでもこの小説は面白いが、それを貫く、家族・死をみつめる彼の視線が通奏低音のように絶え間ないところに、この小説が多くの内容を含みながら、散漫になることなく、ある重力をもって迫ってくる所以があるように思う。
なお、余談だが、もう10年以上前、黒川氏が私が参加するある会(もくの会)にゲストとしてやってきて、二次会まで付き合ってくれ、大いに飲みかつ歓談したことがある。
彼は、その日のうちに京都へ帰るということで新幹線に乗ったのだが(その折、私は名古屋駅まで同行)、列車の揺れにつれ爆睡し、気づいたら、無情にも列車は京都を過ぎて進行しつつあったという。

















