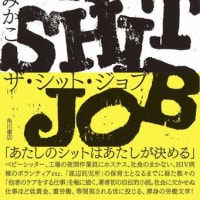加藤典洋『9条入門』(創元社、2019年)
 内田樹がすぐにでもどこやらをポチるなり本屋へ直行するなりして購入して一読せよとツイッターで書いていたので、そんなに面白い本なのかと思い、図書館で借りてきた。
内田樹がすぐにでもどこやらをポチるなり本屋へ直行するなりして購入して一読せよとツイッターで書いていたので、そんなに面白い本なのかと思い、図書館で借りてきた。
びっくらこいた、というのが正直な感想だ。まさか憲法9条の戦争放棄宣言がマッカーサーの大統領になりたいという野望から出たものだったとは。
1948年の大統領選挙で勝利して、アメリカ大統領になりたい。
そのためには48年までに占領軍司令官として占領政策を速やかに完了して凱旋しなければならない。
天皇が敗戦の宣言を行うことで数百万の兵士が速やかに武装蜂起をしてほとんどゲリラ戦もなかったことを考えると、日本の占領統治政策の実行には天皇の存在が不可欠である。
しかし極東委員会の諸国の多くは天皇の処分(死刑とか天皇制の廃止)を主張するところがほとんどであり、天皇存続で彼らを納得させるためには、日本が天皇のもとに再び軍事国家とならないとような憲法が必要である。
そこで憲法1条の天皇の象徴化と9条の「特別な戦争放棄」という、今後国連が担っていくであろう世界平和の理念ともいうべき姿を日本に体現させることによって、それが可能になる。
著者によれば、日本の側にも、当時の共産党の野坂参三でさえも「自衛権は放棄すべきでない」と主張したにもかかわらず、首相の吉田茂をはじめとする閣僚たちが声をそろえて「自衛権の放棄」を主張した裏には、マッカーサーの主張に声を合わえることによって、天皇が東京裁判で責任を問われないようにする必要があったというのだ。
いったい憲法9条の出生の秘密を知ったうえで私たちはどうしたらいいのだろうか。
おまけにその後の憲法を国民に周知させる運動が、占領者にすりよった東大法学部の教授たちによって進められていたという事実まで明らかにされている。
戦争に破れた時の国民の「二度と戦争はいやだ」という思いは、こうして幾重にも私物化されてきた。もちろんその最たる姿が日米安保条約によって生じた、アメリカ軍の一翼にすぎない自衛隊の創設と巨大化である。
 内田樹がすぐにでもどこやらをポチるなり本屋へ直行するなりして購入して一読せよとツイッターで書いていたので、そんなに面白い本なのかと思い、図書館で借りてきた。
内田樹がすぐにでもどこやらをポチるなり本屋へ直行するなりして購入して一読せよとツイッターで書いていたので、そんなに面白い本なのかと思い、図書館で借りてきた。びっくらこいた、というのが正直な感想だ。まさか憲法9条の戦争放棄宣言がマッカーサーの大統領になりたいという野望から出たものだったとは。
1948年の大統領選挙で勝利して、アメリカ大統領になりたい。
そのためには48年までに占領軍司令官として占領政策を速やかに完了して凱旋しなければならない。
天皇が敗戦の宣言を行うことで数百万の兵士が速やかに武装蜂起をしてほとんどゲリラ戦もなかったことを考えると、日本の占領統治政策の実行には天皇の存在が不可欠である。
しかし極東委員会の諸国の多くは天皇の処分(死刑とか天皇制の廃止)を主張するところがほとんどであり、天皇存続で彼らを納得させるためには、日本が天皇のもとに再び軍事国家とならないとような憲法が必要である。
そこで憲法1条の天皇の象徴化と9条の「特別な戦争放棄」という、今後国連が担っていくであろう世界平和の理念ともいうべき姿を日本に体現させることによって、それが可能になる。
著者によれば、日本の側にも、当時の共産党の野坂参三でさえも「自衛権は放棄すべきでない」と主張したにもかかわらず、首相の吉田茂をはじめとする閣僚たちが声をそろえて「自衛権の放棄」を主張した裏には、マッカーサーの主張に声を合わえることによって、天皇が東京裁判で責任を問われないようにする必要があったというのだ。
いったい憲法9条の出生の秘密を知ったうえで私たちはどうしたらいいのだろうか。
おまけにその後の憲法を国民に周知させる運動が、占領者にすりよった東大法学部の教授たちによって進められていたという事実まで明らかにされている。
戦争に破れた時の国民の「二度と戦争はいやだ」という思いは、こうして幾重にも私物化されてきた。もちろんその最たる姿が日米安保条約によって生じた、アメリカ軍の一翼にすぎない自衛隊の創設と巨大化である。