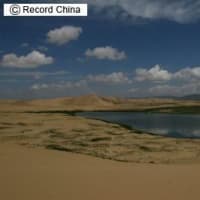■ほんの1年ほど前まで「デカップリング」理論なるものが経済雑誌や新聞紙上に踊っておりました。昨年度の流行語大賞に選ばれてもよいくらい頻繁に使われていた印象がありますが、流行した期間が短かったためにノミネートもされず、そして、金融危機があっと言う間に世界中に広がってしまった今にして思えば、誰がも「ウソツキ!」と罵りたくなるような言葉でありましたなあ。改めて「デカップリング」理論を確認してみたくなったのには理由があるのですが、それは後述するとして、みずほインベスターズ証券のシニアストラテジストをしている佐藤政俊氏が昨年の12月3日『日経CNBCジャーナル』に寄稿した文章から抜粋して、当時のことを思い出してみましょう。
……最近、経済関係でよく使われる用語に「デカップリング(非連動性)」がある。これは、米国経済が減速しても中国等の新興諸国や欧州の成長に支えられ、世界経済の拡大が継続する、といったことを指して用いられる。
■この言葉を信じて新興諸国への投資や投機に励んでいた人や企業も多かったはずです。サブプライム・ローンを混ぜ込んだ上に、これまた聞きたくもない「レバレッジ」を効かせて膨らますだけ膨らました金融商品を世界中に売りつけて荒稼ぎしていた連中は、この「デカップリング」を最大限に利用して自分たちの稼ぎ自体にレバレッジを掛けていたようなものです。
「デカップリング」は、サブプライム問題の米国実体経済への波及が現実のものとなりつつある中、世界の株式市場関係者の心のよりどころとなっており、10月末頃まで、アジア等新興諸国市場に世界のマネーが流入、過去最高値を更新する市場が相次いだ。IMFが10月17日に発表した世界経済見通しの中で、「中国・インド・ロシア3カ国が過去1年間の世界の成長の半分を占めた」といった分析を示したが、こうした分析も後押ししたものと思われる。
■今となってはIMFの手に負えないほど深刻な事態が進んでいるのですから、たった1年で世界が激変したことを実感しますなあ。新興3箇国の頭文字を取って「ブリックス」などと持て囃していたのも同じ頃でした。
一方、この「デカップリング」に関して慎重な見方もある。米国経済の悪化は新興諸国からの米国への輸出を減速させ新興諸国の景気に悪影響を与える、という考え方だ。11月初から、アジアの株価は調整色を強め、東京市場でも海運、鉄鋼、商社等、新興諸国の経済成長で恩恵を受けるセクターの株価が急落した。株式市場では、「デカップリング」に対する懐疑が台頭してきた。
■まあ、この文章が書かれた頃に素早く対処することが出来た人は、投資分を高値で売り抜けて大儲けしたのでしょうが、もう少しもう少しと欲を掻いてしまった人は大損害を被ってしまいました。
実際は、米国経済の悪化度合いによって、新興諸国への影響度も異なるはずで、「デカップリング」の成否を簡単に結論付けるのは難しい。株式相場は、「デカップリング」に対する見解と株価が相互に共鳴し、楽観と悲観の間を揺れ動いているように思う。2008年相場でも、「デカップリング」は重要な論点となるだろう。過度に楽観、悲観することなく、世界経済を見極めていく冷静さが必要な場面である。
■専門家の文章らしく「穏当な」締め括りになっていますが、飽くまでも証券会社の人が書いたものなので、やんわりと株式投資を推奨しているのが分かります。間も無く「2008年相場」が終わる時期になって振り返れば、「デカップリング」は重要な論点になどならないまま紙くずのように投げ捨てられてしまっております。
■最近の新聞を見ますと重要な話題には「両論併記」の形式をとる紙面づくりが広がっているようです。それも「自己責任」という言葉が流行した結果なのかも知れませんが、読者に必要な情報を漏れなく伝えた上で自己判断を任せるのは良心的と申せましょう。でも、時々意図的に情報が操作されていたり、「両論」が単なる二つの意見の併記でしかない場合もあるようです。情報操作と言えば、今年の秋口には「解散総選挙」の日程を得意満面に書き立てていた新聞がありましたなあ。
……最近、経済関係でよく使われる用語に「デカップリング(非連動性)」がある。これは、米国経済が減速しても中国等の新興諸国や欧州の成長に支えられ、世界経済の拡大が継続する、といったことを指して用いられる。
■この言葉を信じて新興諸国への投資や投機に励んでいた人や企業も多かったはずです。サブプライム・ローンを混ぜ込んだ上に、これまた聞きたくもない「レバレッジ」を効かせて膨らますだけ膨らました金融商品を世界中に売りつけて荒稼ぎしていた連中は、この「デカップリング」を最大限に利用して自分たちの稼ぎ自体にレバレッジを掛けていたようなものです。
「デカップリング」は、サブプライム問題の米国実体経済への波及が現実のものとなりつつある中、世界の株式市場関係者の心のよりどころとなっており、10月末頃まで、アジア等新興諸国市場に世界のマネーが流入、過去最高値を更新する市場が相次いだ。IMFが10月17日に発表した世界経済見通しの中で、「中国・インド・ロシア3カ国が過去1年間の世界の成長の半分を占めた」といった分析を示したが、こうした分析も後押ししたものと思われる。
■今となってはIMFの手に負えないほど深刻な事態が進んでいるのですから、たった1年で世界が激変したことを実感しますなあ。新興3箇国の頭文字を取って「ブリックス」などと持て囃していたのも同じ頃でした。
一方、この「デカップリング」に関して慎重な見方もある。米国経済の悪化は新興諸国からの米国への輸出を減速させ新興諸国の景気に悪影響を与える、という考え方だ。11月初から、アジアの株価は調整色を強め、東京市場でも海運、鉄鋼、商社等、新興諸国の経済成長で恩恵を受けるセクターの株価が急落した。株式市場では、「デカップリング」に対する懐疑が台頭してきた。
■まあ、この文章が書かれた頃に素早く対処することが出来た人は、投資分を高値で売り抜けて大儲けしたのでしょうが、もう少しもう少しと欲を掻いてしまった人は大損害を被ってしまいました。
実際は、米国経済の悪化度合いによって、新興諸国への影響度も異なるはずで、「デカップリング」の成否を簡単に結論付けるのは難しい。株式相場は、「デカップリング」に対する見解と株価が相互に共鳴し、楽観と悲観の間を揺れ動いているように思う。2008年相場でも、「デカップリング」は重要な論点となるだろう。過度に楽観、悲観することなく、世界経済を見極めていく冷静さが必要な場面である。
■専門家の文章らしく「穏当な」締め括りになっていますが、飽くまでも証券会社の人が書いたものなので、やんわりと株式投資を推奨しているのが分かります。間も無く「2008年相場」が終わる時期になって振り返れば、「デカップリング」は重要な論点になどならないまま紙くずのように投げ捨てられてしまっております。
■最近の新聞を見ますと重要な話題には「両論併記」の形式をとる紙面づくりが広がっているようです。それも「自己責任」という言葉が流行した結果なのかも知れませんが、読者に必要な情報を漏れなく伝えた上で自己判断を任せるのは良心的と申せましょう。でも、時々意図的に情報が操作されていたり、「両論」が単なる二つの意見の併記でしかない場合もあるようです。情報操作と言えば、今年の秋口には「解散総選挙」の日程を得意満面に書き立てていた新聞がありましたなあ。