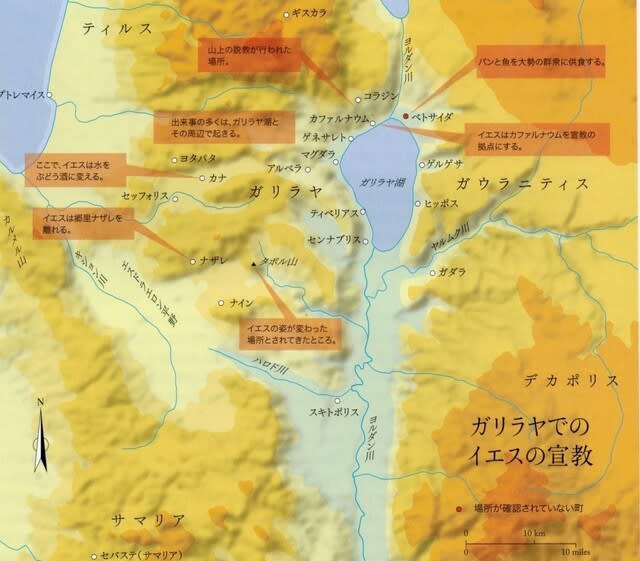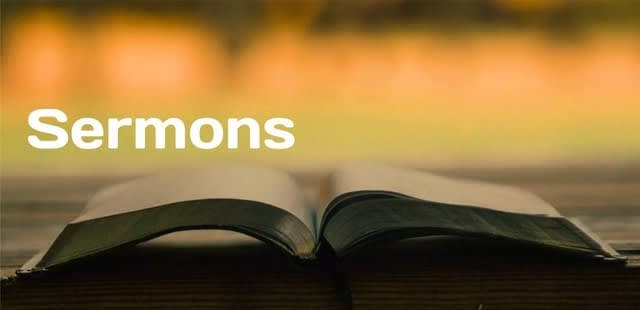説教集 新約聖書の部
マタイによる福音書
1 「東方の占星術の学者たち」 マタイによる福音書2章1~12節 2019/12/28
「東方の占星術の学者たちの礼拝」マタイによる福音書2章1~12節 2018/12/29
「東方の学者たちの来訪」 マタイよる福音書2章1~12節 2017/12/29
「星に導かれた東方の学者たち」 マタイによる福音書2章1~12節 2015/12/27
「東方の学者たちの来訪とヘロデ大王」 マタイによる福音書2章1-18節 2014/12/22
2 「聖家族のエジプト避難」 マタイによる福音書2章13~23節 2016/12/31
「ヘロデ王と神のみ旨に従ったヨセフ」 マタイによる福音書2章13-23節 2017/01/04
3 「イエスの洗礼」 マタイによる福音書3章13~17節 2017/01/04
4 「荒れ野の誘惑」 マタイによる福音書4章1~11節 2017/03/03
「人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きる」 マタイによる福音書4章1~11節 2016/02/13
5 「最初の弟子たち―人間をとる漁師」 マタイによる福音書4章18~25節 2017/01/14
6 「山上の説教―八つの幸いの教え」 マタイによる福音書5章1~12節、17節 2017/02/12
7 「八つの祝福と、地の塩・世の光である信徒」 マタイによる福音書5章17-26節 2019/11/10
8 「律法の完成と隣人との和解」 マタイによる福音書5章17節-26節 2019/11/16
9 「姦淫、離婚、誓いについて」 マタイによる福音書5章27-37節 2019/11/22
10 「あなたの敵を愛しなさい。」 マタイによる福音書5章38-48節 2020/1/11
11 「施しと祈りについてのイエスの教え」 マタイによる福音書6章1~8節 2017/05/21
12 「『主の祈り』とその他の祈り」 マタイによる福音書6章1-18節 2020/1/16
13 「明日のことまで思い悩むな」マタイによる福音書6章19-34節 2020/03/26 2020/1/23
14「求めなさい。そうすれば、与えられる。」 マタイによる福音書7章1-12節 2020/1/31
15「主イエスの言葉を聞いて行う者」マタイによる福音書7章24-29節 2020/2/9
16「悪と戦うキリスト、聖霊によって悪霊を追い出す」 マタイによる福音書12章22~32節 2017/03/12
17「たとえで語るキリスト-種蒔きのたとえ」 マタイによる福音書13章10~17節 2017/02/04
18 「奇跡を行うキリストー湖上を歩く」 マタイによる福音書14章22~36節 2017/02/26
19 「心身の病(やまい)をいやすキリスト」 マタイによる福音書15章21~31節 017/02/19
20 「主の変貌―栄光に輝くキリスト」 マタイによる福音書17章1~13節 2017/03/25
21 「フィリポ・カイサリアでの信仰告白と受難の予告」マタイによる福音書16章13~28節 2017/03/19
22 「十字架の勝利(偉くなりたい者は仕える人に)。」 マタイによる福音書20章20~28節 2017/04/02
23 「新しい神殿」 マタイによる福音書21章12~16節 2017/01/29
24「タラントンのたとえが主張するもの」マタイによる福音書25章14-30節 2020/2/14
25 「十字架への道」 マタイによる福音書27章32~56節 2017/04/09
26 「キリストの復活」 マタイによる福音書28章1~10節 2017/04/16
27 「主の復活顕現」 マタイによる福音書28章11~20節 2017/04/23
28 「キリストの昇天」 マタイによる福音書28章16~20節 2019/05/30
「キリストの昇天の意義」 マタイによる福音書28章16-20節 2015/05/16
マルコによる福音書
1 「イエスの洗礼」 マルコによる福音書1章1~11節 2018/01/14
2 「荒れ野の誘惑と神の国の宣教」 マルコによる福音書1章12~15節 2018/02/16
3 「イエスの最初の弟子たち」 マルコによる福音書1章14~20節 2018/01/20
4 「癒すキリスト」 マルコによる福音書2章1~12節 2018/01/31
5 「悪(霊)と戦うキリスト」 マルコによる福音書3章20~30節 2018/02/23
6 「教えるキリスト」 マルコによる福音書4章1~9節 2018/01/28
7 「奇跡を行うキリスト:突風と湖を静める」 マルコによる福音書4章35~41節 2018/02/10
8 「受難の予告とイエスに従う者」 マルコによる福音書8章27~33節 2018/03/02
9 「高山右近の信仰に学ぶ」 マルコによる福音書8章36-38節 2014/05/18
10 「主の変容とその意義」 マルコによる福音書9章2~10節 2018/03/07
11 「十字架の勝利」 マルコによる福音書10章32~45節 2018/03/18
12 「十字架への道」 マルコによる福音書14章32-42節 2018/03/24
13 「イエスの十字架上の最後の言葉」 マルコによる福音書15章25-37節 2014/04/13
14 「キリストの復活」 マルコによる福音書16章1-8節 2018/03/30
「イエスの復活」 マルコによる福音書16章1-11節 2014/04/21
ルカによる福音書
1 「洗礼のヨハネの父、ザカリアの賛歌」 ルカによる福音書1章67-79節 2014/11/30
2 「受胎告知とマリアの賛歌」 ルカによる福音書1章47-55節 2014/11/30
3 「世を救うキリストの降誕」養老施設でのクリスマス・ミニ礼拝と聖餐式 ルカ2章1-20節 2019/12/25
「世を救うキリストの降誕」 ルカによる福音書2章1~20節 2019/12/20
「クリスマスー世の罪を取り除く神の小羊の誕生」 ルカによる福音書2章1~20節 2018/12/14
「キリストの降誕」 ルカによる福音書2章1~20節 2017/12/24
「キリストの降誕」 ルカによる福音書2章1~20節 2016/12/24
「キリストの降誕」ルカによる福音書2章1~20節 2015/12/19
「真の救い主の誕生」 ルカによる福音書2章1-55節 2014/12/14
「救い主の誕生」 ルカによる福音書2章1-20節 2013/12/24
4 「シメオンの讃歌」 ルカによる福音書2章22-38節 2014/12/28
5 「イエスの洗礼」 ルカによる福音書3章15~22節 2019/01/03
「洗礼のヨハネの出現とイエスの洗礼」 ルカによる福音書3章1-22節 2015/01/18
6 「神殿での少年イエス」 ルカによる福音書2章41~52節 2018/01/06
7 「荒れ野の誘惑」 ルカによる福音書4章1-13節 2019/03/04
「イエスの荒れ野の誘惑」 ルカによる福音書4章1-13節 2015/02/22
8 「宣教の開始ーナザレの会堂で教えるイエス」 ルカによる4章16~30節 2019/01/16
「イエスの宣教開始とナザレの人々の反応」 ルカによる福音書4章14-30節 2015/01/25
9 「最初の弟子たちの召命」 ルカによる福音書5章1~11節 2019/01/12
10 「病を癒すキリスト」 ルカによる福音書5章12-26節 2019/02/21
「イエスの病気の癒しと罪の赦し」 ルカによる福音書5章12-26節 2015/02/01
11 「断食についての問答―新しい時代の到来」 ルカによる福音書5章33~39節 2019/02/02
12 「安息日の主」 ルカによる福音書6章1~11節 2019/02/07
13 「百人隊長の驚くべき信仰」 ルカによる福音書7章1~10節 2019/05/26
14 「教えるキリストー種を蒔く人のたとえ」 ルカによる福音書8章4-15節 2019/02/12
『種を蒔く人のたとえ』 ルカによる福音書8章1-15節 2015/02/08
15 「五千人に食べ物を与えたイエスの奇跡」 ルカによる福音書9章1-17節 2015/02/15
16 「受難の予告」 ルカによる福音書9章18-27節 2019/03/20
「メシアの受難の予告とイエスに従うこと」 ルカによる福音書9章18-27節 2015/03/07
17 「奇跡を行うキリスト」 ルカによる福音書9章10-17節 2019/02/27
18 「イエスの姿が変わる」 ルカによる福音書9章28-36節 2019/03/26
「山上で神の栄光に輝くイエス」 ルカによる福音書9章28-36節 2015/03/15
19「『善きサマリア人』のたとえ」ルカによる福音書10章25-37節 2020/2/19
20 「悪と戦うキリスト」 ルカによる福音書11章14-26節 2019/03/11
「神の指による悪霊追放と神の国の到来」 ルカによる福音書11章14-26節 2015/03/01
21「『愚かな金持』のたとえ」ルカによる福音書12章1-21節 2020/2/28
22「『放蕩息子』のたとえ(二人の息子の父の愛)」ルカによる福音書15章11-32節 2020/3/14
23「『金持ちとラザロ』のたとえ」 ルカによる福音書16章19-31節 2020/3/20
24「『ファリサイ派の人と徴税人』のたとえ」ルカによる福音書18章10-14節 2020/3/6
25「十字架の勝利」 ルカによる福音書20章9~19節 2019/04/03
26「ぶどう園と農夫のたとえ」 ルカによる福音書20章9-19節 2015/03/22
27 「貧しいやもめの献金」 ルカによる21章1~4節 2019/01/25
28「十字架への道―オリーブ山で祈る」 ルカによる福音書22章39~53節 2019/04/12
「ゲッセマネの祈り」 ルカによる福音書22章39-46節 2015/03/29
29 「あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる」 ルカによる福音書23章39-43節 2014/05/25
30 「キリストの復活」 ルカによる福音書24章1-12節 2019/10/10 04/18
「キリストの復活」 ルカによる福音書24章1-12節 2015/04/04
31 「「エマオ途上での主の顕現」 ルカによる福音書24章13~35節 2019/04/27
「エマオへの道でのイエスの顕現」 ルカによる福音書24章13-35節 2015/04/12
32 「弟子たちに現れた復活のイエス」 ルカによる福音書24章36~43節 2019/05/05
「弟子たちに現れた復活のイエス」 ルカによる福音書24章36-49節 2015/04/19
33 「キリストの昇天」 ルカによる福音書24章44~53節 2017/05/27
ヨハネによる福音書
1 「世に遣わされた神の子イエス」 ヨハネによる福音書1章14~18節 2016/01/03
2 「世の罪を取り除く神の子羊」 ヨハネによる福音書1章29~34節 2016/01/10
3 「最初の弟子たちの信仰告白」 ヨハネによる福音書1章35~51節 2016/01/13
4 「病気で苦しむ人を癒すキリスト」ヨハネによる福音書5章1~18節 2016/01/27
5 「奇跡を行うキリスト」ヨハネによる福音書6章1~15節 2016/02/06
6 「わたしは命のパンである 」 ヨハネによる福音書6章34-51節 2015/04/26
7 「主よ、わたしたちはだれのところへ行きましょうか」 ヨハネによる福音書6章60~71節 2016/02/26
8 「わたしのことばにとどまるならば、わたしの弟子である」ヨハネによる福音書8章21~362016/01/24
9 「心の目を開くイエス」 ヨハネによる福音書9章1~7節、35~41節 2016/02/21
10 「真の良い羊飼い」 ヨハネによる福音書10章7~18節 2018/04/16
11 「復活と命の主イエス」 ヨハネによる福音書11章17~27節 2017/05/07
12 「イエスに香油を注いだマリアの信仰」 ヨハネによる福音書12章1~8節 2016/03/06
13 「自分の命を失う者と永遠の命に至る人」 ヨハネによる福音書12章20~28節 2016/03/13
14 「キリストの新しい愛の掟」 ヨハネによる福音書13章31~38節 2018/04/24
15 「道であり、真理であり、命である」ヨハネによる福音書14章1~17節 2016/05/22
16 「聖霊の賜物」 ヨハネによる福音書14章15節~27節 2016/05/15
17 「わたしはまことのぶどうの木」 ヨハネによる福音書15章1~11節 2018/04/28
18 「新しい愛の戒め」 ヨハネによる福音書15章12~17節 2019/05/26
「新しいイエスの戒めー互いに愛し合いなさい」 ヨハネによる福音書15章12-17節2015/05/03
19 「世の苦難に打ち勝つ勝利」 ヨハネによる福音書16章25節~33節 2016/04/30
20 「父のみもとへ行く。聖霊をおくる。」 ヨハネによる福音書16章12~24節 2018/05/05
21 「十字架への道」 ヨハネによる福音書18章1-14節 2016/03/20
22 「マグダラのマリアに現れた復活のイエス」 ヨハネによる福音書20章1~18節 2019/04/18
23 「復活顕現」 ヨハネによる福音書20章19~31節 2018/04/05
「トマスに現れた復活のイエス」 ヨハネによる福音書20章19~31節 2016/04/03
24 「ガリラヤ湖畔で弟子たちに朝食を与えた復活の主」ヨハネによる福音書21章1~14 2016/04/09
25 「主イエスとの愛による永遠の結合関係」 ヨハネによる福音書21章15~25節2016/05/07 『あなたはこの人たち以上にわたしを愛しているか』 ヨハネによる福音書21章15~25 2016/04/17
使徒言行録
1 「キリストの昇天と、私たちが天国に行くことについて」 使徒言行録1章1-13節 2014/06/01
2 「聖霊の賜物ー宣教する教会の誕生」 使徒言行録2章1~11節 2019/06/05
「聖霊の賜物」 使徒言行録2章1~11節 2018/05/20
「聖霊の賜物」 使徒言行録2章1~11節 2017/06/03
「聖霊降臨による教会創設と世界宣教」 使徒言行録2章1-11節 2015/05/24
「聖霊降臨日の出来事と私たちが聖霊に満たされるには」 使徒言行録2章1-13節 2014/06/08
3 「五旬祭のペトロの説教」 使徒言行録2章14~36節 2019/06/13
「ペトロのペンテコステ説教」 使徒言行録2章14-36節 2015/05/28
4 「教会の一致と交わり」 使徒言行録2章37~47節 2019/06/23
「邪悪な時代から救われなさい」 使徒言行録2章37-47節 2015/06/07
5「ヨエルの預言『神の霊の降臨』と、ぺトロの聖霊降臨日の説教」 ヨエル書3章1-2節 2014/08/03
6 「人間を救うのは、この人以外にない。」 使徒言行録4章1~12節 2019/06/29
「わたしたちが救われるべき名」 使徒言行録4章1-12節 2015/06/14
「ヨエルの預言『神の霊の降臨』と、ぺトロの聖霊降臨日の説教」 ヨエル書3章1-2節 2014/08/03
7 「宣教する教会」 使徒言行録4章13~31節 2018/06/03
8 「主にある共同生活」 使徒言行録4章32節~37節 2017/07/08
9 「キリストの苦しみにあずかる喜び」 使徒言行録5章27~42節 2018/10/06
10 「フィリポ、エチオピアの高官に福音を伝える 」 使徒言行録8章26-38節 2015/06/21
11 「宣教への派遣」 使徒言行録9章26節~31節 2017/08/12
12 「ペトロによる、しるしと不思議な業」使徒言行録9章32~43節 2016/06/24
13 「異邦人にも聖霊が降る」 使徒言行録11章1-18節 2015/06/28
14 「アンティオキア教会の誕生」 使徒言行録11章19~26節 2013/06/16
15 「教会の祈りと天使による牢からの脱出 」 使徒言行録12章1-19節 2013/07/02
16 「宣教への派遣」 使徒言行録13章1-12節 2018/06/18「宣教への派遣」
17 「罪の赦しの福音」 使徒言行録13章13-26節 2013/07/09
18 「すべての人に対する教会の宣教」 使徒言行録13章44~52節 2018/08/15
19 「偶像を離れて、生ける神に立ち帰る 」 使徒言行録14章8-20節 2013/0
20 「エルサレムの使徒会議」 使徒言行録15章1-21節 2013/07/23
21 「神の摂理による伝道」 使徒言行録15章36-16章5節 2013/07/28
22 「悪霊追放」 使徒言行録16章16~24節 2018/06/10
「人生の揺るがない土台と自由」 使徒言行録16章11-40節 2013/08/04
23 「偶像崇拝との対決 」 使徒言行録17章13-31節 2013/08/11
24 「悔改めの使信:十字架を欠いたアレオパゴスの説教」使徒言行録17章22~34節 2017/06/18
25 「わたしが共にいる。恐れるな、語り続けよ。」 使徒言行録18章1-17節 2013/08/18
26 「生活の刷新」 使徒言行録19章11節~20節 2017/07/23
27 「貪欲は偶像礼拝にほかならない 」 使徒言行録19章23-40節 2013/08/25
28 「パウロ、青年を生き返らせる」 使徒言行録20章1-12節 2015/07/04
29 「苦難の共同体」 使徒言行録20章17節~35節 2017/08/17
30 「復活の希望」 使徒言行録24章10~21節 2016/07/03
31 「パウロへのイエスの顕現」 使徒言行録26章12-23節 2013/09/01
32 「パウロのローマへの旅」 使徒言行録27章13-38節 2013/09/06
33 「破局からの救い」 使徒言行録27章33~44節 2016/07/10
34 「パウロのローマ到着と伝道 」 使徒言行録28章11-31節 2013/09/18
ローマ の信徒への手紙
1 「霊に従う生活」 ローマの信徒への手紙7章1節~6節 2016/08/14
2 「希望による忍耐」 ローマの信徒への手紙8章18-25節 2017/09/02
3 「神の子とする霊」 ローマの信徒への手紙8章12~17節 2018/05/27
「神の霊に従って歩む者」 ローマの信徒への手紙8章12~14節
4 「聖書の神は語られる神、沈黙し続けない」 ローマの信徒への手紙8章31~39節 2018/05/08
5 「異邦人の救い」 ローマの信徒への手紙9章19~29節 2017/07/26
6 「新たな神の民の誕生」 ローマの信徒への手紙10章1節~17節 2016/05/29
7 「神の救いのご計画の深い富と知恵」 ローマの信徒への手紙11章28~36節 2016/09/17
8 「神の賜物である愛に生きる生活」 ローマの信徒への手紙12章9~21節 2019/08/14
「偽りのない愛」 ローマの信徒への手紙12章9-21節 2015/08/12
9 「教会内の強い者と弱い者の交わり」 ローマの信徒への手紙14章1~9節 2019/09/04
「正しい服従」<福音のためなら、わたしはどんなことでもします> 2015/08/23
コリントの信徒への手紙一
1 「教会の一致の勧め」 コリントの信徒への手紙一、1章10~17節 2017/09/1 6
2 「神のために力を合わせて働く」 コリントの信徒への手紙一、2章10節~3章9節 2016/08/06
3 「試練から逃れる道」 コリントの信徒への手紙一、10章13節 2019/05/11
4 「主の晩餐とは」 コリントの信徒への手紙一、11章23~39節 2016/07/21
5 「キリストの体である教会」 コリントの信徒への手紙一、12章14~26節 2018/07/21
6 「最高の道である愛」 1コリント12章27~13章13節 2018/08/24
7 「世を救うキリストの愛」 1コリント13章4~8、13節 2018/09/17
8 「もし、キリストが復活しなかったのなら。」 コリントの信徒への手紙一、15章1-20節 2014/04/28
9 「もし、死者が復活しないとしたら」 コリントの信徒への手紙一、15章30-34節 2014/05/04
10 「究極の希望-死者の復活」 コリントの信徒への手紙一、15章35-52節 2017/09/08
コリントの信徒への手紙二
1 「左右の手にある義の武器」 コリントの信徒への手紙二、6章1~10節 2018/07/16
2 「永遠の住み家」 コリントの信徒への手紙二、5章1~10節 2016/09/25
3 「和解の福音」 コリントの信徒への手紙二、5章14~6章2節 2017/08/02
4 「神の恵みに応える献金」 2コリントの信徒への手紙9章6~15節 2018/09/08
「神の恵みによる慈善の業(献金)」 コリントの信徒への手紙二、8章1~15節 2017/07/02
5 「神の恵みに応える献金」 2コリントの信徒への手紙9章6-15節 2018/09/08
「神の恵みによる慈善の業(献金)」 2コリントの信徒への手紙8章1-15節 2017/07/02
6 「パウロの伝道者としての誇り」 コリントの信徒への手紙二、11章7~15節 2019/09/10
「弱さの中で発揮される神の力」 コリントの信徒への手紙二、11章7~15節 2015/08/30
ガラテヤの信徒への手紙
1 「キリストの僕として生きる」 ガラテヤの信徒への手紙1章1~10節 2018/08/31
2 「愛に生きるキリスト者の自由」 ガラテヤの信徒への手紙5章1~11節 2018/07/01
3 「霊の導きに従って歩もう」 ガラテヤの信徒への手紙5章13節~25節 2016/05/01
4 「聖霊に導かれる信仰生活」 ガラテヤの信徒への手紙5章16-26節 2015/05/10
5 「キリスト者の愛の実践」 ガラテヤの信徒への手紙6章1~10節 2019/07/27
「互いに重荷を担いなさい」 ガラテヤの信徒への手紙6章1~10節 2015/07/12
6 「十字架の他に誇るものなし」 ガラテヤの信徒への手紙6章14~18節 2019/09/16
「十字架の他に誇るものなし」ガラテヤの信徒への手紙、6章11~18節 2015/09/06
エフェソの信徒への手紙
1 「神(キリスト)の計り知れない富」 エフェソの信徒への手紙1章3~14節 2017/06/11
2 「異邦人の救い」 エフェソの信徒への手紙2章11~22節 2016/06/19
3 「キリストを心に宿す者」エフェソの信徒への手紙3章14~21節 2016/09/11
4 「新しい人」 エフェソの信徒への手紙4章17~32節 2018/08/12
5 「愛によって歩む、聖なる者とは」 エフェソの信徒への手紙5章1~5節 2017/09/29
6 「新しい人間」 エフェソの信徒への手紙5章11~20節 2016/08/20
7 「夫と妻の務め、親と子の務め」 エフェソの信徒への手紙5章21~6章4節 2018/08/05
フィリピの信徒への手紙
1 「キリストの日に備えて」フィリピの信徒への手紙1章1~11節 2015/10/11
2 「キリストにある生」 フィリピの信徒への手紙、1章12~30節 2016/10/02
3 「世の光としての使命」 フィリピの信徒への手紙2章12~18節 2017/06/24
4 「天国に市民権を持つ者」 フィリピの信徒への手紙3章7~21節 2016/10/16
「何とかして死者の中からの復活に達したいのです」 フィリピの信徒への手紙3章10-15 2014/05/11
5 「女性の働き」 フィリピの信徒への手紙4章1~3節 2019/08/04
「女性たちの働き」 フィリピの信徒への手紙4章1節~3節 2015/07/17
コロサイの信徒への手紙
1 「キリストに仕える喜びと苦難」 コロサイの信徒への手紙1章21~29 2018/09/23
2 「新しい命・悪徳に勝つには」 コロサイの使徒への手紙3章1~11節 2017/04/30
3 「赦しの愛に生きる新しい人間」 コロサイの信徒への手紙、3章12~17節 2019/09/28
「すべてを主イエスの名によって行い、神に感謝しなさい」3章12~17節 2015/09/12
4 「主にある家族の関係」 コロサイの信徒への手紙3章18節~4章1節 2017/08/26
テサロニケの信徒への手紙一
1 「主の来臨の希望と忍耐」 テサロニケの信徒への手紙一、1章1~10節 2019/08/23
テサロニケの信徒への手紙二
1 「主の来臨に備える」 テサロニケの信徒への手紙二、1章1-10節 2015/08/13
2 「働きたくない者は、食べてはならない。」テサロニケの信徒への手紙二、3章6~13節 2017/10/05
テモテへの手紙一
1 「教会における祈り」 テモテへの手紙一、2章1節~10節 2017/07/14
2 「真理の柱である、生ける神の教会」 テモテへの手紙一、3章14~16節 2018/07/08
3 「世の富」 テモテへの手紙一、6章1~12節 2019/10/06
「富にではなく、神に望みを置くように」 2015/09/20
テモテへの手紙二
1 キリスト者の走るべき道のりとは」 テモテへの手紙二、4章7~8節 2018/06/25
テトスへの手紙
フィレモンへの手紙
1 「奴隷をも愛する兄弟とする福音」フィレモンへの手紙1~25節 2015/10/04
ヘブライ人への手紙
1 「大祭司イエスの執り成し」 ヘブライ人への手紙4章14~16 2018/09/29
「大祭司イエスによる永遠の救いの完成」 ヘブライ人への手紙4章14-16 2018/09/14
2 「キリストによる永遠の贖罪」 ヘブライ人への手紙9章11~22節 2016/10/07
2 「信仰による生涯」 ヘブライ人への手紙11章23~29節 2018/10/12
3 「信仰による生涯」 ヘブライ人への手紙11章17~22、29~31節 2017/10/13
4 「天国に市民権を持つ者」 ヘブライ人への手紙11章32-12章2節 2019/10/18
「信仰の完成者イエスを仰ぎ見つつ走ろう」ヘブライ人への手紙11章32~12章2節 2015/10/17
5 「主に従い、信仰のコースを走りきる」 ヘブライの信徒への手紙12章1~13節 2018/07/29
6 「天のエルサレムを目指して」 ヘブライ人への手紙12章18~29節 2016/06/11
ヤコブの手紙
1 「信仰者の実行による証し」 ヤコブの手紙1章19~27節 2019/08/29
「御言葉の実践」 ヤコブの手紙1章19~27節 2015/08/15
2 「金持ちと貧者」 ヤコブの手紙2章1-9節 2019/10/10
「分け隔てをしない真実の愛」ヤコブへの手紙2章1~9節 2015/09/27
3 「隣人愛について」 ヤコブの手紙2章8~13節 2017/09/23
ペトロの手紙一
1 「上に立つ人々に対して」ペトロの手紙一、2章11~25節 2016/09/04
2 「苦難の中にあるキリスト者を励ます」 ペトロの第一の手紙3章13~22節 2019/08/11
「苦難の中の喜び」 ペトロの手紙一、3章13-22節 2015/07/26
ペトロの手紙二
ヨハネの手紙一
1 「世に打ち勝つ信仰」 ヨハネの手紙一、5章1~5節 2016/07/29
2 「天国に市民権を持つ者」 ヨハネ黙示録7章1-4、9-12節 2018/10/19
「天国の礼拝に迎えられるキリスト教徒」 ヨハネの黙示録7章9~17節 2017/10/20
3 「信仰の道」 ヨハネ第一の手紙2章18~29節 2016/06/05
4 「神の愛」 ヨハネによる手紙一、4章7~21節 2018/03/19
5 「神に属する者」 ヨハネの第一の手紙5章10~21節 2016/08/27
ヨハネの手紙二
ヨハネの手紙三
ユダの手紙
ヨハネの黙示録
1 「天国の礼拝に迎えられたキリスト教徒」 ヨハネの黙示録7章9-17節 2017/10/20