http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/tonomura_miki/120300008/
2015.12.08
権威が大嫌いな一休さん。庶民に慕われる
自殺未遂した翌年の応永22年(1415年)、一休さんは22歳で生涯の師、近江堅田の禅興庵(現・祥瑞寺)にいた華叟宗曇(かそうそうどん)に巡り合います。京都「大徳寺」住持(住職)の後継者にもかかわらず、名利(名誉と利益)を嫌い、大徳寺を出て、謙翁と同じように貧困の中で本物の禅を追求していた僧侶です。
一休さんがいかに権力や名利を嫌ったのか、謙翁宗為に続き、華叟宗曇を生涯の師と仰いだことでも分かります。もしかしたら、天皇の皇子として生まれながら権威や名誉に遠い環境で育ったことが、一休さんを反権威主義にしたのかもしれません。
一休の名を「道号(僧侶が戒名の上につける号)」として授けられたのは25歳のとき。以後、彼は亡くなるまで「一休宗純」と名乗りますが、「一休」という名は、彼が自らの境地を以下のようにうたったことから授かったと伝えられています。
「有漏地(うろじ)より 無漏地(むろじ)へ帰る一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」
有漏地は煩悩(人間の欲望)のある境地(状態)で、無漏地は欲に惑わされない境地のこと。一休さんは、このうたで「煩悩を捨てて無欲になるまでの間、ちょっと一休み。雨がふっても、風が吹いても」と自らの心中を表したのです。
真面目な僧ならば、「今すぐ煩悩を捨てる」と言うところでしょう。反骨の一休さんらしいうたに、華叟宗曇が「一休」の名を授けた気持ちもわかる気がします。
その後、27歳の時、一休さんは“琵琶湖でカラスが鳴くのを聞いて”大悟(仏教において真理を得ること)したと伝えられています。このとき、華叟宗曇は印可状(師が熟練した弟子にお墨付きを与える書状、つまり卒業証書のようなもの)を与えようとしますが一休さんは辞退。華叟宗曇は「ばか者!」と笑いながら送り出したといいます。
こうして“独立”した一休さんは以後、詩や狂歌、書画などに興じる日々を送りますが、僧侶としては信じられない奇行を行ったと伝えられています。たとえば……
【一休さんの奇行 その1】
おめでたいムードに包まれた正月の街を、竹の先にドクロを刺して「ご用心、ご用心」と説きながら歩き回る。
このとき、以下の有名な言葉を残しています。
「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」
つまり、正月はめでたいと祝っているけれど、死へまた一歩近づいたことでもあるから、めでたいと浮かれてはいられないという教えです。
【一休さんの奇行 その2】
木製の刀身を朱鞘(しゅざや)の大太刀にさして風変りな格好で街を歩き、「鞘に納めていれば豪壮に見えるが、抜いてみれば木刀でしかない」と説く。
これは、外面を飾ることにしか興味のない当時の世相を風刺したものと伝えられています。そのほか、僧侶とは思えない言葉も残しています。
・釈迦といふ いたづらものが世にいでて おほくの人をまよわすかな
・世の中は起きて稼いで寝て食って 後は死ぬを待つばかりなり
・南無釈迦じゃ 娑婆じゃ地獄じゃ 苦じゃ楽じゃ どうじゃこうじゃというが愚かじゃ
このような一休さんの奇行や言動は一見、とんでもない行為に思えますが、すべてに社会風刺や一休さんならではの教えを含んでいました。そして、この戒律や形式にとらわれない人間臭さが民衆の共感を呼び、一休さんは庶民の人気者になります。
この人気は一休さんの死後も続き、江戸時代には、彼をモデルとした「一休咄(はなし)」が生まれました。そして「一休さんの頓知咄」がさらなる人気に火をつけたのです。
○処世術に「とんち」の発想を生かす
一休さんの「とんち」について、著名な哲学者・梅原猛さんは、以下のように解説しています。
一休がどうして、とんち話の主人公になるのか。「東海一休和尚年譜」には、彼が養叟をはじめとする多くの禅僧や俗人と交わした問答が載っている。禅問答はいつも相手の意表をついて相手を言い負かすことをモットーとしている。一休はこのような禅問答の名人であったらしいが、その問答は自ら読者の笑いを誘う。
(週刊朝日百科「仏教を歩く」:風狂を生きる一休/朝日新聞出版より引用)
つまり、一休さんの「とんち」は禅問答の発展形で、「相手を言い負かす」ことができるというのです。だったら、「こんなはずじゃなかった」とため息ばかりついている現代人の処世術にも使えそうです。試しに実際に一休さんの有名な「とんち」を、処世術に応用してみましょう(ちょっと強引かもしれませんが……)。
『屏風の虎退治』
将軍・足利義満が一休さんに出した有名な問題。
「屏風絵の虎が夜な夜な屏風を抜け出して暴れるので退治してほしい」という問いに「では捕まえますから、虎を屏風絵から出してください」と切り返し義満を感服させた。
この話に出てくる義満公、まるで無理難題をふっかける上司のようではありませんか。だったら、あなたも一休さんのように「どこが無理難題なのか」という根本の部分を徹底的に考え、例えば「それではまず、百戦錬磨の部長のお力でガードの堅い先方の担当者を引っ張り出していただけますか。うちのサービスの魅力は、私が完璧に説明できるように準備しておきます」と切り返してみてはどうでしょう。そこまで言われてはと、逆に率先して動いてくれる上司も案外多いのではありませんか?
『このはし渡るべからず』
桔梗屋が一休さんに出した有名な問題。
店の前の橋を一休さんが渡ろうとすると、「このはしわたるべからず」と書いてある。しかし一休は「この端、渡るべからず」と切り返し、橋の真ん中を堂々と渡った。
この話に出てくる桔梗屋、まるで嫌味な取引先のようですね。そこであなたも一休さんのように、意地悪な課題であっても、あえてまっすぐ「良い方」に受け止め、堂々と正面突破でプレゼンしてみましょう。「本当はこの案件、おたくの会社に頼むつもりはなかったんだけど……」と思っていた取引先も、あまりにストレートなあなたの熱意に考えを改めるかもしれません。
○一休寺に行こう。一休さんの言葉に触れよう
「そうは言っても、一休さんのように機転のきいたとんちは思いつかないよ」という人は多いことでしょう。そんな人は一度、京都府京田辺市の「一休寺」を訪ねてみてください。ここは、一休さんが晩年を過ごし、一休さんを最も身近に感じられるところ。豊かな自然の中に静かにたたずむ風情に、晩年の一休さんをしのぶことができます。
また、運が良ければ、ご住職のお話を聴くことができます。現在の住職・田邊宗一さんは、まるで現代の一休さんのように気さくな方で、観光客が多い休日や、時間が空いている時には、一休さんの教えをわかりやすく語り聞かせてくださいます。
私が訪ねた時も、多くの観光客にマイクで優しく、このように語りかけてくれました。
「人はとかく他人と比べて羨ましがったりねたんだりするもんです。でも、幸せは他人との比較で生まれるものではありません。だから今を良かれ、良かれ、と思って生きていくのが一番、幸せなんですよ」(一休寺住職・田邊宗一さん)
なんだかホッとしませんか。また、一休寺になかなか行けない人のために、一休さんが晩年に著した漢詩集「狂雲集」から、一休さんの言葉をご紹介しましょう。
「ひとつの人形芝居の舞台では、まるごと人間の世界を表現している。あるときは王様の役になり、あるときはただの庶民の役にもなる。目の前に動いているのは、ただの木の切れ端でつくった人形であることをすっかり忘れてしまい、愚かな者はそれが本当の人間の姿だと思いこみ一喜一憂する。舞台の裏でこれをあやつる者のあるのを知らないままでいるのか(狂雲集 七〇 口語訳)」
(「へたな人生論より一休のことば」松本市壽著/河出文庫より引用)
もしかしたら、あなたも目に見える虚像に振り回されていませんか。そうだとしたら、今日から「一休さんの視点」で周囲を見直してみましょう。意外な真実が見えてきて、これまでため息ついていたことがバカバカしくなるかもしれませんよ。
2015.12.08
権威が大嫌いな一休さん。庶民に慕われる
自殺未遂した翌年の応永22年(1415年)、一休さんは22歳で生涯の師、近江堅田の禅興庵(現・祥瑞寺)にいた華叟宗曇(かそうそうどん)に巡り合います。京都「大徳寺」住持(住職)の後継者にもかかわらず、名利(名誉と利益)を嫌い、大徳寺を出て、謙翁と同じように貧困の中で本物の禅を追求していた僧侶です。
一休さんがいかに権力や名利を嫌ったのか、謙翁宗為に続き、華叟宗曇を生涯の師と仰いだことでも分かります。もしかしたら、天皇の皇子として生まれながら権威や名誉に遠い環境で育ったことが、一休さんを反権威主義にしたのかもしれません。
一休の名を「道号(僧侶が戒名の上につける号)」として授けられたのは25歳のとき。以後、彼は亡くなるまで「一休宗純」と名乗りますが、「一休」という名は、彼が自らの境地を以下のようにうたったことから授かったと伝えられています。
「有漏地(うろじ)より 無漏地(むろじ)へ帰る一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」
有漏地は煩悩(人間の欲望)のある境地(状態)で、無漏地は欲に惑わされない境地のこと。一休さんは、このうたで「煩悩を捨てて無欲になるまでの間、ちょっと一休み。雨がふっても、風が吹いても」と自らの心中を表したのです。
真面目な僧ならば、「今すぐ煩悩を捨てる」と言うところでしょう。反骨の一休さんらしいうたに、華叟宗曇が「一休」の名を授けた気持ちもわかる気がします。
その後、27歳の時、一休さんは“琵琶湖でカラスが鳴くのを聞いて”大悟(仏教において真理を得ること)したと伝えられています。このとき、華叟宗曇は印可状(師が熟練した弟子にお墨付きを与える書状、つまり卒業証書のようなもの)を与えようとしますが一休さんは辞退。華叟宗曇は「ばか者!」と笑いながら送り出したといいます。
こうして“独立”した一休さんは以後、詩や狂歌、書画などに興じる日々を送りますが、僧侶としては信じられない奇行を行ったと伝えられています。たとえば……
【一休さんの奇行 その1】
おめでたいムードに包まれた正月の街を、竹の先にドクロを刺して「ご用心、ご用心」と説きながら歩き回る。
このとき、以下の有名な言葉を残しています。
「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」
つまり、正月はめでたいと祝っているけれど、死へまた一歩近づいたことでもあるから、めでたいと浮かれてはいられないという教えです。
【一休さんの奇行 その2】
木製の刀身を朱鞘(しゅざや)の大太刀にさして風変りな格好で街を歩き、「鞘に納めていれば豪壮に見えるが、抜いてみれば木刀でしかない」と説く。
これは、外面を飾ることにしか興味のない当時の世相を風刺したものと伝えられています。そのほか、僧侶とは思えない言葉も残しています。
・釈迦といふ いたづらものが世にいでて おほくの人をまよわすかな
・世の中は起きて稼いで寝て食って 後は死ぬを待つばかりなり
・南無釈迦じゃ 娑婆じゃ地獄じゃ 苦じゃ楽じゃ どうじゃこうじゃというが愚かじゃ
このような一休さんの奇行や言動は一見、とんでもない行為に思えますが、すべてに社会風刺や一休さんならではの教えを含んでいました。そして、この戒律や形式にとらわれない人間臭さが民衆の共感を呼び、一休さんは庶民の人気者になります。
この人気は一休さんの死後も続き、江戸時代には、彼をモデルとした「一休咄(はなし)」が生まれました。そして「一休さんの頓知咄」がさらなる人気に火をつけたのです。
○処世術に「とんち」の発想を生かす
一休さんの「とんち」について、著名な哲学者・梅原猛さんは、以下のように解説しています。
一休がどうして、とんち話の主人公になるのか。「東海一休和尚年譜」には、彼が養叟をはじめとする多くの禅僧や俗人と交わした問答が載っている。禅問答はいつも相手の意表をついて相手を言い負かすことをモットーとしている。一休はこのような禅問答の名人であったらしいが、その問答は自ら読者の笑いを誘う。
(週刊朝日百科「仏教を歩く」:風狂を生きる一休/朝日新聞出版より引用)
つまり、一休さんの「とんち」は禅問答の発展形で、「相手を言い負かす」ことができるというのです。だったら、「こんなはずじゃなかった」とため息ばかりついている現代人の処世術にも使えそうです。試しに実際に一休さんの有名な「とんち」を、処世術に応用してみましょう(ちょっと強引かもしれませんが……)。
『屏風の虎退治』
将軍・足利義満が一休さんに出した有名な問題。
「屏風絵の虎が夜な夜な屏風を抜け出して暴れるので退治してほしい」という問いに「では捕まえますから、虎を屏風絵から出してください」と切り返し義満を感服させた。
この話に出てくる義満公、まるで無理難題をふっかける上司のようではありませんか。だったら、あなたも一休さんのように「どこが無理難題なのか」という根本の部分を徹底的に考え、例えば「それではまず、百戦錬磨の部長のお力でガードの堅い先方の担当者を引っ張り出していただけますか。うちのサービスの魅力は、私が完璧に説明できるように準備しておきます」と切り返してみてはどうでしょう。そこまで言われてはと、逆に率先して動いてくれる上司も案外多いのではありませんか?
『このはし渡るべからず』
桔梗屋が一休さんに出した有名な問題。
店の前の橋を一休さんが渡ろうとすると、「このはしわたるべからず」と書いてある。しかし一休は「この端、渡るべからず」と切り返し、橋の真ん中を堂々と渡った。
この話に出てくる桔梗屋、まるで嫌味な取引先のようですね。そこであなたも一休さんのように、意地悪な課題であっても、あえてまっすぐ「良い方」に受け止め、堂々と正面突破でプレゼンしてみましょう。「本当はこの案件、おたくの会社に頼むつもりはなかったんだけど……」と思っていた取引先も、あまりにストレートなあなたの熱意に考えを改めるかもしれません。
○一休寺に行こう。一休さんの言葉に触れよう
「そうは言っても、一休さんのように機転のきいたとんちは思いつかないよ」という人は多いことでしょう。そんな人は一度、京都府京田辺市の「一休寺」を訪ねてみてください。ここは、一休さんが晩年を過ごし、一休さんを最も身近に感じられるところ。豊かな自然の中に静かにたたずむ風情に、晩年の一休さんをしのぶことができます。
また、運が良ければ、ご住職のお話を聴くことができます。現在の住職・田邊宗一さんは、まるで現代の一休さんのように気さくな方で、観光客が多い休日や、時間が空いている時には、一休さんの教えをわかりやすく語り聞かせてくださいます。
私が訪ねた時も、多くの観光客にマイクで優しく、このように語りかけてくれました。
「人はとかく他人と比べて羨ましがったりねたんだりするもんです。でも、幸せは他人との比較で生まれるものではありません。だから今を良かれ、良かれ、と思って生きていくのが一番、幸せなんですよ」(一休寺住職・田邊宗一さん)
なんだかホッとしませんか。また、一休寺になかなか行けない人のために、一休さんが晩年に著した漢詩集「狂雲集」から、一休さんの言葉をご紹介しましょう。
「ひとつの人形芝居の舞台では、まるごと人間の世界を表現している。あるときは王様の役になり、あるときはただの庶民の役にもなる。目の前に動いているのは、ただの木の切れ端でつくった人形であることをすっかり忘れてしまい、愚かな者はそれが本当の人間の姿だと思いこみ一喜一憂する。舞台の裏でこれをあやつる者のあるのを知らないままでいるのか(狂雲集 七〇 口語訳)」
(「へたな人生論より一休のことば」松本市壽著/河出文庫より引用)
もしかしたら、あなたも目に見える虚像に振り回されていませんか。そうだとしたら、今日から「一休さんの視点」で周囲を見直してみましょう。意外な真実が見えてきて、これまでため息ついていたことがバカバカしくなるかもしれませんよ。










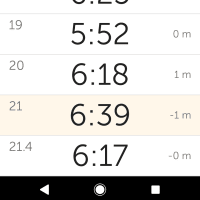

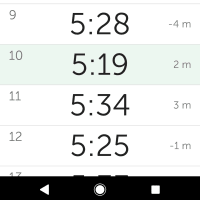
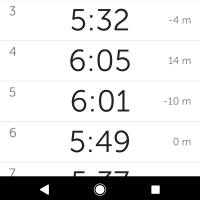
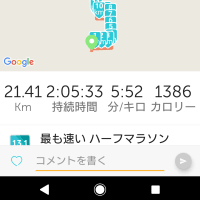





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます