秋田県立新美術館には世界的画家の一人である藤田嗣治が1937年(昭和12年)に平野政吉の依頼で描いた大作「秋田の行事」が飾られている。縦3.65m、横20.5で当時世界一と言われた。しかも、それだけの大作を僅か15日間という驚異的な速さで書き上げた、という。
私は旧美術館にある時に3-4回見に行った。見事な構成、構図があり、描かれている人物の表情、馬や犬は本当に生きている。藤田の鋭い観察力、卓越した表現力が感じられる。秋田の行事として多くの対象を描いていながら広い空の空間が保持され、その青さが素晴らしい。私は見る度に感心した。藤田の画は画集とかで見ると必ずしも写実的ではなくとっつきにくい部分もあるが、他の作品と併せてその凄さを実感していた。特に裸婦像、猫の絵も良い。
フジタに関するドキュメント番組を過去に2本ほど見た。しかし、その人間像は興味はあったがとても分かり難い。平野政吉とフジタの関係もよくわからなかった。
秋田市のにぎわい交流館の多目的ホールで、内館牧子脚本、わらび座員によるミュージカル「政吉とフジタ」が8月30日から12月13日の長期間にわたって1日2公演、約130公演が行われており、興味を感じていた。毎日出勤時に会場脇を徒歩で通るのであるが、なかなか観劇の機会は得られなかった。
全公演スケジュールが間も無く終了するというので、12月6日の昼の部の公演を見に行った。このミュージカルを見て、当時、超裕福であった平野が藤田の才能認め、多額の経済援助をしながら真摯に応援し、秋田の子供達のために世界的画家であるフジタの作品をすべて収集するという夢を描いていた。藤田も平野に対する感謝の念を表すために、秋田に逗留しこの大作を短期間で完成させた。この平野の計画は戦中戦後の騒乱の中で頓挫したが、平野の意思はのちに「秋田の行事」が秋田県立美術館に収蔵されるという形で実現した。藤田はその後に描いた戦争画を非難され、再度渡仏し、二度と日本の地を踏むとなく81歳で没した。平野は93歳で死去した。
ミュージカルは出演者が藤田とその妻マドレーヌ、政吉と雇い人の娘リエの4人。藤田と平野の交流の場面を中心に描かれ、上演時間1時間50分ほどであった。舞台装置も簡素で場面展開もスムーズに行われ、コンパクトにまとめられた。出演者4人の演技も卓越していた。特に、藤田がキャンバスに見立てた何もない空間に向かい絵筆を振るう場面の演技、表現は真に迫っていた。ミュージカルなので節目節目には歌で表現されたが、セリフ以上の説得力があった。
秋田の地において約3け月のロングランが行われたのも驚きであったが、私が見た12月6日の昼の部で入場者数が2万人に達したとのことで、簡素なお祝いが舞台上で催され、2万人目の方に花束が贈呈された。会場は席数が280席程度の小ホールである。100回ほどの公演でこれだけ観客数があったということも驚きである。秋田市民にとって、県民にとって国際的画家レオナール・フジタの存在は「秋田の行事」を通じて不動の位置にある・・と感じた。
フジタの作品をもっと味わってみたい、評論や伝記を通じて彼の人物像に触れてみたいと思いつつ満足して帰路についた。
私は旧美術館にある時に3-4回見に行った。見事な構成、構図があり、描かれている人物の表情、馬や犬は本当に生きている。藤田の鋭い観察力、卓越した表現力が感じられる。秋田の行事として多くの対象を描いていながら広い空の空間が保持され、その青さが素晴らしい。私は見る度に感心した。藤田の画は画集とかで見ると必ずしも写実的ではなくとっつきにくい部分もあるが、他の作品と併せてその凄さを実感していた。特に裸婦像、猫の絵も良い。
フジタに関するドキュメント番組を過去に2本ほど見た。しかし、その人間像は興味はあったがとても分かり難い。平野政吉とフジタの関係もよくわからなかった。
秋田市のにぎわい交流館の多目的ホールで、内館牧子脚本、わらび座員によるミュージカル「政吉とフジタ」が8月30日から12月13日の長期間にわたって1日2公演、約130公演が行われており、興味を感じていた。毎日出勤時に会場脇を徒歩で通るのであるが、なかなか観劇の機会は得られなかった。
全公演スケジュールが間も無く終了するというので、12月6日の昼の部の公演を見に行った。このミュージカルを見て、当時、超裕福であった平野が藤田の才能認め、多額の経済援助をしながら真摯に応援し、秋田の子供達のために世界的画家であるフジタの作品をすべて収集するという夢を描いていた。藤田も平野に対する感謝の念を表すために、秋田に逗留しこの大作を短期間で完成させた。この平野の計画は戦中戦後の騒乱の中で頓挫したが、平野の意思はのちに「秋田の行事」が秋田県立美術館に収蔵されるという形で実現した。藤田はその後に描いた戦争画を非難され、再度渡仏し、二度と日本の地を踏むとなく81歳で没した。平野は93歳で死去した。
ミュージカルは出演者が藤田とその妻マドレーヌ、政吉と雇い人の娘リエの4人。藤田と平野の交流の場面を中心に描かれ、上演時間1時間50分ほどであった。舞台装置も簡素で場面展開もスムーズに行われ、コンパクトにまとめられた。出演者4人の演技も卓越していた。特に、藤田がキャンバスに見立てた何もない空間に向かい絵筆を振るう場面の演技、表現は真に迫っていた。ミュージカルなので節目節目には歌で表現されたが、セリフ以上の説得力があった。
秋田の地において約3け月のロングランが行われたのも驚きであったが、私が見た12月6日の昼の部で入場者数が2万人に達したとのことで、簡素なお祝いが舞台上で催され、2万人目の方に花束が贈呈された。会場は席数が280席程度の小ホールである。100回ほどの公演でこれだけ観客数があったということも驚きである。秋田市民にとって、県民にとって国際的画家レオナール・フジタの存在は「秋田の行事」を通じて不動の位置にある・・と感じた。
フジタの作品をもっと味わってみたい、評論や伝記を通じて彼の人物像に触れてみたいと思いつつ満足して帰路についた。

















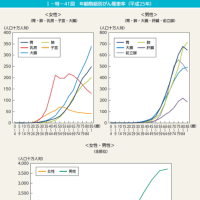


http://www.sakigake.jp/p/akita/hokuto.jsp?kc=20151206ax
>なぜ戦争画に力を入れたのかを考えると複雑な思いに駆られる。
戦時中は参戦国の画家たちが熱心に戦争画を描いていた事実、こんな簡単なことが分からない取材不足。
この数ヶ月前に私は東京国立近代美術館で藤田嗣治の「アッツ島玉砕」を鑑賞してきました。
先入観を持って作品を視るほどバカではありません。あらゆる角度からしても「反戦画」でした。
なお同館の観覧券一般430円、65歳以上は無料で、隣接した工芸館も観覧いただけます。
撮影も可能でしたが、係員にご確認ください。
しばらくは上京の予定もありませんが、美術館のご紹介ありがとうございました。
今の所、画集でしか見てませんが、藤田嗣治の「アッツ島玉砕」には悲しみが表現されていると思います。
竹橋は地名ではなく、お堀に架かる橋の名で東京メトロの駅名です。
美術館の所在地は北の丸公園、向かいのパレスサイドビルの毎日新聞社は一ツ橋になります。
http://www.momat.go.jp/am/visit/
都心にあって心休まる場所と思います。
前々回のコメントで正しくは “violinist” 失礼しました。