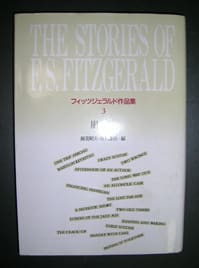WORLD'S END AND OTHER STORIES 


1980年 ポール・セロー
前に読んだ記憶はあるけれど内容が思い出せないという本がけっこうあります。
それで読み直してみると「確かに読んだことがあるわ」と思えたりします。
特に短篇集だと、他の話しは全然覚えてないけれど、鮮明に思い出せる話しが
1~2篇あったりして、自分が好きな物語の傾向とかを再認識できたりします。
『ワールズ・エンド』も読んだ覚えはあるんだけど内容が思い出せなくて再読したら
3篇が読み出しで甦ってきました。
9篇がおさめられていますが、主人公は全て外国人。
ロンドンで暮らすアメリカ人ビジネスマン、コルシカ島にやってきたアメリカ人教授
毎年ロンドンへ出かけるアメリカ人教授、商用(?)でパリにやって来たアメリカ人男性
ドイツの友人夫妻を訪ねたアメリカ人外交官などなど…
旅慣れていて、海外にいても自国にいるようにリラックスしているような印象を受けがちな
人たちばかりですが、ふとよぎる異国での違和感… みたいなものが描かれているようです。
鮮明に甦った3篇をあげてみます。
『サーカスと戦争(After The War)』
15歳のイギリス人の少女ディーリアは、一夏親元を離れてフランスのラモー氏一家の
ヴァンスのコテージで過ごしている。
コテージには電気が無く、ラモー氏はそれが自慢のようだった。
ある日、皆でサーカスを観に行くというラモー氏の提案をディーリアが拒否すると
ラモー氏は戦争の話しを始めた。
いわゆる短期ホームステイみたいなもんなのでしょうが、ホストファミリーが
「…」という人たちだったら、せっかくの海外暮らしがけっこうきつい日々になりますね。
友人が何人かロンドンでホームステイしてたんですけどいくつかトラブルもあったし…
もちろん素敵なホストファミリーの方々もたくさんいらっしゃると思いますけど。
隣同士の国なのに、こんなに意識に隔たりがあろうとは… ヨーロッパでもそうなのか…
『真っ白な嘘(White Lies)』
アフリカで寄生虫の研究をしていた撲は、ある学校の敷地内でジェリーと同居していた。
ジェリーは毎週末にアシーナというアフリカ人女性と過ごしていた。
ある日校長の娘が休暇を過ごすためにやって来た。
ジェリーはその娘と結婚すると宣言し、週末に校長一家を招待することにする。
けっこうゾッとする話しなのですが、女性をなんだと思ってるんだよぉというキャラクターの
ジェリーに対してはちょっと「いい気味!」という気もします。
でもこの話しを読んでからしばらくは外に洗濯物を干すのが怖くなったのよね~。
うちのまわり、けっこう緑が多くて虫もウジャウジャいるもんだから…
『緑したたる島(The Greenest Island)』
大学生のデュヴァル19歳とポーラ21歳は、ありったけの320ドルを持ち、片道のチケットで
プエルト・リコのサン・ファンへ向かった。
二人の気持ちはすでに離れていたが、ポーラは妊娠していた。
ギリギリの暮らしの末、デュヴァルはホテルのレストランで働くことにする。
南国へ愛の逃避行… なんてロマンティックなことでしょう! と思ったら…
現実って厳しいよね… でも若い頃は夢みるよね… でもやっぱり無茶しすぎよね…
「こんなはずじゃない!」がお互いの頭の中をかけめぐる毎日って地獄よ、きっと。
色あせていく風景の美しさと二人の心をリンクさせているところが絶妙です。
『あるレディーの肖像』というのがあって、ヘンリー・ジェイムズの『ある貴婦人の肖像』を思い出しました。
内容はぜんぜん違うんですけどね。
解説すっとばしましたのでよくわかりませんが
ポール・セローもヘンリー・ジェイムズ的にヨーロッパに心を寄せてるタイプなのかしら?
でも讃美しているってわけでもなさそうだし…
国内にいるより海外でこそ際立つ国民性を描くつもりだったのでしょうか?
それとも、コスモポリタンならではの気楽さと所詮は異国人だという悲哀を
対比させて物語を… ま、どうでもいいや。
面白かったです、とにかく。
それはさておき、けっこう暗めな話しばかり覚えてましたね。
皮肉が利いた笑い話みたいなものもあったのですけど…
さては私は暗い物語が好きだね! そんな気はしてました。
世界各国を見て来た訳者(村上春樹氏)だからこそ訳せた一冊なのでしょうか?
読んでみたいな!という方は下の画像をクリックしてね


 ひとことフィギュアスケートコーナー
ひとことフィギュアスケートコーナー
あぁぁ…小塚崇彦ファンとか言いながら、24日のすぽると見忘れた!! Nさんが特集するよってお知らせくれたのに
27日は全力で応援します! もちろん他のお二人も… あ!女子もフリー頑張って!!



1980年 ポール・セロー
前に読んだ記憶はあるけれど内容が思い出せないという本がけっこうあります。
それで読み直してみると「確かに読んだことがあるわ」と思えたりします。
特に短篇集だと、他の話しは全然覚えてないけれど、鮮明に思い出せる話しが
1~2篇あったりして、自分が好きな物語の傾向とかを再認識できたりします。
『ワールズ・エンド』も読んだ覚えはあるんだけど内容が思い出せなくて再読したら
3篇が読み出しで甦ってきました。
9篇がおさめられていますが、主人公は全て外国人。
ロンドンで暮らすアメリカ人ビジネスマン、コルシカ島にやってきたアメリカ人教授
毎年ロンドンへ出かけるアメリカ人教授、商用(?)でパリにやって来たアメリカ人男性
ドイツの友人夫妻を訪ねたアメリカ人外交官などなど…
旅慣れていて、海外にいても自国にいるようにリラックスしているような印象を受けがちな
人たちばかりですが、ふとよぎる異国での違和感… みたいなものが描かれているようです。
鮮明に甦った3篇をあげてみます。
『サーカスと戦争(After The War)』

15歳のイギリス人の少女ディーリアは、一夏親元を離れてフランスのラモー氏一家の
ヴァンスのコテージで過ごしている。
コテージには電気が無く、ラモー氏はそれが自慢のようだった。
ある日、皆でサーカスを観に行くというラモー氏の提案をディーリアが拒否すると
ラモー氏は戦争の話しを始めた。
いわゆる短期ホームステイみたいなもんなのでしょうが、ホストファミリーが
「…」という人たちだったら、せっかくの海外暮らしがけっこうきつい日々になりますね。
友人が何人かロンドンでホームステイしてたんですけどいくつかトラブルもあったし…
もちろん素敵なホストファミリーの方々もたくさんいらっしゃると思いますけど。
隣同士の国なのに、こんなに意識に隔たりがあろうとは… ヨーロッパでもそうなのか…
『真っ白な嘘(White Lies)』

アフリカで寄生虫の研究をしていた撲は、ある学校の敷地内でジェリーと同居していた。
ジェリーは毎週末にアシーナというアフリカ人女性と過ごしていた。
ある日校長の娘が休暇を過ごすためにやって来た。
ジェリーはその娘と結婚すると宣言し、週末に校長一家を招待することにする。
けっこうゾッとする話しなのですが、女性をなんだと思ってるんだよぉというキャラクターの
ジェリーに対してはちょっと「いい気味!」という気もします。
でもこの話しを読んでからしばらくは外に洗濯物を干すのが怖くなったのよね~。
うちのまわり、けっこう緑が多くて虫もウジャウジャいるもんだから…
『緑したたる島(The Greenest Island)』

大学生のデュヴァル19歳とポーラ21歳は、ありったけの320ドルを持ち、片道のチケットで
プエルト・リコのサン・ファンへ向かった。
二人の気持ちはすでに離れていたが、ポーラは妊娠していた。
ギリギリの暮らしの末、デュヴァルはホテルのレストランで働くことにする。
南国へ愛の逃避行… なんてロマンティックなことでしょう! と思ったら…
現実って厳しいよね… でも若い頃は夢みるよね… でもやっぱり無茶しすぎよね…
「こんなはずじゃない!」がお互いの頭の中をかけめぐる毎日って地獄よ、きっと。
色あせていく風景の美しさと二人の心をリンクさせているところが絶妙です。
『あるレディーの肖像』というのがあって、ヘンリー・ジェイムズの『ある貴婦人の肖像』を思い出しました。
内容はぜんぜん違うんですけどね。
解説すっとばしましたのでよくわかりませんが
ポール・セローもヘンリー・ジェイムズ的にヨーロッパに心を寄せてるタイプなのかしら?
でも讃美しているってわけでもなさそうだし…
国内にいるより海外でこそ際立つ国民性を描くつもりだったのでしょうか?
それとも、コスモポリタンならではの気楽さと所詮は異国人だという悲哀を
対比させて物語を… ま、どうでもいいや。
面白かったです、とにかく。
それはさておき、けっこう暗めな話しばかり覚えてましたね。
皮肉が利いた笑い話みたいなものもあったのですけど…
さては私は暗い物語が好きだね! そんな気はしてました。
世界各国を見て来た訳者(村上春樹氏)だからこそ訳せた一冊なのでしょうか?
読んでみたいな!という方は下の画像をクリックしてね

 ひとことフィギュアスケートコーナー
ひとことフィギュアスケートコーナーあぁぁ…小塚崇彦ファンとか言いながら、24日のすぽると見忘れた!! Nさんが特集するよってお知らせくれたのに
27日は全力で応援します! もちろん他のお二人も… あ!女子もフリー頑張って!!











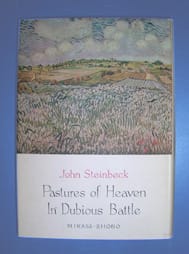


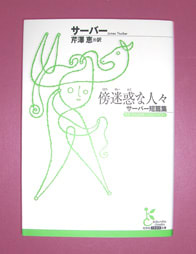







 良すぎる
良すぎる  ものすごくよいんだけど
ものすごくよいんだけど
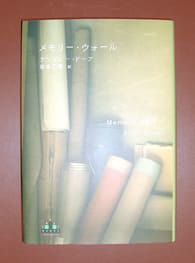




 ) とうとう500本のツルハシと250本のオノが役にたつ時が!
) とうとう500本のツルハシと250本のオノが役にたつ時が!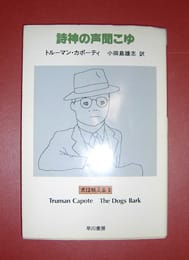





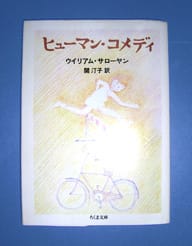


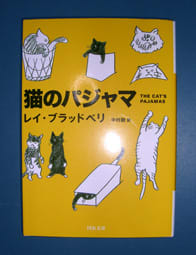






 すごくいい席でテソン目の前!! Fantastic Babyまで聞けて最高でした
すごくいい席でテソン目の前!! Fantastic Babyまで聞けて最高でした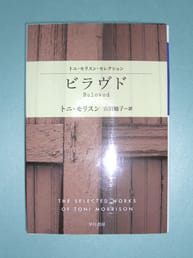

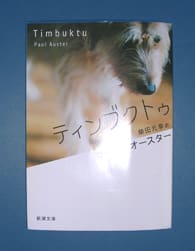

 きちんときちんと治して、また美しくて癒される歌声を聴かせてね。 待っています。
きちんときちんと治して、また美しくて癒される歌声を聴かせてね。 待っています。