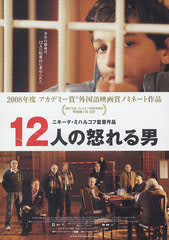ロミオとジュリエットの悲劇はわずか4日間の出来事で、そのスピードにこそ若さが宿っているのだと思っていた。
本作は熟年カップルの大人の恋だが、旅行者リチャ-ド・ギアの海辺の宿への滞在期間4日間で燃え上がるのだ。その海辺の宿がとても凝った作りでセットなのか、実在するのか不思議なムードを持っている。
主役の二人、ギアとダイアン・レインは「運命の女」で共演しており、このときは夫婦役。妻の危険な不倫が引き起こす事件の波紋を描いた。
今回は一転してラブ・ロマンス。脇役もなかなかの顔ぶれが揃っているのだが、平板な出来事が平板に展開し、人物を魅力的に描くエピソードもない。
このような作品をじっくり見せてくれるとハリウッドの底力を示すことができるのに、と思ってしまう。
本作は熟年カップルの大人の恋だが、旅行者リチャ-ド・ギアの海辺の宿への滞在期間4日間で燃え上がるのだ。その海辺の宿がとても凝った作りでセットなのか、実在するのか不思議なムードを持っている。
主役の二人、ギアとダイアン・レインは「運命の女」で共演しており、このときは夫婦役。妻の危険な不倫が引き起こす事件の波紋を描いた。
今回は一転してラブ・ロマンス。脇役もなかなかの顔ぶれが揃っているのだが、平板な出来事が平板に展開し、人物を魅力的に描くエピソードもない。
このような作品をじっくり見せてくれるとハリウッドの底力を示すことができるのに、と思ってしまう。