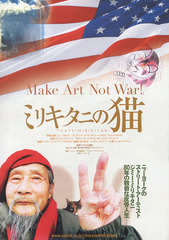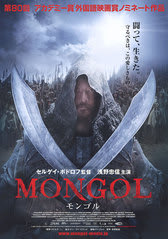中年パワー炸裂のミュージカル。中年男も中年女も3人組だが、女性の方が元気だ。
主演のメリル・ストリープはロバート・アルトマン監督の遺作「今宵、フィッツジェラルド劇場で」でも得意ののどを披露、歌もうまいんだ、と感心した覚えがある。今年60歳だからすでに中年以上だ。
地中海、ギリシャの島でホテルを経営するメリル一家の娘の、結婚式前夜からの1日の物語。父親知らずの娘が父親の可能性のある3人の男性を招待したことことから巻き起こる騒動をミュージカルに仕立てている。
ABBAのヒット曲を豪華配役のストーリー付きで楽しもうという趣向だ。いずれも耳にしたことのある楽曲が次から次にオン・パレード。こういう意味の歌詞だったのかと初めて知った。それにしてもうまく物語とシンクロしたものだ。
先代007・ピアーズ・ブロスナンの歌も愛嬌だ。