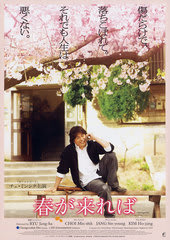冒頭に出てくる新宿のアンダーグラウンドないかがわしさで一挙にタイムスリップ感を味わえる。当時を知らない世代にはまるで異界かもしれないが。
ただし、時代のムードはよく出ているものの、学生運動、三億円事件とドラマチックな事件を描いているにしては視点が引いていて、平板な描写に終始している。遅れて失敗するかに見えた強奪もなぜかすんなり成功してしまう。
ヒロインが大事件に巻き込まれるのが「恋心」のためという説得力がまるでないのだ。登場人物がそれぞれに背負っている事情も表面的に触れられるがそれ以上には立ち入ろうとしていない。藤村俊二のバイク屋も魅力的なキャラクターなのに、ふくらませることなくいつの間にか中途半端に死んでしまっている。
こういう人たちがいてこんな出来事が起きました、という小さな新聞記事の読後感に似ている。したがって誰に感情移入できるでもなく、ラストでそれぞれのその後を示されても感慨を持って迫ってこない。
予告で流れる元ちとせの主題歌「青のレクイエム」に惹かれて見に行ったのだ。面白い題材なのにもったいない。
ただし、時代のムードはよく出ているものの、学生運動、三億円事件とドラマチックな事件を描いているにしては視点が引いていて、平板な描写に終始している。遅れて失敗するかに見えた強奪もなぜかすんなり成功してしまう。
ヒロインが大事件に巻き込まれるのが「恋心」のためという説得力がまるでないのだ。登場人物がそれぞれに背負っている事情も表面的に触れられるがそれ以上には立ち入ろうとしていない。藤村俊二のバイク屋も魅力的なキャラクターなのに、ふくらませることなくいつの間にか中途半端に死んでしまっている。
こういう人たちがいてこんな出来事が起きました、という小さな新聞記事の読後感に似ている。したがって誰に感情移入できるでもなく、ラストでそれぞれのその後を示されても感慨を持って迫ってこない。
予告で流れる元ちとせの主題歌「青のレクイエム」に惹かれて見に行ったのだ。面白い題材なのにもったいない。