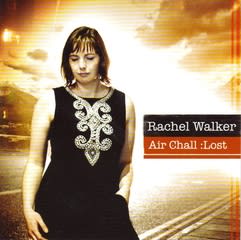”Raison D'etre”by Dave Swarbrick
デイブ・スワブリックといえばイギリスのエレクトリック・トラッドの開祖、フェアポート・コンベンションの看板バイオリン弾きとして、いまさら説明の必要もない。
60年代末、それまでトラッド歌手のマーティン・カーシーとコンビを組んで渋い英国民謡を演奏していたスワブリックが、トラッドの世界に旅立とうとしていたフェアポート・コンベンションから、アルバム”アンハーフブリッキング”製作のためのセッションに招かれた時のエピソードが面白い。
「異種音楽とのセッションだって?それも相手がジャズバンドならまだしも、ロックバンドとは!”俺を誰だと思ってるんだ」と困惑をあらわにしつつ出かけて行ったスワブリックがその夜、相棒のカーシーにかけてきた電話は、「おい、信じられるかい!最高のセッションだったんだ」との内容だった。この話は大好きだ。
そして、一日だけの付き合いのはずがスワブリックは、以後十年余の長きに渡ってフェアポート・コンベンションなる”ロックバンド”の看板スターとして活躍することとなる。
フェアポートを抜けた後のスワブリックは自身のバンドを率いてみたり、フェアポート時代の同僚、サイモン・ニコルとデュオを組み、あるいは旧友マーティン・カーシーとのコンビを復活させたりと、それなりの活躍をしていたのだが、いつの間にか名前を聞く機会もなくなっていた。
そういえばこの頃スワブリックの音沙汰がないな、と思い始めた90年代、かっての仲間が”スワブ・エイド”なる基金を組み、「苦境にあるスワブリックを救おう」などと呼びかけるようになる。
何事かと思えば、スワブリックは重い肺気腫に侵され、明日をも知れぬ健康状態だったのだった。思い起こせばフェアポート時代、咥え煙草でバイオリンを奏でるスワブリックの勇姿は、まさにバンドの看板スターにふさわしいかっこよさだったのだが、その影で彼の肺はボロボロとなっていた。
スワブ・エイドが立ち上がった頃スワブリックは、酸素吸入器が離せぬ車椅子暮らしで、ひとたび風邪でもひこうものならそれだけで命取りとなるような状態にあったようだ。一時はそんなところまで行ってしまったスワブリックだったのだ。
その後、思い切って受けてみた肺の移植手術が成功し、どうにか社会生活に復帰できるようになったとの知らせが、「意外にも」なんてニュアンスもないではなくもたらされたのは、何年後だったろうか。
ネット越しで届けられた、吸入器もなしに歩き語り、そしてバイオリンを奏でるスワブリックの映像は、まさに”地獄から生還を果たした者”のそれで、ひどく年齢を重ねた感じのその姿に、かってのひょうきん者のバイオリン弾きの面影を探すのは難しかった。
そんなスワブリックから届けられたアルバム、これは彼の復活宣言・・・と言っていいのだろうか。
ともかく聴いてみると、「ああ、ずいぶん音が細く硬くなってしまったなあ」と感じないでもなかった。が、そのバイオリンの節回しのクセは、昔と変わらぬスワブリックのそれである。トラッド曲あり自作曲あり。ダンス曲で弾み、メロディアスな曲で泣かせ。気ままにメロディをまさぐり、自身の世界を編み上げて行くスワブリックに、「まあ、生きてりゃいいじゃん」と頷いてみせたい気分になっていた。うん、ずいぶん長い付き合いだよなあ。
スワブリックはすべての曲に自筆の解説文を寄せているのだが、最終曲、18世紀のアイルランドのハープ祭りに関する話が妙に心に残った。
10人のアイリッシュ・ハープ弾き。そのうち6人が盲目で、皆、70歳を越えている。最高齢者は97歳。そこに音楽の記録のため、18歳のオルガン弾きの少年が呼ばれていた。
そして今日、スワブリックは時空を越え、それらハープ弾きの音楽を我がものとする事が出来た・・・
手術後のスワブリックを貼るところだろうけど、これがスワブリック初対面という人もおられるだろうし、スワブリックとフェアポートが一番生き生きとしていた1970年頃の映像を貼る。と言うか私も、久しぶりに若い彼らを見たくなった。