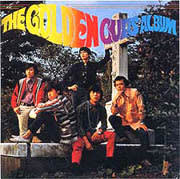”Peter Skellern ”
ピ-タ-・スケラ-ンという歌手がいる。もっと正確に言えば、主に70年代に活躍したイギリスのシンガ-・ソングライタ-。一般には単なるポップな歌手としか認識されていず、その存在、あまり重くは見られていない。(というか、まったく知られていないヒト、というべきかも知れないが)レコ-ドコレクタ-ズ誌の増刊として出された「英国ロックの深い森」なる書をひもといてみても、たった1ペ-ジを費やしての紹介文しか載っていない。
まあ、知名度から言ってその程度で満足すべきなのかも、だが、納得できないのは、彼を語るにおいて最重要作品といえる「ホ-ルディング・マイ・オウン」について一言も言及されていない事だ。
このアルバム、甘ったるいポップス歌手と思われがちな彼が、その「変化球ロッカ-」としての隠れた資質を全開させた隠れた名盤なのである。
かってアナログ盤時代に「男性自身」なるタイトルで日本盤も出たこの作品、浜辺で、海水パンツを流された男が恥ずかしそうに股間を抑えるジャケットのイラストが暗示するとおりの、なんと珍しい「艶笑ロック」アルバムなのだ。
「彼女はアスタ-であるものを失ってしまったのです。それはなにしろ若い女性にとっては大切なものでしたので、皆は大騒ぎ。それを奪ったのは彼女の家の運転手でしょうか、それとも庭番の男でしょうか?さまざまな男たちに疑いがかかりました。が、やがて彼女は思い出したのです。それを机の中に入れたまま忘れていた事を。これは、アスタ-で、あるものを無くしたと思い込んだ女の子の物語です」
こんな、意味ありげな歌詞を持つ歌ばかりが、キンクスのマスウェル・ヒルビリ-ズや、初期のニルソンあたりを連想させるノスタルジックな、かつブラックユ-モアの雰囲気仄かに漂うサウンドを伴って歌い次がれてゆく。その、気取りすました人間社会に向けた皮肉な視線が実に痛快だ。
このような洒落た、そして背後に「ロックの気骨」を濃厚に感じさせるアルバムを発表しているからこそ、スケラ-ンが、いくら「単なるポップ」なアルバムを連発しようと、私は彼を最後の一線で信ずる気になれるのだが・・・
スケラ-ンのために、そしてまだ未発達の「ロックの下半身」のために(?)、「男性自身」の、詳細な日本語訳詞付きのCD化再発を強く望むものである。