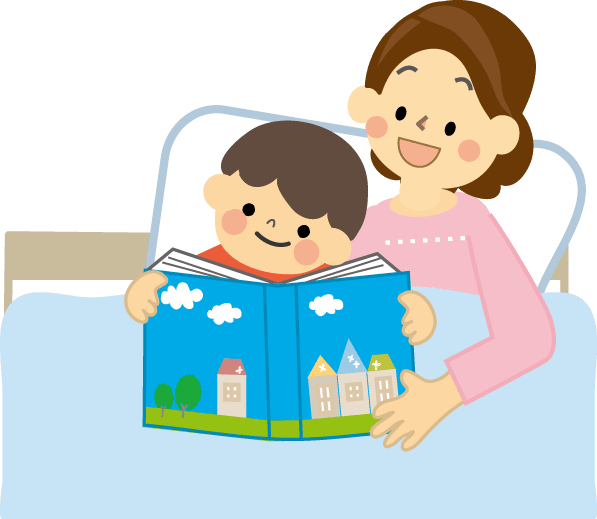6歳クラスがキッザニアへ卒園旅行にいくための寄付金活動として、テイクアウトのレストランをオープンしました。レストランの名前は、みんなで話し合って「JAF」(Jelly And Fried rice)に決めました。
前日にゼリーを作り、玉ねぎ21個、人参21本、ねぎ1パック、ソーセージ3.1キロを切って用意して、当日は朝からひたすらチャーハンを炒めました。約100食用意して各クラスの子どもたちに配達し、午後からは注文してくださった保護者の方たちに販売しました。
前日の準備では、"This is hard, but we can do it!" (大変だけど、がんばろう!)と子どもたちがお互いに励まし合いながらたくさんの材料を切り続けて準備をしました。毎年この根気強さと集中力に子どもたちの成長を感じますし、みんなでがんばってキッザニアに行こう!という気持ちになります。
当日の販売では、まだ桁の学習を初めて間がないので、お金の計算に戸惑う姿は見られましたが、お互いに助け合い、先生の援助も借りながらがんばっていました。算数の学習時だけではなく、遊びの中で培った力が活きていました。"Welcome to our restaurant!!"と大きな声でお客様たちを歓迎して、レジも商品を渡す係もそれぞれ一生懸命役割を果たしていました。
プレイハウスのペンキ塗りとレストランという2つの大きなプロジェクトをやり終えて、また成長した6歳クラスの子どもたちです。
前日にゼリーを作り、玉ねぎ21個、人参21本、ねぎ1パック、ソーセージ3.1キロを切って用意して、当日は朝からひたすらチャーハンを炒めました。約100食用意して各クラスの子どもたちに配達し、午後からは注文してくださった保護者の方たちに販売しました。
前日の準備では、"This is hard, but we can do it!" (大変だけど、がんばろう!)と子どもたちがお互いに励まし合いながらたくさんの材料を切り続けて準備をしました。毎年この根気強さと集中力に子どもたちの成長を感じますし、みんなでがんばってキッザニアに行こう!という気持ちになります。
当日の販売では、まだ桁の学習を初めて間がないので、お金の計算に戸惑う姿は見られましたが、お互いに助け合い、先生の援助も借りながらがんばっていました。算数の学習時だけではなく、遊びの中で培った力が活きていました。"Welcome to our restaurant!!"と大きな声でお客様たちを歓迎して、レジも商品を渡す係もそれぞれ一生懸命役割を果たしていました。
プレイハウスのペンキ塗りとレストランという2つの大きなプロジェクトをやり終えて、また成長した6歳クラスの子どもたちです。