いやぁ~、蒸し暑い日でした。
やはりこのくらい暑いと特産の八色スイカも格別です。魚沼の八色原で育てられるスイカは魚沼盆地特有の寒暖の差で、甘さ、みずみずしさは天下一品です。
今日はお盆前日・・・お葬式で遅れていた準備が急ぎで進められ、明朝、もう一踏ん張り必要ですが何とか間に合いそうです。
明日は境内中庭の池で灯籠を浮かべるのですが、平成16年の中越地震以降、池にヒビが入って水漏れが進み、今回は大がかりに修復して明日を迎える予定でした。
しかし、修復のフタをあけてみると、想像以上に水漏れが進んでおり、予定通りに修復が進んでいないのが現状です。明日は灯籠を浮かべるために池に水をはりますが、今後の本堂の建物への影響を考えると、もしかしたら池を壊さなければいけないかもしれません。
ほんのひとしずくでも、水の力は偉大です。
水は上から下に流れるのが自然の法則、それに逆らおうとする行いはいつまでも続くものではありませんね。
人間に例えると「上」とはご先祖や親、先輩などにあたります。
脈々と受け継がれてきたもの、「水」イコール「教え」は必ず下に流れます。その際に大切なのは「謙虚な心」です。自分自身を低く保たなければ水は決して流れて来ません。
これ、老僧から教えられたことです。

やはりこのくらい暑いと特産の八色スイカも格別です。魚沼の八色原で育てられるスイカは魚沼盆地特有の寒暖の差で、甘さ、みずみずしさは天下一品です。
今日はお盆前日・・・お葬式で遅れていた準備が急ぎで進められ、明朝、もう一踏ん張り必要ですが何とか間に合いそうです。

明日は境内中庭の池で灯籠を浮かべるのですが、平成16年の中越地震以降、池にヒビが入って水漏れが進み、今回は大がかりに修復して明日を迎える予定でした。
しかし、修復のフタをあけてみると、想像以上に水漏れが進んでおり、予定通りに修復が進んでいないのが現状です。明日は灯籠を浮かべるために池に水をはりますが、今後の本堂の建物への影響を考えると、もしかしたら池を壊さなければいけないかもしれません。
ほんのひとしずくでも、水の力は偉大です。
水は上から下に流れるのが自然の法則、それに逆らおうとする行いはいつまでも続くものではありませんね。

人間に例えると「上」とはご先祖や親、先輩などにあたります。
脈々と受け継がれてきたもの、「水」イコール「教え」は必ず下に流れます。その際に大切なのは「謙虚な心」です。自分自身を低く保たなければ水は決して流れて来ません。
これ、老僧から教えられたことです。













 どの季節も必要なもの、どれが良いとか悪いとかの概念ではありません。あくまでも自分の心次第といったところでしょうか・・・。
どの季節も必要なもの、どれが良いとか悪いとかの概念ではありません。あくまでも自分の心次第といったところでしょうか・・・。
 、魚沼盆地は他地域より湿度の多いところですが、それがまた美味しいお米や野菜を育てます。
、魚沼盆地は他地域より湿度の多いところですが、それがまた美味しいお米や野菜を育てます。


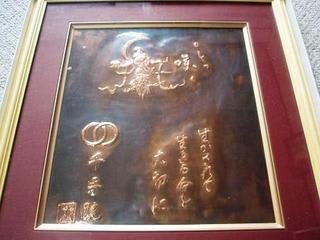




 と思ってここ数年過ごしています。
と思ってここ数年過ごしています。
 と言いたくなるものばかりです。
と言いたくなるものばかりです。