
人間と動物の関係をめぐる問題の広がりを描いてみたい。そのなかに、わたしたちのプロジェクトを位置づけるために。以下、2010年10月30日の研究会(桜美林・四ツ谷キャンパス)での奥野克巳による口頭発表(「人獣原論」)の概略(以下、文献表示省略)。
【1】動物の権利(アニマルライツ)を認める思想について。
その代表的な論者には、功利主義の立場のピーター・シンガー、権利論の立場のトム・リーガンがいる。シンガーは、利害の前提として、動物もまた、苦楽の感覚を持つ点から出発する。彼のいう平等の原理とは、同等の配慮の要求である。人間と動物をともに含む「最大多数の最大幸福」が目指されるべきだというのが、シンガーの主張である。リーガンは、動物も人間と同様に固有の価値をもっている点から出発する。生命の主体こそが、固有の価値の有無の基準であり、それは人間以外の動物の一部にも認めることができる。
【2】そうしたアニマルライツの思想の延長線上に、映画『ザ・コーヴ』がある。
この『ザ・コーヴ』という作品は、イルカ・クジラの保護を唱える点で一面的であり、単純すぎる。人間と自然の多様な関係性を、こんなにあっさりと切り捨ててしまうことはできない。全編をつうじて、太地町の人たちが描かれていないという印象がある。人間と自然をめぐるローカルな実践に届こうとさえしていない。動物の殺害とは、それなくしては、本来的には、人間が生きていくことができないものである。血の海の映像は、はたして、そうした覚悟の上でなされているのかどうかを、きちんと見極めるものとして扱われるべきである。
【3】いったい、動物の権利をめぐる議論は現在、どのあたりにまで広がっているのだろうか。
クッツェーの『動物のいのち』は、そのことを考えるためのよいテキストである。クッツェーの作品を批評する4人の専門家のうち、印象深い二つの意見を見てみよう。宗教史家、ウェンディ・ドニガーは、アングローサクソン的な議論を世界中にあてはめることはできないとして、インドにおける動物の扱いを取り上げ、最後に、アングローサクソンの動物愛好家の行き過ぎについて書いている。これは、人類学の行き方に近い。霊長類学者バーバラ・スマッツは、ヒヒやイヌとの交感をつうじて、動物も人間と同じように、社会的主体であり、個性をもった動物を、一個の主体として見ないのなら、人間のほうが「個性的存在性」を喪失することになるのだと述べている。
【4】舞台を日本に向けて、坂東眞砂子の「子猫殺し」について見てみよう。
タヒチ在住の直木賞作家・坂東眞砂子は、『日経新聞』「プロムナード」に、2006年8月18付で、「子猫殺し」と題するコラムを書いている。そのなかで、彼女は、飼い猫が生んだ子猫を崖から突き落として殺していると述べた。坂東によれば、メス猫の生にとって重要なことは、セックスをして子を産むことであり、飼い主の都合で避妊手術を施すことは、増えてゆく子猫に手を焼き、殺害しないためのふるまいである。彼女は、猫の生の充実を選んだ上で、痛みと悲しみを引き受けながら殺したのだと述べた。この記事に対しては、その後、動物愛護家から多数の批判が寄せられた。「子猫殺し」バッシングを経て、中村生雄は、言葉を喋って反論する人間の代わりとして、人はペットを溺愛するが、それと同時に、ペットへの愛情は洪水のように溢れかえり、人間のどうし愛情を不毛にし、砂漠化するのだという。人と動物の関係は、たんにその関係のあり方だけではなくて、人と人の関係を映し出している。
【5】動物愛護とは何なのだろうか?小林照幸『ドリームボックス:殺されてゆくペットたち』は、いたたまれない気持ちになるが、それを考えるための手がかりである。
・・・・今朝の殺処分状況を記す日報を開いたとき、机の電話が鳴った。(今日もまた 引き取り依頼の 電話かな)胸中で一句、詠んで史朗は電話に出た。老婦人の声。やはり、引き取りの依頼だった。同居していた息子夫婦が転勤で東京に引っ越した。引っ越し先のマンションでは犬が飼えないという。「息子夫婦から飼ってくれ、と頼まれたのだが、大きく杖をついて歩いている私たちでは、散歩にも連れだせないし、困って役所に相談したら、動物愛護センターがタダで引き取ってくれると教えられまして・・・」「犬も家族の一員です。新しい飼い主を探されましたでしょうか?」「いいえ。とにかく吠えるもので、なんとかして下さい。近所にも迷惑なんで」「役所からお聞きになっていると思いますが、センターで今日これから引き取れば、犬は明日の朝には呼吸をガスで止めて殺してしまいます。それでもよろしいですか?」「えっ、殺す?確か、そちらは、犬を引き取って面倒を見てくれる所じゃないのですか?愛護センターというじゃないですか」老婦人が攻撃的な口調になる・「私どもでは、負傷した動物を保護し、治療をしたりする活動もしていますが、犬や猫の引き取り、野良犬などの捕獲、殺処分と多岐の活動をしています」・・・・
【6】動物や生き物が見て、感じる世界とはどのようなものか。
手がかりは、ユクスキュルの「環世界」論である。日高敏隆によれば、「それぞれの動物、それぞれの主体となる動物は、まわりの環境の中から、自分にとって意味のあるものを認識し、その意味のあるものの組み合わせによって、自分たちの世界を構築しているのだ・・・・たとえば、美しい花が咲いていようと、それは彼らにとっては意味がない。食物としても敵としても意味のないそのようなものは、彼らの世界に存在しないのである。彼らにとって大切なのは、客観的な環境といわれているようなものではなくて、彼らという主体、この場合にはイモムシが、意味を与え、構築している世界なのである。それが大事なのだと、ユクスキュルはいう。ユクスキュルはこの世界のことを『環世界』、ウムヴェルト(Umwelt)と呼んだ。ウムは周りの、ヴェルトは世界である。つまり、彼らの周りの世界、ただ取り囲んでいるというのではなくて、彼ら主体が意味を与えて作り上げた世界なのであるということを、ユクスキュルは主張した」。
【7】ペット(愛玩動物)には人間と同等のあるいはそれ以上の価値が与えられる一方で、同じ動物でも、食用動物には、どんなに大量に殺害されようとも、憐れみがかけられることはないという点について考えてみたい。
内澤旬子の『世界屠畜紀行』には、ルポライターによる観察に基づいて、比較的小規模で手作業で行われる屠畜作業から工場畜産に至るまで、商業屠畜の詳細が示されている。わたしたちは、食用動物のと解体を、もっぱら、自分ではない他人にゆだねている。血や個体の死に接することなく、わたしたちは、肉を食べ、生き続けている。生き物としての動物は、現代社会では、遠い存在である。
【8】人は、原初において、動物をどのように狩猟し、その後、どのように動物の飼育に乗り出したのだろうか?
500万年ほど前、樹上から地上に降りたとき、周囲にはヒトの祖先を捕食する肉食獣がいた。人は、食べられる存在であった。彼らは、死肉をあさって、生き延びていたとされる。二足歩行によって、長距離を移動し肉にありつくようになったヒト科の祖先は、肉食をつうじて脳容量を増大させたのである。谷泰によれば、狩猟採集期を経て、その後、「牧畜の開始とともに、家畜化された動物種は、そのナチュラルな条件から引き離され、人の管理下で成長・繁殖し、人にとって優位な生活資源を、より安定的に供給する、人為的制限下におかれた存在となっている。しかもそれらが搾乳対象となり、人による接触や搾乳を許している姿を見るとき、牧畜とは、人の側からの一方的介入管理によって達成されているのでなく、野生段階では許容しなかったはずの介入を動物の側が許容する、いわば動物の側での対応的変化を伴う・・・・このような条件下で、ひとは、対象動物の個体維持に必要な摂食活動、また群の再生維持にかかわる生殖・出産・育児といった、本来的な諸活動のある特定の項に、一連の慣習的、かつプログラム化され技術的関与を行うことで、狩猟段階よりも効率よく、安定した資源獲得に成功している。家畜化とは、まさに介入と介入許容という相互的すり合わせを通じて、一連の人為的技術行為の連鎖のなかに、当該の動物種を、自発性を維持しつつ、組み入れることであり、牧畜とは、そのような一連の技術的介入を通じて、当動物から生活資源を恒常的に取得する生業技術体系だといえる」と述べている。
【9】アイヌのイヨマンテ(熊送り儀礼)を取り上げて、人がどのように動物に向き合ってきたのかについて考えてみたい。
イヨマンテでは、熊をいつくしんで飼い育てて殺すという点で、一見、残酷であるように思える。しかし、実は、それは、わたしたち人間誰しもが、生きていく上でやらなければ生きていけない事柄を拡大(誇張)して見せてくれている。イヨマンテの背後には、アイヌの人たちは、熊が神の化身であり、自然=神が人に対して純粋に贈与をしてくれているというコスモロジーを用意している。イヨマンテを残酷だ、野蛮だというのは、ただ、うわべだけを見ているからであり、事柄の本質を見ようとするならば、生きた動物を殺害するためだけに育てて、それを血のしぶきを上げさせて切り刻んだ後に売買し、生命ある存在物に対して何も感じないという点で、わたしたちのほうこそ、野蛮なのではあるまいかという見方が成り立つのかもしれない。
【10】動物とヒトのあいだで確立されてきたヒト中心主義とは何か?
いままで世界を制覇して、いまもグローバル化の中でいちばん力をもっている一神教的人間中心主義(「創世記パラダイム」)を川田順造は攻撃する。「自己中心主義」「自民族中心主義」「地球中心主義=天動説」というような狭隘なセントリズムは、これまで、ヒトの聡明さによって否定されてきた。次に乗り越えなければならないのは、西洋近代を支えてきたヒト中心主義であることを、川田は強調する。そのために、ヒトの快適さのためにではなく、ヒトとヒト以外の生物の間にあるべき掟を探る努力をすること、つまり、「種間倫理(interspecific ethics)」を探求することこそが、わたしたちの最重要課題となるという。他方で、中沢新一は、人間の思考を、「対称性の論理」である神話的な思考から、「非対称性の論理」であるアリストテレス型の論理や一神教的(=キリスト教的)な形而上学が未分化であった時代にまでさかのぼって、ホモサピエンスの「心」の基体にまで純化させた上で、語りはじめる。中沢は、それを、わたしたちが真正面から取り組むべき課題として指し示すのではなく、レヴィ=ストロースの流れを汲みながら、それ(=「創世記パラダイム」)が、抑圧してしまったのだけれども、不動の作動を続けている基体(=「対称性の論理」)との関わりのなかで明らかにしようとする。
【11】先住民社会における動物観(自然観)は、西欧のヒト中心主義よりましであるとして、非西洋をロマン化することに対しては慎重であったほうがいいかもしれないという意見がある。
マット・リドレーによれば、「インディアンは自然を崇拝し、慎み深く、自然と一体となって暮らしていたというのが通説である。自然と神秘的な調和を保ち、獲物のストックを減らさぬよう、むやみやたら動物を殺すようなことは決してなかった、と信じられてきた。だが発掘現場からの証拠は、このような心温まる神話に疑問を投げかけている。オオカミは年老いた動物、あるいは非常に若い動物を主に狙うが、インディアンが殺すのは一番元気のいいヘラジカばかりである。雄牛よりも雌牛のほうがはるかに殺される確率が高く、現在のヘラジカの寿命よりも長生きできたヘラジカはごくわずかであった。北アメリカ先住民が大きな獲物を保護していたという証拠はまったくないと、生態学者のチャールズ・ケイは結論している。実際、現在の植生と昔の植生の比較に基づいて彼が論じているところによれば、コロンブスが上陸する以前、インディアンはロッキー山脈地帯の広い領域においてヘラジカを絶滅寸前に追い込んでいたというのだ」。「人間は環境保護思想を本能的には備えていない、つまり、行動を抑制したり、抑制を教える傾向を生まれつき持っているわけではないというのが信頼のおける結論である。したがって、環境保護思想は、本来、人間の本性とは相いれないものであり、本性に逆らって教えこまなければならないものなのである。生まれつきそのような道徳観念が備わっているわけではない。そんなことはとうに分かっていたことではないか、それでもなお、われわれは正しいスローガンや呪文をとなえる生態学的な意味における高潔な野人がいるはずだという希望にすがりついているのである。高潔な野人はわれわれの内部には存在しない」。オーバーキル仮説と伝統的民族知識(Traditional Ecological Knowledge)のどちらが正しいのかという問いは不毛であるように思われるが、こういった意見にも耳を傾けてみる必要がある。
【12】川田順造のいう、アニミズムなどに裏打ちされるような、間世界のものを人間による比ゆ的な投影で擬人化し、それに働きかけたり、それにお供えをしたりして願い事をするような「汎生的世界像」として、日本社会のあちこちに見られる「獣魂碑」「鳥獣供養塔」などの現象について、その広がりと意義を押さえてゆかなければらない。
http://blog.goo.ne.jp/katsumiokuno/e/55a35983e5e790fa493d6a3f8fb3d757
【13】はたして、人類学は、人と動物の関係について、どういった問題提起をすることができるのだろうか?
ハウェルによれば、マレー半島のチュウォン人(Chewong)社会には、意識の存在と不在によって構成されるある存在のクラスがある。外見が、テナガザルであれ、人であれ、ノブタ、カエル、ランブータン、果実、竹の皮、雷や特定の巨石であれ、意識はひとつの「人格」をつくりあげる。ヴィヴェイロス・デ・カストロは、こうした先住民社会の動物観は、大きな意味での「観点主義」に含まれるとみなすことができるという。「観点」を有することによって、全ての存在(人間、動物、精霊など)が主体となりうるという考え方は、わたしたちが人だけを入れている「社会」という集合からはみ出てしまう。「社会」概念は、基本的には、人によって構成されるということしか想定されていないからである。「コレクティヴ」という概念は、それに代えて、人間、動物、精霊を一つの集合のなかに含むために案出された概念である。わたしたちは、人間だけが社会をつくっていると考えてきた。人間だけが社会的存在であり、社会は、自然から切り離された、精神活動を行う人間のものであると考えられてきた。ラトゥールは、こうした西洋思考に挑戦する。人間を含めて動物、植物、地形や気象などの無生物が、同等の存在であるという視点を導入することによって、既存の「社会」概念を組み替えることで、人類学から、新たな人間観を発信しようとしている。
【14】動物と人間の関係をめぐって、日本の人類学者はどのような貢献をしてきたのであろうか。
【15】最後に、これだけでは、人間と動物の問題の現在について、まだまだ網羅的ではあるまい。
トーテミズム、動物憑依、異類婚姻譚などの動物と人間との関わりをめぐる民話、神話や伝承の類、ヨーロッパ中世の動物裁判に比することができる現代日本における「アマミノクロウサギ」や「ジュゴン」を原告とした裁判など、ペットロス、ペット葬、withペット墓などのペットをめぐる諸問題、生物多様性条約のなかの動物保護と動物資源の活用などなど、いくらでも検討項目を増やすことができるだろう。増やせばいいというものでもないのかもしれないが、人間と動物の問題を考える射程を知るために、とりあえずの試みとして。I先生は、わたしの口頭発表を聞いて、全体をつうじて、他者としての動物が、わたしたちの日常のなかに深く入り込んできたということではないかという感想を述べられた。そういった事態が、目の前にあるのだ。今日、動物が、わたしたちの大きな関心事になりつつある。
【1】動物の権利(アニマルライツ)を認める思想について。
その代表的な論者には、功利主義の立場のピーター・シンガー、権利論の立場のトム・リーガンがいる。シンガーは、利害の前提として、動物もまた、苦楽の感覚を持つ点から出発する。彼のいう平等の原理とは、同等の配慮の要求である。人間と動物をともに含む「最大多数の最大幸福」が目指されるべきだというのが、シンガーの主張である。リーガンは、動物も人間と同様に固有の価値をもっている点から出発する。生命の主体こそが、固有の価値の有無の基準であり、それは人間以外の動物の一部にも認めることができる。
【2】そうしたアニマルライツの思想の延長線上に、映画『ザ・コーヴ』がある。
この『ザ・コーヴ』という作品は、イルカ・クジラの保護を唱える点で一面的であり、単純すぎる。人間と自然の多様な関係性を、こんなにあっさりと切り捨ててしまうことはできない。全編をつうじて、太地町の人たちが描かれていないという印象がある。人間と自然をめぐるローカルな実践に届こうとさえしていない。動物の殺害とは、それなくしては、本来的には、人間が生きていくことができないものである。血の海の映像は、はたして、そうした覚悟の上でなされているのかどうかを、きちんと見極めるものとして扱われるべきである。
【3】いったい、動物の権利をめぐる議論は現在、どのあたりにまで広がっているのだろうか。
クッツェーの『動物のいのち』は、そのことを考えるためのよいテキストである。クッツェーの作品を批評する4人の専門家のうち、印象深い二つの意見を見てみよう。宗教史家、ウェンディ・ドニガーは、アングローサクソン的な議論を世界中にあてはめることはできないとして、インドにおける動物の扱いを取り上げ、最後に、アングローサクソンの動物愛好家の行き過ぎについて書いている。これは、人類学の行き方に近い。霊長類学者バーバラ・スマッツは、ヒヒやイヌとの交感をつうじて、動物も人間と同じように、社会的主体であり、個性をもった動物を、一個の主体として見ないのなら、人間のほうが「個性的存在性」を喪失することになるのだと述べている。
【4】舞台を日本に向けて、坂東眞砂子の「子猫殺し」について見てみよう。
タヒチ在住の直木賞作家・坂東眞砂子は、『日経新聞』「プロムナード」に、2006年8月18付で、「子猫殺し」と題するコラムを書いている。そのなかで、彼女は、飼い猫が生んだ子猫を崖から突き落として殺していると述べた。坂東によれば、メス猫の生にとって重要なことは、セックスをして子を産むことであり、飼い主の都合で避妊手術を施すことは、増えてゆく子猫に手を焼き、殺害しないためのふるまいである。彼女は、猫の生の充実を選んだ上で、痛みと悲しみを引き受けながら殺したのだと述べた。この記事に対しては、その後、動物愛護家から多数の批判が寄せられた。「子猫殺し」バッシングを経て、中村生雄は、言葉を喋って反論する人間の代わりとして、人はペットを溺愛するが、それと同時に、ペットへの愛情は洪水のように溢れかえり、人間のどうし愛情を不毛にし、砂漠化するのだという。人と動物の関係は、たんにその関係のあり方だけではなくて、人と人の関係を映し出している。
【5】動物愛護とは何なのだろうか?小林照幸『ドリームボックス:殺されてゆくペットたち』は、いたたまれない気持ちになるが、それを考えるための手がかりである。
・・・・今朝の殺処分状況を記す日報を開いたとき、机の電話が鳴った。(今日もまた 引き取り依頼の 電話かな)胸中で一句、詠んで史朗は電話に出た。老婦人の声。やはり、引き取りの依頼だった。同居していた息子夫婦が転勤で東京に引っ越した。引っ越し先のマンションでは犬が飼えないという。「息子夫婦から飼ってくれ、と頼まれたのだが、大きく杖をついて歩いている私たちでは、散歩にも連れだせないし、困って役所に相談したら、動物愛護センターがタダで引き取ってくれると教えられまして・・・」「犬も家族の一員です。新しい飼い主を探されましたでしょうか?」「いいえ。とにかく吠えるもので、なんとかして下さい。近所にも迷惑なんで」「役所からお聞きになっていると思いますが、センターで今日これから引き取れば、犬は明日の朝には呼吸をガスで止めて殺してしまいます。それでもよろしいですか?」「えっ、殺す?確か、そちらは、犬を引き取って面倒を見てくれる所じゃないのですか?愛護センターというじゃないですか」老婦人が攻撃的な口調になる・「私どもでは、負傷した動物を保護し、治療をしたりする活動もしていますが、犬や猫の引き取り、野良犬などの捕獲、殺処分と多岐の活動をしています」・・・・
【6】動物や生き物が見て、感じる世界とはどのようなものか。
手がかりは、ユクスキュルの「環世界」論である。日高敏隆によれば、「それぞれの動物、それぞれの主体となる動物は、まわりの環境の中から、自分にとって意味のあるものを認識し、その意味のあるものの組み合わせによって、自分たちの世界を構築しているのだ・・・・たとえば、美しい花が咲いていようと、それは彼らにとっては意味がない。食物としても敵としても意味のないそのようなものは、彼らの世界に存在しないのである。彼らにとって大切なのは、客観的な環境といわれているようなものではなくて、彼らという主体、この場合にはイモムシが、意味を与え、構築している世界なのである。それが大事なのだと、ユクスキュルはいう。ユクスキュルはこの世界のことを『環世界』、ウムヴェルト(Umwelt)と呼んだ。ウムは周りの、ヴェルトは世界である。つまり、彼らの周りの世界、ただ取り囲んでいるというのではなくて、彼ら主体が意味を与えて作り上げた世界なのであるということを、ユクスキュルは主張した」。
【7】ペット(愛玩動物)には人間と同等のあるいはそれ以上の価値が与えられる一方で、同じ動物でも、食用動物には、どんなに大量に殺害されようとも、憐れみがかけられることはないという点について考えてみたい。
内澤旬子の『世界屠畜紀行』には、ルポライターによる観察に基づいて、比較的小規模で手作業で行われる屠畜作業から工場畜産に至るまで、商業屠畜の詳細が示されている。わたしたちは、食用動物のと解体を、もっぱら、自分ではない他人にゆだねている。血や個体の死に接することなく、わたしたちは、肉を食べ、生き続けている。生き物としての動物は、現代社会では、遠い存在である。
【8】人は、原初において、動物をどのように狩猟し、その後、どのように動物の飼育に乗り出したのだろうか?
500万年ほど前、樹上から地上に降りたとき、周囲にはヒトの祖先を捕食する肉食獣がいた。人は、食べられる存在であった。彼らは、死肉をあさって、生き延びていたとされる。二足歩行によって、長距離を移動し肉にありつくようになったヒト科の祖先は、肉食をつうじて脳容量を増大させたのである。谷泰によれば、狩猟採集期を経て、その後、「牧畜の開始とともに、家畜化された動物種は、そのナチュラルな条件から引き離され、人の管理下で成長・繁殖し、人にとって優位な生活資源を、より安定的に供給する、人為的制限下におかれた存在となっている。しかもそれらが搾乳対象となり、人による接触や搾乳を許している姿を見るとき、牧畜とは、人の側からの一方的介入管理によって達成されているのでなく、野生段階では許容しなかったはずの介入を動物の側が許容する、いわば動物の側での対応的変化を伴う・・・・このような条件下で、ひとは、対象動物の個体維持に必要な摂食活動、また群の再生維持にかかわる生殖・出産・育児といった、本来的な諸活動のある特定の項に、一連の慣習的、かつプログラム化され技術的関与を行うことで、狩猟段階よりも効率よく、安定した資源獲得に成功している。家畜化とは、まさに介入と介入許容という相互的すり合わせを通じて、一連の人為的技術行為の連鎖のなかに、当該の動物種を、自発性を維持しつつ、組み入れることであり、牧畜とは、そのような一連の技術的介入を通じて、当動物から生活資源を恒常的に取得する生業技術体系だといえる」と述べている。
【9】アイヌのイヨマンテ(熊送り儀礼)を取り上げて、人がどのように動物に向き合ってきたのかについて考えてみたい。
イヨマンテでは、熊をいつくしんで飼い育てて殺すという点で、一見、残酷であるように思える。しかし、実は、それは、わたしたち人間誰しもが、生きていく上でやらなければ生きていけない事柄を拡大(誇張)して見せてくれている。イヨマンテの背後には、アイヌの人たちは、熊が神の化身であり、自然=神が人に対して純粋に贈与をしてくれているというコスモロジーを用意している。イヨマンテを残酷だ、野蛮だというのは、ただ、うわべだけを見ているからであり、事柄の本質を見ようとするならば、生きた動物を殺害するためだけに育てて、それを血のしぶきを上げさせて切り刻んだ後に売買し、生命ある存在物に対して何も感じないという点で、わたしたちのほうこそ、野蛮なのではあるまいかという見方が成り立つのかもしれない。
【10】動物とヒトのあいだで確立されてきたヒト中心主義とは何か?
いままで世界を制覇して、いまもグローバル化の中でいちばん力をもっている一神教的人間中心主義(「創世記パラダイム」)を川田順造は攻撃する。「自己中心主義」「自民族中心主義」「地球中心主義=天動説」というような狭隘なセントリズムは、これまで、ヒトの聡明さによって否定されてきた。次に乗り越えなければならないのは、西洋近代を支えてきたヒト中心主義であることを、川田は強調する。そのために、ヒトの快適さのためにではなく、ヒトとヒト以外の生物の間にあるべき掟を探る努力をすること、つまり、「種間倫理(interspecific ethics)」を探求することこそが、わたしたちの最重要課題となるという。他方で、中沢新一は、人間の思考を、「対称性の論理」である神話的な思考から、「非対称性の論理」であるアリストテレス型の論理や一神教的(=キリスト教的)な形而上学が未分化であった時代にまでさかのぼって、ホモサピエンスの「心」の基体にまで純化させた上で、語りはじめる。中沢は、それを、わたしたちが真正面から取り組むべき課題として指し示すのではなく、レヴィ=ストロースの流れを汲みながら、それ(=「創世記パラダイム」)が、抑圧してしまったのだけれども、不動の作動を続けている基体(=「対称性の論理」)との関わりのなかで明らかにしようとする。
【11】先住民社会における動物観(自然観)は、西欧のヒト中心主義よりましであるとして、非西洋をロマン化することに対しては慎重であったほうがいいかもしれないという意見がある。
マット・リドレーによれば、「インディアンは自然を崇拝し、慎み深く、自然と一体となって暮らしていたというのが通説である。自然と神秘的な調和を保ち、獲物のストックを減らさぬよう、むやみやたら動物を殺すようなことは決してなかった、と信じられてきた。だが発掘現場からの証拠は、このような心温まる神話に疑問を投げかけている。オオカミは年老いた動物、あるいは非常に若い動物を主に狙うが、インディアンが殺すのは一番元気のいいヘラジカばかりである。雄牛よりも雌牛のほうがはるかに殺される確率が高く、現在のヘラジカの寿命よりも長生きできたヘラジカはごくわずかであった。北アメリカ先住民が大きな獲物を保護していたという証拠はまったくないと、生態学者のチャールズ・ケイは結論している。実際、現在の植生と昔の植生の比較に基づいて彼が論じているところによれば、コロンブスが上陸する以前、インディアンはロッキー山脈地帯の広い領域においてヘラジカを絶滅寸前に追い込んでいたというのだ」。「人間は環境保護思想を本能的には備えていない、つまり、行動を抑制したり、抑制を教える傾向を生まれつき持っているわけではないというのが信頼のおける結論である。したがって、環境保護思想は、本来、人間の本性とは相いれないものであり、本性に逆らって教えこまなければならないものなのである。生まれつきそのような道徳観念が備わっているわけではない。そんなことはとうに分かっていたことではないか、それでもなお、われわれは正しいスローガンや呪文をとなえる生態学的な意味における高潔な野人がいるはずだという希望にすがりついているのである。高潔な野人はわれわれの内部には存在しない」。オーバーキル仮説と伝統的民族知識(Traditional Ecological Knowledge)のどちらが正しいのかという問いは不毛であるように思われるが、こういった意見にも耳を傾けてみる必要がある。
【12】川田順造のいう、アニミズムなどに裏打ちされるような、間世界のものを人間による比ゆ的な投影で擬人化し、それに働きかけたり、それにお供えをしたりして願い事をするような「汎生的世界像」として、日本社会のあちこちに見られる「獣魂碑」「鳥獣供養塔」などの現象について、その広がりと意義を押さえてゆかなければらない。
http://blog.goo.ne.jp/katsumiokuno/e/55a35983e5e790fa493d6a3f8fb3d757
【13】はたして、人類学は、人と動物の関係について、どういった問題提起をすることができるのだろうか?
ハウェルによれば、マレー半島のチュウォン人(Chewong)社会には、意識の存在と不在によって構成されるある存在のクラスがある。外見が、テナガザルであれ、人であれ、ノブタ、カエル、ランブータン、果実、竹の皮、雷や特定の巨石であれ、意識はひとつの「人格」をつくりあげる。ヴィヴェイロス・デ・カストロは、こうした先住民社会の動物観は、大きな意味での「観点主義」に含まれるとみなすことができるという。「観点」を有することによって、全ての存在(人間、動物、精霊など)が主体となりうるという考え方は、わたしたちが人だけを入れている「社会」という集合からはみ出てしまう。「社会」概念は、基本的には、人によって構成されるということしか想定されていないからである。「コレクティヴ」という概念は、それに代えて、人間、動物、精霊を一つの集合のなかに含むために案出された概念である。わたしたちは、人間だけが社会をつくっていると考えてきた。人間だけが社会的存在であり、社会は、自然から切り離された、精神活動を行う人間のものであると考えられてきた。ラトゥールは、こうした西洋思考に挑戦する。人間を含めて動物、植物、地形や気象などの無生物が、同等の存在であるという視点を導入することによって、既存の「社会」概念を組み替えることで、人類学から、新たな人間観を発信しようとしている。
【14】動物と人間の関係をめぐって、日本の人類学者はどのような貢献をしてきたのであろうか。
【15】最後に、これだけでは、人間と動物の問題の現在について、まだまだ網羅的ではあるまい。
トーテミズム、動物憑依、異類婚姻譚などの動物と人間との関わりをめぐる民話、神話や伝承の類、ヨーロッパ中世の動物裁判に比することができる現代日本における「アマミノクロウサギ」や「ジュゴン」を原告とした裁判など、ペットロス、ペット葬、withペット墓などのペットをめぐる諸問題、生物多様性条約のなかの動物保護と動物資源の活用などなど、いくらでも検討項目を増やすことができるだろう。増やせばいいというものでもないのかもしれないが、人間と動物の問題を考える射程を知るために、とりあえずの試みとして。I先生は、わたしの口頭発表を聞いて、全体をつうじて、他者としての動物が、わたしたちの日常のなかに深く入り込んできたということではないかという感想を述べられた。そういった事態が、目の前にあるのだ。今日、動物が、わたしたちの大きな関心事になりつつある。










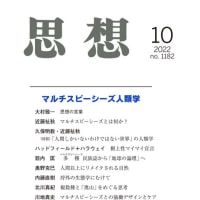

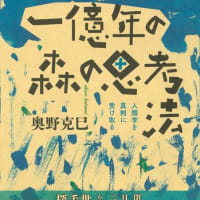
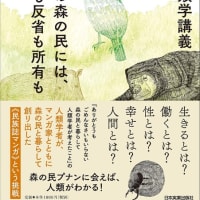



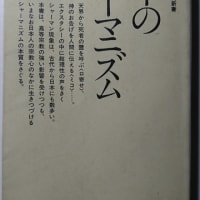


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます