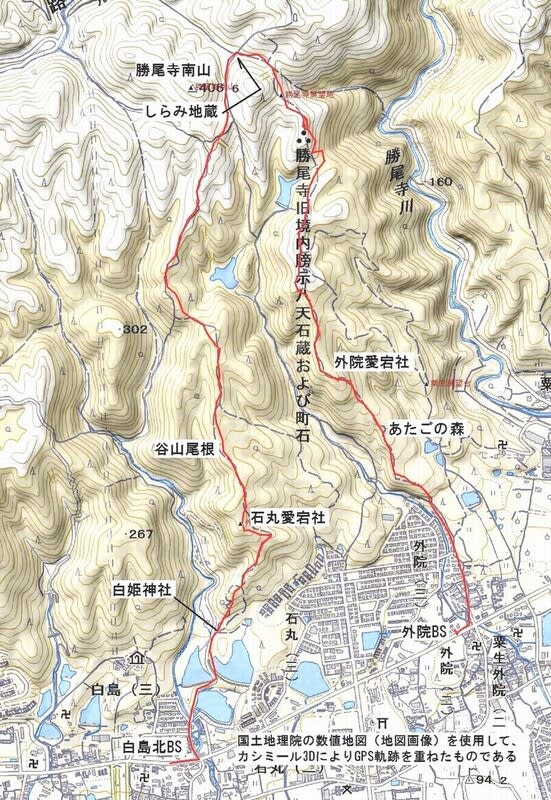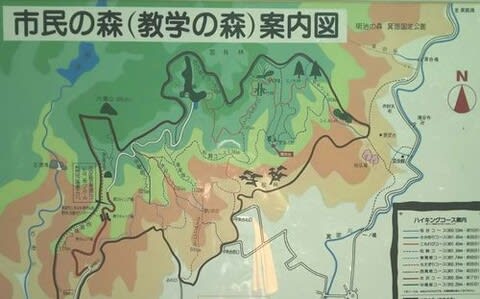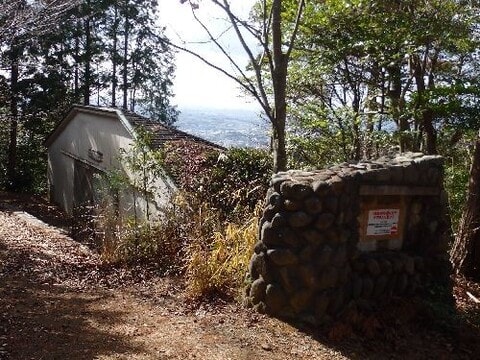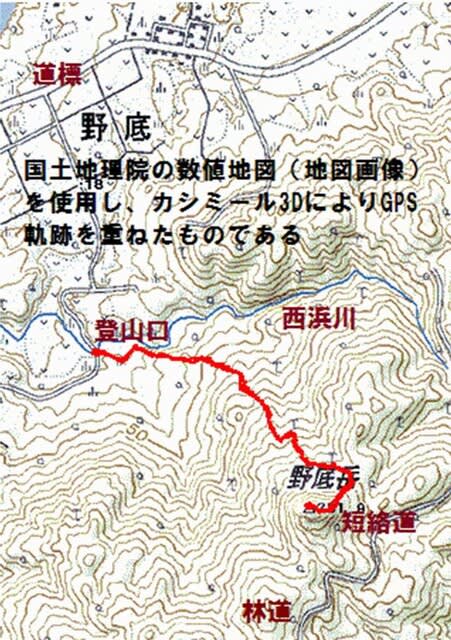淀川土手から見る大日トリプルタワーと生駒山

淀川堤防際にある浄土真宗本願寺派の阿弥陀寺
美しい庭園に親鸞聖人と写真左に寺西沖乃の歌碑がありました。
美しい庭園に親鸞聖人と写真左に寺西沖乃の歌碑がありました。

北に少し歩くと「うきうき歴史街道 別府・一津屋コース」の始点が…
別府を通って新幹線公園まで続いています。
別府を通って新幹線公園まで続いています。

水路を行くと味生(あじふ)神社が

宮ノ下渡し跡の説明板

コースは水路を真直ぐ西へ行くようですが、右に曲がりました。

淀川土手からは願正寺が見えていますが、境内には入れませんでした。

藤森神社ですが…工事中で残念

新幹線の西の三箇牧水路行く途中にあった「摂津ふれあいの里」
ここは阪急バスの停留所で、横には鳥飼水路が流れています。
ここは阪急バスの停留所で、横には鳥飼水路が流れています。
右の石柱には「此付近鳥養院址」、左の歌碑には「あさみどり
かひある春に あひぬれば かすみならねど たちのぼりけり」。

離宮「鳥養院」の址の説明板

安威川新橋手前の三箇牧水路


中央に仕切りがあり、左排水・右用水に分けています。
番田井路の隔流壁(水路の保守用と推測)とは意味が違います。
番田井路の隔流壁(水路の保守用と推測)とは意味が違います。

水路は道路の下を潜って番田井路につながっています。

玉川の里を流れる番田井路に着きました。
道は水路沿いと土手上と二つに分かれますが、水路側を歩きました。
春には桜並木を楽しめそうです。
道は水路沿いと土手上と二つに分かれますが、水路側を歩きました。
春には桜並木を楽しめそうです。