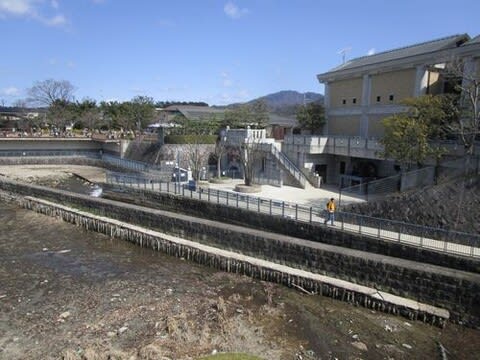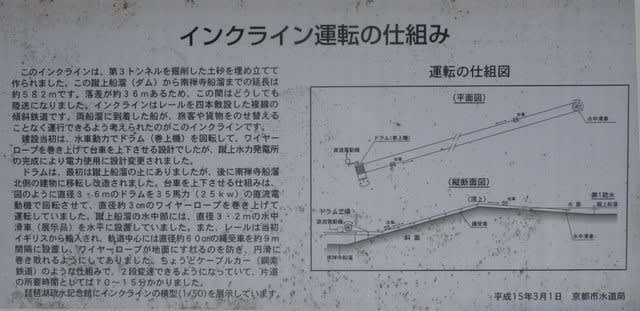よく行く京都府立植物園から帰る途中、船岡山の傍を通るのでいつか寄りたいと思っていました。
本日船岡山に参詣してのち展望台に登り、東山から西山の展望を楽しんできました。(2020.09.28)

JR二条城から線路沿いに北上すると平安宮豊楽殿跡がありました。

七本松通リを北上すると日蓮宗本山立本寺(りゅうほんじ)がありました。
桜と蓮の名所で、歴史あるお寺のようです。

さらに七本松通リを北上、一条通リと交差するところに賑やかな一画がありました。
出雲ノ阿国・ 歌舞伎発祥の地、七本松通リ名発祥ノ地、宮本武蔵と吉岡一門の決闘ノ地 、
チンチン電車(旧市電北野車庫)などにぎやかな一角です。

上七軒歌舞練場を通リ、北野天満宮にお参りしてきました。

拝殿(国宝)

天神川を渡ると平野神社の大鳥居が

2018年台風21号による被害からの復興中の拝殿

船岡山に向かう途中、紫野の御土居(おどい)がありました。
京都の町外周に築いた豊臣時代の土手・塀のことで、外敵および水害から町を守った、とのこと。
御土居の内を洛内、外を洛外と言ったそうです。

建勲神社にお参りしてから展望広場にある東屋へ

船岡山の山頂、煙突のような構造物は戦時中の遺物で、サイレン塔というらしいです。

建勲神社石段から見る比叡山、大文字山です。 大きく見る: 拡大

山頂より、稲荷山~生駒山~小塩山の展望 大きく見る: 拡大

愛宕山と左大文字も見れました。