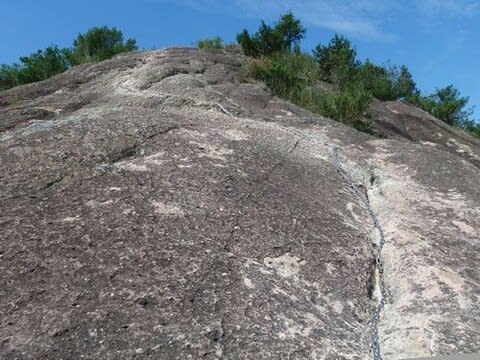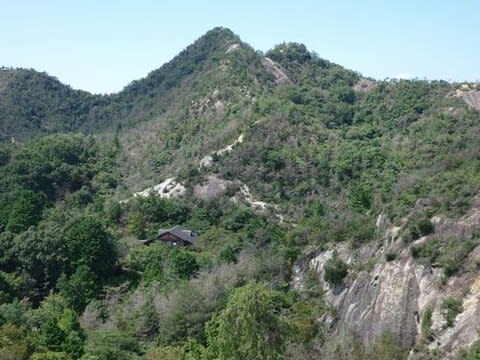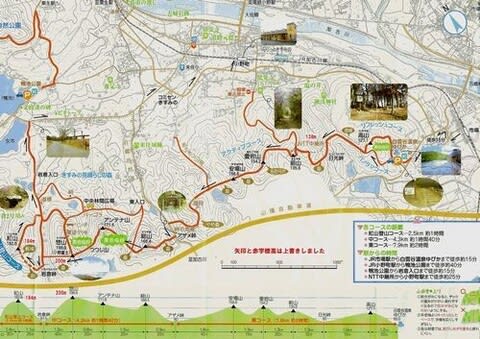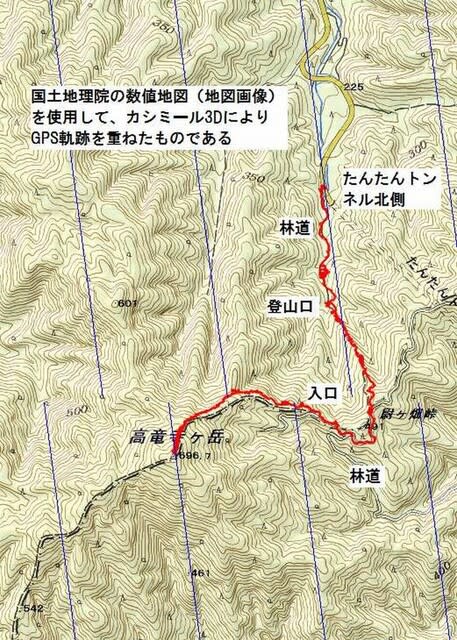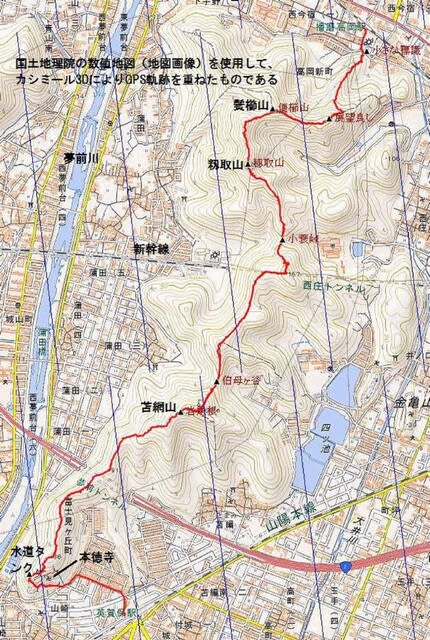「播磨に面白い岩山がある」と山友達に誘われて、三草アルプス・数曽寺


加東市山口の公民館前の私道手前に駐車
今日は天気も良くて風もなく絶好の登山日和となりそうです。
今日は天気も良くて風もなく絶好の登山日和となりそうです。

ケルンのあるP186ピークを過ぎて馬の背を快適に歩きます。
播磨アルプス(高御位山)に比べ、この山はスラブ尾根が広範囲に亘り、
播磨アルプス(高御位山)に比べ、この山はスラブ尾根が広範囲に亘り、
望もアルプスを想わせるものがあります。
藪も谷もあり変化に富んだ山行ができました。
藪も谷もあり変化に富んだ山行ができました。


P298を過ぎると、小さいながらも少し緊張するキレットがありました。


その間に架かる明石海峡大橋、さらにその右には淡路島が

展望が良すぎて時間を食ったので、大坂山は寄らずに数曽寺峠から谷
を下ることにしました。(写真はWEBから借用)
岩尾根とは違ってこの谷道は、穏やかで森林浴がたのしめました。
岩尾根とは違ってこの谷道は、穏やかで森林浴がたのしめました。

数曽寺池に下山
対岸には別荘地が並び、ちょっとエキゾチックな感じでした。
対岸には別荘地が並び、ちょっとエキゾチックな感じでした。