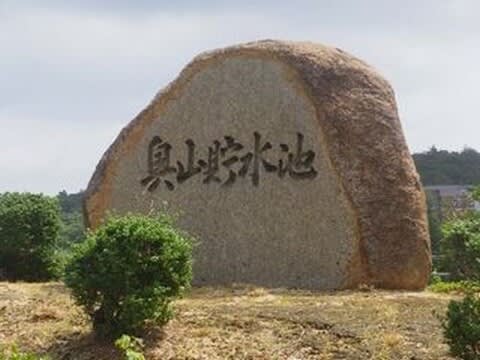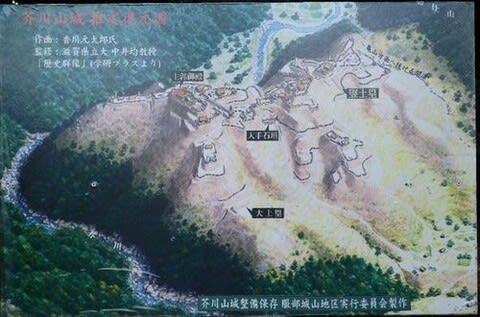まだまだ極暑が続くなか、涼を求めて六甲高山植物園に行ってきました。(2017.08.24)
四国剣山で見ることができなかった、キレンゲショウマに出会えたのは収穫でした。
四国剣山で見ることができなかった、キレンゲショウマに出会えたのは収穫でした。

六甲高山植物園
平均気温9度という北海道並の気温で、牧野富太郎博士の指導を受けて1933年に開園
スイスのインターラーケンにある高山植物園と姉妹提携をした由緒ある高山植物園です。
平均気温9度という北海道並の気温で、牧野富太郎博士の指導を受けて1933年に開園
スイスのインターラーケンにある高山植物園と姉妹提携をした由緒ある高山植物園です。

四国剣山で見ることができなかった、キレンゲショウマの群落に逢えて感激
キレンゲショウマは、剣山を舞台にした宮尾登美子著「天涯の花」で有名です。
キレンゲショウマは、剣山を舞台にした宮尾登美子著「天涯の花」で有名です。

カノコユリ 白地に赤(色違いですが)の斑点がら鹿の子模様の意でこの名が
花の中央部をよく見ると白い棘状の突起があり先端が赤いようです。
花の中央部をよく見ると白い棘状の突起があり先端が赤いようです。

フシグロセンノウ 田中澄江著「花の百名山」で紹介している高山の花です。

珍しい燕の尾、エンビセンノウ 北海道と本州中部のごく一部に分布
山野の草原に自生するようです。

ゲンノショウコ(フウロソウ科)?

サギソウ、鉢植えが展示、地植えも数株ありました。

レンゲショウマはキンポウゲ科、かわいい清楚な花の群落がありました。
先のキレンゲショウマはユキノシタ科です。
先のキレンゲショウマはユキノシタ科です。

ヒヨドリバナ、フジバカマとの違いが分かりません。

アサマフウロ、きれいで鮮やかな花が印象的

ハマナス、実は食べられるそうです。
ナシの味からハマナシ、訛ってハマナスになったとか。

おなじみのツリガネニンジン

ヤマハハコ

センニンソウ、近くの山野で密生した花をよく見かけます。

シラヒゲソウ、ウメバチソウ科らしいですが想像できません。
(ヒゲが出ていないとき見たいです)
(ヒゲが出ていないとき見たいです)

マツムシソウ

シモツケソウ?

ハナトラノオ、街中でよく見かけます。

調べましたがわかりません。

ミソハギ、湿地帯で群生しているのをよく見かけます。

ホツツジ

群落をよく見かけるキツリフネ、六甲山上で一時の涼に浸ってきました。