
この写真は横で撮ったものを縦にトリミングしてあります。
だって、鹿が動くもんだから、思い通りの構図で撮れなかった。
考えてみたら本格的な写真展を見るのは初めてなのだ。
一眼レフ始めるまでは人の写真なんか興味もなかったし。
入江泰吉・土門拳 二人展
二人はほぼ同時代(明治の終わりから昭和いっぱい)を生きて、同じくらい長く生きて、死ぬまで写真を撮り続けた。
二人とも初めは画家を志したが挫折、写真に転向している。
二人の余技として、油絵、木彫りや篆刻が展示されていて、これも興味深かった。
泰吉愛用のカメラも3台並んでいて、今まで、カメラそのものなんて興味もなかったのに、しげしげと見入ってしまった。
最晩年まで愛用のミノルタはグリップ?のゴム部分が磨り減ってるように見えた。
入江泰吉も土門拳も、もちろん名前や概略は知っていたけど、
写真はカレンダーで見たかなというくらいのもん。
見るまではきっと入江泰吉のほうが好きだろうと思っていた。
だって土門拳のイメージってなんかアニマル浜口みたいくない?
どういう連想や?ほんの気まぐれの思いつきだけど。
リアルで、直接的で、暑苦しそうな感じで、名前からしてインパクト在り過ぎ。
ひところ流行った言い回しで言えば土門はソース顔で、入江泰吉がショーユ顔か。
同じ仏像や建築物を撮った写真を比べたら違いが歴然とする。
展示室に入ってしばらくは気付かなかったが額装も違う。
入江は細い黒枠に白マット。
土門はマット無しで広幅の木枠。
この額がなくても名前を消してても、たぶん二人の写真はほとんどわかると思う。
入江泰吉の写真はは絵画であり、土門拳はデザイン画に見える。
泰吉は奥行きがあり、土門は平面的。
同じ仏像の絵を撮っているのに、なんで、こんなに違うもんができるのん?
この意味でも、写真はただのコピーじゃなくて表現=アートだと実感できた。
リアリズムとリリシズムかな?
今回、自分で意外に思ったのは、もし部屋に飾るなら、土門拳のほうを選ぶだろうなということ。
遠くから見ると、デザイン画にしか見えないのが、とってもいいのね。
ほとんどの写真は長辺1mほどの大きさで展示されている。
石の質感など、大判カメラを使っているとはいえ、フィルム写真がここまで細密に表現できることにも驚いた。
他にもいろいろ感じたことがあったけれど、上手く言葉に表せない。
ただ、ワクワクどきどきしながら写真展を見られてとても幸せだった。
付記:パソコンのMSの辞書?によると、「どもんけん」は一発で漢字変換するけれど、「いりえたいきち」は出ない。
土門拳の方が有名なんだろうか?
奈良市写真美術館は近鉄奈良から歩いて30分くらい。
閑静な住宅街の中にある。
あたりの風景にとけこむように、平屋建てで展示室は地下になっている。


お土産は入江泰吉の文庫本と絵葉書1枚。

宿六さんリクエストの
紅葉の壁紙 できました。

















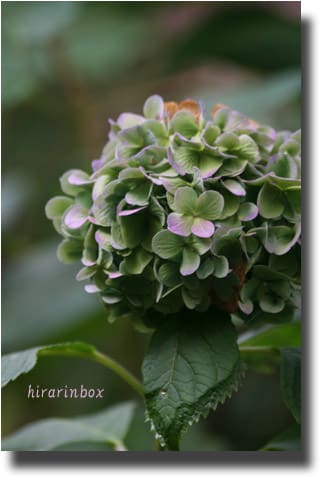
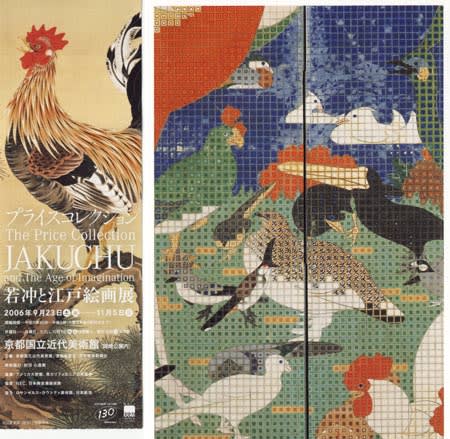

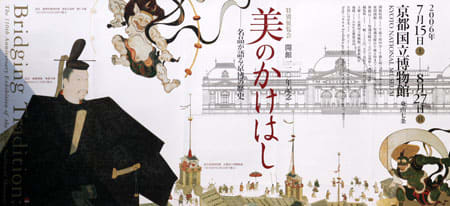
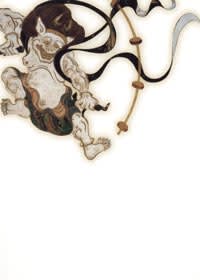 京阪電車の七条から歩いて10分ほど。この辺りは昔通学していて久しぶりだけど、それほど変わっていない。
京阪電車の七条から歩いて10分ほど。この辺りは昔通学していて久しぶりだけど、それほど変わっていない。 よくみると雷神風神には耳がついていて、むき出しの大口のにやけた笑い、おどろおどろしいというよりユーモラスだ。
よくみると雷神風神には耳がついていて、むき出しの大口のにやけた笑い、おどろおどろしいというよりユーモラスだ。



 「そのうち行ってみよう」は結局行きそびれることが多い。
「そのうち行ってみよう」は結局行きそびれることが多い。 その2、同じく大丸の14階「有希」のランチ。
その2、同じく大丸の14階「有希」のランチ。




