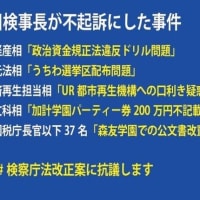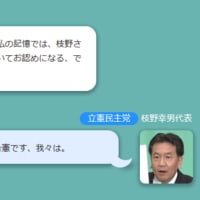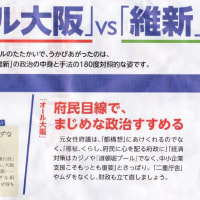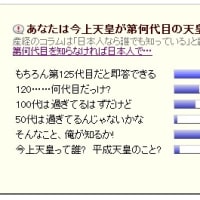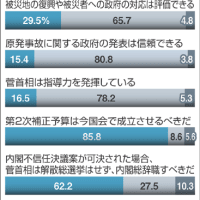(承前)
前回書きそびれていたが、マッカーサーはその『回想記』において、小堀桂一郎(1933-)氏が挙げている1951年5月3日の上院軍事外交合同委員会での証言と、1950年10月15日のトルーマン大統領とのウェーキ島会談について、どう述べているだろうか。
1951年5月に3日間、上院軍事外交合同委員会で証言したとは述べているが、その具体的な内容には触れていない。ただ、ラッセル委員長によるマッカーサーへの謝辞を引用しているのみである。
晩年のマッカーサーにとって、いわゆる「自衛戦争」証言や、「我々が過去百年間に太平洋で犯した最大の政治的過誤は、共産主義者達がシナに於いて強大な勢力に成長するのを黙認してしまった」との証言が、回想記に残しておくほど重要なものではなかったことがうかがえる。
ウェーキ島会談についてはかなり紙数を割いて詳しく述べている。しかし、トルーマンをやんわり批判しつつも、会談は友好的に行われたとしている。そして、中共軍の参戦については、
と述べ、自らの責任の回避を図っている。
もちろん、小堀氏が重視する、「戦犯には手をつけるな。手をつけてもうまくいかない」「東京裁判とニュールンベルグ裁判には警告的な効果はないだろう」と述べたとされる点への言及はない。
小堀氏をはじめこれらのマッカーサーの発言を好んで取り上げる人々は、マッカーサーが重要視していない片言隻句だけを切り取って、自説に都合の良いように解釈を付けて、吹聴しているだけだということがわかる。
さて、私がこの一連の記事の参考にするため袖井林次郎(1932-)の『マッカーサーの二千日』(中公文庫、1976、親本は中央公論社、1974)を読んだところ、その最終章の記述が、離任したマッカーサーと日本国民との関係を実に手際よく示していると思えたので、長くなるが紹介したい。
そして、文庫版の解説で、映画評論家の佐藤忠男(1930-)は次のように述べている。
こんにち、「自衛戦争」証言を好んで取り上げたり、あげくの果てには「マッカーサーの告白」なる偽文書を流布したりする人々もまた、「マッカーサーから賞めてもらいた」いという、被占領者の心理を引きずっているのかもしれない。
(完)
前回書きそびれていたが、マッカーサーはその『回想記』において、小堀桂一郎(1933-)氏が挙げている1951年5月3日の上院軍事外交合同委員会での証言と、1950年10月15日のトルーマン大統領とのウェーキ島会談について、どう述べているだろうか。
1951年5月に3日間、上院軍事外交合同委員会で証言したとは述べているが、その具体的な内容には触れていない。ただ、ラッセル委員長によるマッカーサーへの謝辞を引用しているのみである。
晩年のマッカーサーにとって、いわゆる「自衛戦争」証言や、「我々が過去百年間に太平洋で犯した最大の政治的過誤は、共産主義者達がシナに於いて強大な勢力に成長するのを黙認してしまった」との証言が、回想記に残しておくほど重要なものではなかったことがうかがえる。
ウェーキ島会談についてはかなり紙数を割いて詳しく述べている。しかし、トルーマンをやんわり批判しつつも、会談は友好的に行われたとしている。そして、中共軍の参戦については、
会談の終りごろになって、ほとんどつけたりのような調子で中共介入の問題が持出された。中共は介入する意志はないというのが、会談参加者全員の一致した意見だった。この意見は当時すでに、中央情報局(CIA)と国務省も出していたものだ。
と述べ、自らの責任の回避を図っている。
もちろん、小堀氏が重視する、「戦犯には手をつけるな。手をつけてもうまくいかない」「東京裁判とニュールンベルグ裁判には警告的な効果はないだろう」と述べたとされる点への言及はない。
小堀氏をはじめこれらのマッカーサーの発言を好んで取り上げる人々は、マッカーサーが重要視していない片言隻句だけを切り取って、自説に都合の良いように解釈を付けて、吹聴しているだけだということがわかる。
さて、私がこの一連の記事の参考にするため袖井林次郎(1932-)の『マッカーサーの二千日』(中公文庫、1976、親本は中央公論社、1974)を読んだところ、その最終章の記述が、離任したマッカーサーと日本国民との関係を実に手際よく示していると思えたので、長くなるが紹介したい。
マッカーサーの解任のショックが大きかっただけに、日本国民の反応もセンチメンタルであった。そして贈物の好きな日本人は多くの感謝決議を行ない、マッカーサーの功績と貢献を末永くたたえるにふさわしい方法を考えようとした。衆参両院は休会中の本会議を開いて感謝決議を行った。
〔中略〕たしかに吉田首相のいうように「天皇陛下から一市民に至るまで、すべての日本人があなたとの別れを惜しんでいます」というわけではなかったにしても、マッカーサーを「偉大なおやじ」(『朝日新聞』天声人語)として惜しむ気持が、国民の間に圧倒的であったことは事実であろう。
〔中略〕出発の日の新聞は、政府がマッカーサー元帥に対し「名誉国民」の称号を送ることを考慮中であると伝えた。これは後に五月に入って、「終身国賓に関する法律案」となって閣議を通っている。
また秩父宮、同妃殿下〔中略〕ら十四人の名士を発起人として、東京に「マッカーサー元帥記念館」の建設が進められ、本人の承諾も得て、実際に募金に着手している。
日本国民のマ元帥像は、彼がアメリカの各都市で歴史はじまって以来の大歓迎を受けているあいだ、海の向こうから燦然と輝く。上下両院合同会議における大演説は、日本国民をほめたたえて次のようにいう。
「日本国民は戦後、現代史上最大の変革を行ってきた。日本国民はみごとな意志力と学ぼうとする熱意、すぐれた理解力を発揮して、戦いの跡に残された灰の中から個人の自由と尊厳を至高とする高い精神を築きあげた」
「私は日本ほど安定し、秩序を保ち、勤勉である国、日本ほど人類の前進のため将来建設的な役割を果たしてくれるという希望のもてる国を他に知らない」
とくに演説の最後のくだりは、感傷ごのみの日本人にぴったりであった。
「〔中略〕私は当時〔引用者註:マッカーサーが52年前に陸軍に入った頃〕非常にはやったある兵営の歌の繰り返し文句を、まだ覚えている。その文句は非常に誇らしく次のようにうたっていた。
“老兵は死なず、ただ消えゆくのみ”
あの歌の老兵のように、私はいま軍歴を閉じて、ただ消えてゆく。神の示すところに従った自分の任務を果たそうとつとめてきた一人の老兵として。
さようなら」
「天声人語」子は、「『人生のたそがれどき』に立って、怒りも憎しみも越えて、心中たゞ『わが国に尽す』老兵の信念と別辞とを米国民に告げて去る元帥の後姿には哲人の面影がある」(『朝日新聞』四月二十一日)と書いた。
だが、上院の軍事・外交合同委員会での証言で、マッカーサーは「日本人はすべての東洋人と同様に勝者に追従し敗者を最大限にみさげる傾向をもっている。米国人が自信、落つき、理性的な自制の態度をもって現われたとき、日本人に強い印象を与えた」「それはきわめて孤立し進歩の遅れた国民が米国人なら赤ん坊のときから知っている『自由』を始めて味わい、楽しみ、実行する機会を得たという意味である」と語る。日本人は首をかしげはじめる。
しかし日本人が神経をもっともいらだてたのは「日本人十二歳論」であろう。マッカーサーはラッセル・ロング議員の質問に答えて「科学・美術・宗教・文化などの発展の上からみて、アングロ・サクソンは四十五歳の壮年に達しているとすれば、ドイツ人もそれとほぼ同年輩である。しかし日本人はまだ生徒の時代で、まず十二歳の少年である」と語った(『朝日新聞』五月十六日)。実はこれはマッカーサーが日本文化のもつ将来の発展性をたたえたのだと、考えればいいのであるが、そう受けとった日本人は少い。同じ「天声人語」子は「元帥は日本人に多くの美点長所のあることもよく承知しているが、十分に一人前だと思っていないようだ。日本人のみやげ物語としてくすぐったい思いをさせるものでなく、心から素直に喜ばれるように、〔名誉を贈るのは〕時期と方法をよく考慮する必要があろう」(五月十七日)といい出すにいたる。マッカーサーは「永久国賓」とはならず、「マッカーサー記念館」建設計画は、いつの間にか立ち消えとなった。日本人はやがて占領そのものを忘却のかなたに追いやることにはげむにいたる。(p.339-342)
そして、文庫版の解説で、映画評論家の佐藤忠男(1930-)は次のように述べている。
袖井氏も指摘するとおり、占領中にマッカーサーをあれほど讃美した日本人は、マッカーサーが去ってしまうと、夢からさめたようにマッカーサーについては語らなくなった。その決定的な切れ目は、例の、「日本人は十二歳」というマッカーサーの発言であった。日本人はいまさらのように、自分たちはマッカーサーによって愛されていたのではなく、“昨日の敵は今日の友”という友情を持たれていたのでもなく、たんに軽蔑されていたにすぎなかったと知った。袖井氏はこの発言にふれて、「マッカーサーが日本文化のもつ将来の発展性をたたえたのだと、考えればいいのであるが、そう受けとった日本人は少い」と書いている。じっさい、誰もこの発言の真意をマッカーサー本人に問いただそうともしなかったくらい、一瞬にして日本人の心はシラケたのである。考えてみれば、支配者である彼が被支配者である日本人を対等の人間であると見ていたはずはない。それを、そう言われてはじめて、がくぜんとして讃美することをやめたというのは、それまでいかに、日本人のほうで、マッカーサーに対して一方的に慈父に接するような甘えの感情を抱きつづけていたかを明らかにしたものであった。恥ずかしながら、日本人は、マッカーサーから賞めてもらいたかったのである。マッカーサーに支配された二千日の間、マッカーサー民主主義学校の優等生になったつもりではげんでいたのに、その校長先生が、教育委員会かどこかで、あんな素質の低い連中なんて……とかなんとか報告したような気がして、あらためて彼が、旧敵国から派遣された司令官であったことを思い出したのであった。
こんにち、「自衛戦争」証言を好んで取り上げたり、あげくの果てには「マッカーサーの告白」なる偽文書を流布したりする人々もまた、「マッカーサーから賞めてもらいた」いという、被占領者の心理を引きずっているのかもしれない。
(完)