私は学生時代に2年ほど、集中的に昔話の調査をしていた。当時は、今ほどのブームでなく、自分の子どもに話して以来、何十年ぶりで語れたよかったと、話者のお年寄りにいわれたことも一度ならずであった。資料としての話の調査は、できるだけ作為を排して伝承のままを記録するようにした。これは、読んで記憶したもと思われる話は、資料としては記録しなかった。話者と調査者の相互作用で、語りの場が生まれるなどと、難しい話をいうことは今回はやめて、伝承された話を対象としてきたのが、民俗学であったといえよう。ところが、その後昔話・世間話・笑い話が、民話という大きなジャンルとしてくくられ、しかも民話は創作なのか伝承なのかなどという区別を厳密にしなくなった。最近は読み聞かせという、読書運動?も盛んになり、民話の語り部講座まである。そうなると、この地の伝統だとして、創作した話が語り部の口から語られるようになる。
民俗学を現代にどう生かすか、という視点からはどんな形であれ、語りが復活してくることは喜ばしいことであるかもしれない。しかし、それが民俗学風に味付けされることで、お墨付きをもらったように、創作されたはなしが、この地に古くから語られた「民話」とされて、宣伝の道具となることはいかがなものだろう。古くからだろうが、最近からだろうが、そこに暮らす人々が語り継いできたと信ずるならば、どっちでもいいような気もするが、最近の「民話」とか「語り部」とかいう用語をみると、どうもすっきりしない思いになるのは、ミンゾクガクの形態にこだわる年寄りのなせる技なのだろうか。
民俗学を現代にどう生かすか、という視点からはどんな形であれ、語りが復活してくることは喜ばしいことであるかもしれない。しかし、それが民俗学風に味付けされることで、お墨付きをもらったように、創作されたはなしが、この地に古くから語られた「民話」とされて、宣伝の道具となることはいかがなものだろう。古くからだろうが、最近からだろうが、そこに暮らす人々が語り継いできたと信ずるならば、どっちでもいいような気もするが、最近の「民話」とか「語り部」とかいう用語をみると、どうもすっきりしない思いになるのは、ミンゾクガクの形態にこだわる年寄りのなせる技なのだろうか。










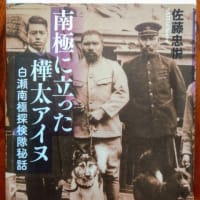

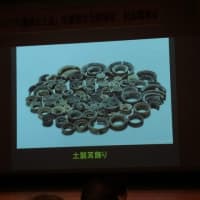


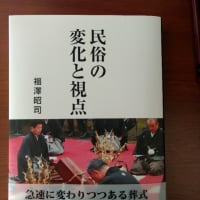




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます