岩田慶治著作集をくってみてはありましが、自然と共生する人間について書かれているとイメージする部分がみつからず、あきらめていました。ところが、コメントで指摘していただき、このあたりだとわかりました。『草木中魚の人類学』(著作集第2巻『草木中魚のたましい』)の中の、「木も語りかけ、小川もささやく。調査者の見る川のさざ波が、同時に、調査者を見つめている。」との記述でした。ついでにいえば、学生のころは、この部分にもひかれましたが、多分その先の記述にもっと感動していた気がするのです。「文化というものは、こういうわけで操作的にその姿をあらわすものである。調査者である私ーいわば日本文化を代表するものとしての私ーの全体にたいする調査されるものとしての他者ー異なる文化ーの全体である」という部分に、民俗学は全体としての人間を明らかにするものでなければならないと考えつつあった自分の根拠を得たような思いがしたものでした。
さて最近のこの国の対外関係が、東アジアで孤立化を深めているように思います。安倍首相は靖国神社に参拝するかどうかは個人の宗教的信条の問題であり、他国からとやかくいわれる筋合いのものではないといってるみたいです。(この対応に国際連盟を脱退した松岡洋介の外交が重なって見えてしまいます。その場は威勢よく国民にアピールしたが後の責任はとらない)首相は2重の間違いをしています。まず、靖国神社が本当に宗教施設なのでしょうか。国家が戦争で死んだ軍人を祀る(恨みをのんで死んだ人はたたるから、戦死者は慰撫する必要がありました)ために作った施設を神社としたもので、民衆の中にあった宗教ではありません。靖国の神は死者であり、しかも軍人に限られているのです。これを宗教施設だと外国に説明しようとしても、理解してはもらえないでしょう。100歩譲って靖国神社が宗教施設だとしたら、公人として1宗教施設に参ることは信教の自由を掲げる憲法に違反しています。しかも、多くの国会議員が参拝し、それが許される社会というのも、他国には説明できないものです。北朝鮮の行動の先が読めないとか、中国に国際感覚がないとかいいますが、同じことはこの国でも行われているということです。他国が遅れているとか訳がわからないとかいう前に、自らの姿をただす必要があると思います。
若いころの私は、戦争にいった父親を代表する世代に対して、あのころは皆そうだったとか、反対なんてできなかった、仕方なかったなどの言を聞くにつけ、戦争をしたことに対する反省がないことに腹をたてていました。若い者が親の世代に反発するのは当然のことでしょう。ところが、安倍首相はお祖父さんの岸信介を尊敬し岸の理念の実現を図るのが使命だと考えているらしい。気持ちの悪い話ですが、サラブレッドとはそういうものなのでしょうか。だとすれば、妖怪岸の行動について、私たちはもっと切実感を持って知らなければなりません。岸について詳しく勉強してない今でもいえることは、満州経営に携わった岸は、戦犯訴追を免れ、もちろん戦前の行為への反省などみじんもないままに、戦後の政界に復帰し戦前の理念の実現を図ったということです。そうすると、満州から現在日本まで政治は一直線に繋がってしまいます。侵略戦争をおこなったなどという意識は岸にはなかったでしょうし、お孫さんの安倍首相にもないでしょう。そういうところを近隣諸国につかれても、当然だと思います。










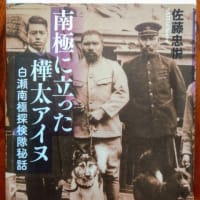

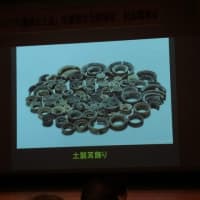


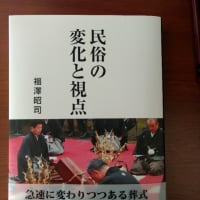




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます