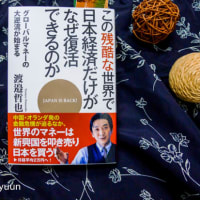民主党政権になって3年。GHQの占領以降に延々と続けられた戦後利得者のための欺瞞の保守政権。この欺瞞の保守政権、永久占領された日本だとい言っても形式的には保守政権の体裁は貫いていた。
ところが、民主党という左翼そして、親中国、親韓国であり本来の日本国民を敵視する妙な政党の毒素というものはなぜか廻ってきた気がする。
その予兆は2年ほど前から妙になったK-POPの氾濫やTVラジオに韓国絡みの出ない日がなくなったことも関係する。
そして笑えるのは、韓国を紹介する若い司会者が韓国は日本の一部だったという過去の歴史を認識していないことであった。
その一方で、新聞、雑誌マスコミというのは本来権力者に対して厳しいものという常識を覆して、時の政権にすり寄るものだと言うことをつとに示してくれたことである。
もともと保守派と言うはずだった読売新聞はあっと言う間に民主党にすり寄り、今や御用新聞で政治、経済などの論説、意見は政府擁護か代弁者になった。
時の政府民主党に都合の悪いことは書かないか、又は小さな見出しで誤魔化したり、論点をずらしたりする。
消費税増税の閣議決定がなされると「消費税増税はしかたがない」とかの容認議論を国民がしているような記事が載る。
朝日、毎日の論調というのはこの期に及ぶと右往左往するものの基本的には中国寄りと言うより中国の代弁者になっている事が多い。
その一方で「センターレフト」だったはずの産経新聞は、フジテレビが韓流偏重で多少おかしくなってきたのに連れて、保守派論調ではなく米国派であることがはっきりしてきた。
米国の保護国というベールを被った「マトリックス」の世界、占領された世界を修復したいというのが産経新聞の論調であり、民主党に至ってはその「マトリックス」社会すら自覚していない。
そう言う文脈で「日銀同意人事 政争の具にせぬルールを2012.4.8主張」を読むと実に面白い解釈をしていることが分かる。
この文面の意味するところは「政争の具にせぬルール」とかいうことは真っ赤な嘘で「BNPパリバ証券チーフエコノミスト河野龍太郎氏の日銀審議委員就任が阻止された」ことを単に面白くないと言っているだけである。
この河野龍太郎氏というのは民主党と言うより財務省に近い人物でいわゆる増税派の人物であることである。
三橋貴明氏のブログから引用すれば
------------------------------
河野氏は、現状の日本のデフレ深刻化について、
「少子高齢化に伴う働き手の減少でトレンド成長率そのものが低下している」
「社会保障制度の持続可能性に対する疑念から現役世代が消費を抑制している」
「財政赤字拡大で民間の貯蓄が食い潰され、設備投資が抑制されている」
三橋貴明氏の反論
なぜ上記がトンデモ論かといえば、
「働き手が減少しているのであれば、供給能力の低下によりインフレになるだろ!」
「現役世代が消費を抑制しているのは、単にデフレで所得水準が下がり、失業率が上がっているためだろ!」
「財政赤字拡大で設備投資が抑制されている(いわゆるクラウディングアウト)ならば、長期金利が上昇するだろ! 長期金利1%でも企業が設備投資をせず、負債残高を減らし続けている(これがデフレの国の特徴)以上、政府が財政赤字を拡大させなければ名目GDPが半減してしまうわ!」
と、デフレという資本主義を食いつぶす現象について、全く理解していないことが明らかであるためです。(あるいは、理解していないフリをしているのかも知れませんが。
----------------------------------
こんなふうに産経新聞社説氏がこのデフレ期に消費税の増税を推進する立場である。
そして、新聞各社異論を挟まずに一斉に消費税の増税の足並みをそろえているところが不思議でもある。
要点は、税収を上げるのが目的なのか、減収しても増税するのが目的なのかという本末転倒なところである。
テレビのある番組では、増税を可とする議論を補強するために週末の銀座で消費税増税のインタビューをしていた。
週末の銀座なんて東京人はいないではないかと思ったりもした中で、「増税したら物を買わないから」関係ないよというリタイヤした様な人物の発言があった。
正に、消費税を増税すれば国民はものを買わなくなる。すると企業は物が売れなくなれば工場を閉鎖するかしてリストラが増える。
「買わなくなる」どころか買えなくなると言うのが本当であろう。
すると企業も国民も消費しないからGDPが減り減収になる。
よってデフレ経済が進み経済が悪化すると言う事になる。
●産経社説では「とりわけ重要なのは『中央銀行の独立性』だ」と書くのだが、なぜ民主主義国家において日銀の独立性が必要なのか良く分からない。
なぜなら日銀というのは上場もしている株式会社である。こう言う株式会社である以上その運営の失敗責任を取る必要がある。
ところが、日銀というのは自らの失敗を認めたくないため責任を回避する政策を採ることがある。
その時に国民から遊離して「独立」していれば国の運営がおかしくなると言うこともありうる。
そこで産経新聞は
「先進国の中央銀行は、程度の差こそあれ、政府からの独立を標榜(ひょうぼう)する。自国通貨の価値を守る『通貨の番人』として政治の思惑とは別に経済状況を分析する。政府と逆の決断が必要な局面もある。
このため、政府のいいなりとみられると市場はもちろん、国際的信用を失い、国益をも損なう。」
と書くがあくまでも標榜するのであって独立はしていない。
そして、「国益を損なえば」当然罰として普通は総裁以下罷免されると言うのが常識である。
しかし、日銀はそうなっていない。
そして産経の社説氏は実際のところ嘘を言っていると言うのは以下の部分である。
「来年は日銀総裁の交代期だ。早急に同意人事に関する公正なルールを作る必要がある。国会提示前の事前調整や、参院で否決された場合は衆院の議決、再議決を優先させることを検討してもよい。」
なぜならもともと民主党内で反対論の多かった河野龍太郎氏を参議院で党議拘束までかけて提出して否決。
衆議院では民主党内で反対者が続出し、政府は採決を取り下げ、自民党が採決を主張して河野龍太郎氏本人が辞退する形にして採決を行わなかったからである。
単純に見ても元々与党民社党内で反対者が多く、野党も反対していたから河野龍太郎氏を審議委員に推薦することが間違いであった。
だから、単に社説氏が言いたかったのは、増税派で財務省にすり寄る河野龍太郎氏が就任できなかったことの不満を述べているだけである。
最後に
「ただ、いくらルールを作っても国会がその背景にある『日銀の独立性維持』を尊重しなければ意味はない。再び政争の具になり、日銀の、ひいては日本の信用失墜という結果を招きかねない。」
と書いているが、今回の件に関しては「政争の具」ではなく正当なものであろう。
そして、「日銀の独立性維持」と言いながら財務省の操り人形に様な人物であることが分かっているのに独立性維持が聞いてあきれる。
産経新聞というのも所詮権力に弱い新聞だったと言う事がよく分かる記事だった。
<script type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script>
日銀同意人事 政争の具にせぬルールを
日銀政策委員会審議委員の人事案が参院で否決された。政府が提案した候補が財政再建派で一段の金融緩和に慎重とされ、「デフレ脱却にはなお金融緩和が必要」とする自民、公明などが反発したのだ。民主党の消費増税反対勢力からも同様の声があがった。
日銀法は総裁、副総裁、審議委員について「両議院の同意を得て、内閣が任命する」と定めており、政策委員会に欠員が生じることになった。定員6人の審議委 員には学者、経済人、エコノミストなどが就いてきた。欠員が出ると多様な意見が交わされないし、意に沿わぬ人は審議委員にしないとなると、異なる立場の意 見を封じてしまいかねない。
法で定める以上、否決が認められないとはいえない。しかし、その際、国会が考慮すべき問題はある。とりわけ重要なのは「中央銀行の独立性」だ。
先進国の中央銀行は、程度の差こそあれ、政府からの独立を標榜(ひょうぼう)する。自国通貨の価値を守る「通貨の番人」として政治の思惑とは別に経済状況を分析する。政府と逆の決断が必要な局面もある。
このため、政府のいいなりとみられると市場はもちろん、国際的信用を失い、国益をも損なう。
当然だが、「独立性」と「政府との協調」は矛盾しない。日銀が政府と緊密に意見を交換し、景気認識をすりあわせることは重要だ。国会同意人事も日銀を意のままに動かすためではなく、独立性の担保が目的だったはずだ。
今回の参院否決にこうした考慮はあったか。消費増税法案審議を控え、恣意的な判断が加わったとすれば、責められるべきだ。
4年前、参院で過半数を制していた野党・民主党は自公政権が示した日銀総裁・副総裁人事案を相次いで否決、総裁は約3週間不在となった。衆参ねじれを武器にした民主党が文字通りの政争の具とし、異常な混乱に陥った。
来年は日銀総裁の交代期だ。早急に同意人事に関する公正なルールを作る必要がある。国会提示前の事前調整や、参院で否決された場合は衆院の議決、再議決を優先させることを検討してもよい。
ただ、いくらルールを作っても国会がその背景にある「日銀の独立性維持」を尊重しなければ意味はない。再び政争の具になり、日銀の、ひいては日本の信用失墜という結果を招きかねない。