第3037回の「太陽電池市場」や第3542 回の「中古パネル」などで取り上げてきた太陽電池パネルのリサイクルの興味深い記事がありました。
早くから取り組んでいた日本でも唯一じゃないかと思う「ネクストエナジー・アンド・リソース」の今までの事例を取り 上げています。
Tech-On!より 2013/12/12
中古パネル事業から見えてきた太陽電池の不具合事例
ネクストエナジー・アンド・リソース第5回
今回のシリーズは、太陽光発電システムの構築や保守などで知られるネクストエナジー・アンド・リソース(長野県駒ケ根 市)の担当者に、メガソーラー(大規 模太陽光発電所)のO&M(運用・保守)の状況などについて聞いている。第5回目となる今回は、同社の太陽光パ ネルのリユース(再使用)ビジネス を通じて蓄積された、中古太陽光パネルの検査・評価方法と劣化事例、その原因分析について紹介する。 …中略
セルの半導体は、半永久的に劣化しない
答 太陽電池のセルは、光を受けると電力を発生するP-N接合の半導体だが、結晶シリコン系の場合、このP-N接合自体 には、太陽光発電程度のストレスで は大きな劣化要因とはならない。それなのに太陽光パネルに出力低下や出力異常が起きるのは、接合部以外の構造に問題が出 てくること多いからだ。結晶シリコ ン系の太陽光パネル(太陽電池モジュール)の構造は、セルを直列に接続し、透明な封止材で挟んで表面をガラス、裏面を バックシートで被い、アルミのフレー ムを付けるという構成になっている。これらの構造体のなかで、不具合が生じる原因には、大きく三つある。
第1は、セルとセルとの接続部、具体的には、ハンダ付け部分に長年の間に不具合が出てきて、断線不良になるケース。 第2は、セルに割れが生じて電流経路が部分的に断たれるケース。第3が、封止材やバックシート、フレームなど材料の劣化 に起因する不具合だ。
――出力異常が見つかるような耐久性に問題のあるパネルには、これらの不具合のうち、何らかの傾向が見られるのか。
答 大量の使用済みパネルを検査してきてわかったことは、特定の異常症状が、同じメーカーの同じ型式、もっと言えば、型 式の中でも一つの工場で同時期に作 られたロットに集中する傾向があるということ。これは、製造工程に何らかの問題があるのではないかと推察される。たとえ ば、ハンダ付けの工程管理などであ る。
封止材やバックシートの不具合は解決されてきた
――封止材、バックシート、フレームの異常は、どのような症状になるのか?
答 アルミ製フレームでは腐食が起きることがある。アルミ製フレームを直接、鉄製のネジで架台に止めている場合に、地理 的条件や気候条件で厳しい要素が重 なると、異種金属の接触電位差による腐食が起きやすくなる(図4)。産業用の架台では、フレームの取り付け用の穴に直接 ねじ止めすることはほとんどなく、 同じアルミ材で押さえる方式のものが主流なので、まず問題にはならないのではないかと考えられる。
また、封止材の変色や剥離などの現象もある(図5~7)。ただし、われわれの中古在庫を見る限り、これ らは古い製品に特有の現象なので、これらの材料はメーカーによる改良が進んだと考えられる。
このように材料に起因する問題は、パネルメーカーや材料メーカーの努力によって、確実に解決へ導かれつつあるようで ある。こうして見ると、パネルの不 具合の原因として、本質的な解決が遅れているのは、ハンダ付けとセルのクラックということになる。これらについては次回 以降、詳しく解説する。
太陽光発電リサイクルセンター
やはり経験は貴重ですね。こうやって弱点が解り、解決されて行くと、100年以上の耐久性を持つパネルだって夢じゃ ないでしょう。
そうなれば、今はコストの問題のある太陽光発電も耐久性を手に入れることで他の発電と比べても圧倒的な 低コストの実現も夢じゃ無くなるはずです。
何と言っても、装置が稼働している間太陽の光さえあれば何のエネルギーも使わないのですから。これは強 いですよ。
今、沢山設置されているメガソーラーが20年後にどうなっているかも興味深いですね。国産品ならその後 も長い間稼働しているかもしれません。そうなれば、それが日本の財産でもあります。
どんな20年後が来るのか!
最新の画像[もっと見る]










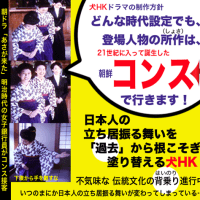
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます