宮崎さんが書評で取り上げてくれた戦前の教科書を、2020年4月8日、第7493回の「★文部省『復刻版 初等科修身』」で、取り上げました。
もう一年近く前になるんですね。その間、トランプさんが不正選挙でニセ大統領に負けるというとんでもない大事件もありすっかり忘れていました。とは言え、本当は、アメリカより日本の方が大事です。
宮崎さんが、今度は同じ復刻版の『高等科国史』を書評で取り上げてくれています。戦時中で未刊となっているそうです。
宮崎さんが何故未刊となったかを鋭く考察してくれています。文部省も戦時中ということで肩に力が入りすぎたのか、都合の悪いところを書かなかったようなところがあるようです。
それでも、今の教科書とは比べものにならない程素晴らしいものじゃないでしょうか。
早く正当な歴史教育に取り掛からないと、あのアメリカと同じ運命を辿りそうです。
「宮崎正弘の国際情勢解題」より 令和三年(2021)1月23日(土曜日) 通巻第6774号
(( 読書特集 ))
書評
まぼろしの歴史教科書、76年の沈黙を破って復刻版見参
GHQは何を怖れたのか。未刊行となった理由は奈辺にあったか?
『高等科国史』(復刻版、三浦小太郎解説=ハート出版)
文部省が昭和十九年に編纂した歴史教科書は、当時の教育科目として「国史」とされる。
古代から中世にかけての記述を『日本書紀』に沿って皇統の正統性が強調され、国威の発揚が企図された。
とりわけ出雲の国譲りが美談仕立てとなって、仏教の伝来と啓蒙普及をなした聖徳太子の威徳を忍び、蘇我稲目、馬子、蝦夷、入鹿の蘇我一族は『悪』と裁断されている。当時の強烈な愛国心が語彙と行間に滲みでており、それなりに往時の雰囲気、国民の漲る決意を感得する。若者達を忠君愛国の徒に育て上げたかったのだ。
「高等 科国史」ではなく「高等科 国史」である。つまり高等学年の生徒に、わかりやすく「豊葦原の瑞穂の国」が辿った輝かしい過去を、自信を持って語りかけた教科書である。
ところが昭和十九年に、第一巻が刊行されたものの学徒動員などと重なって教室で使用されず、第二巻は印刷製本されていたが、見本のまま倉庫に眠る運命をたどった。
まぼろしの歴史教科書が、じつに76年を経て日の目をみたのだ。
往時のわが国は大東亜戦争の最中、社会環境は戦意高揚、当然だが、歴史叙述は皇国史観が主流である。
雲の国譲りのことは以下のように美化されていて、ちょっと長いが引用してみよう。
「豊葦原の瑞穂の国、その一角の出雲地方には、早くも(天照)大神の御弟スサノウノミコトが降され、賊徒を鎮めて良民をいたわり給い、又、半島地方へも往来
し給うた。やがて、その御子大国主神(オオクニヌシノカミ)は、土地を開き、医薬の法などを教えて、民草をいつくしまれ、その御勢力は、とみに盛んとなった。
かくて瑞穂の国は、出雲地方から開け始めたのであるが、なお他の地方には、賊徒が横行し、天の下は、決して安らかではなかった。大神は、このありさまをみそなわし、御子孫をこの国に降して、安らかに治めさせようと思し召し、先ずフツヌシノカミ(経津主神)・タケミカヅチノカミ(武甕槌神)を出雲に遣わして、大国主神にその御旨を伝えしめ給うた。大国主神は、御子事代主神と共に、大神の勅を畏み、土地を奉還して、杵築宮(出雲大社)に退かれた。君臣の分をわきまえ、勅を奉じて必ず謹む臣道の実は、かくて挙がった」
という君臣の美談に置き換えられている。高志国と出雲、信濃との連合状況などは一切語られない。
ここではスサノオの荒んだ行為も描かれず、また八俣大蛇退治も省略。タケミカツジノミコトが勝負した腕比べもない。出雲いがいは単に「賊徒」となっている。
この歴史意識は神武東征の叙述につながり、ナガスネヒコ(長臑彦)は神武天皇の東征に歯向かったのだから「賊徒」の位置づけ。基調は変わらない。
東征の船出(美々津)から宇佐へ上陸、筑紫岡田宮に滞在などの詳細は省略し、瀬戸内海を東へ向かう。
「海上の御苦難は一通りではなかったが、将士の意気は、天を衝くばかりであって、行く行く御船を迎えて水先案内を承る者もあれば、供御を献ずる者、従軍を願い出る者も多かった。(中略)かくて天皇は、御船を安芸の埃宮、吉備の高島宮等、要処々々にとどめて、付近の賊徒を平げ、草民をなつけ給うた。特に高島宮では、三年の間おとどまりになって、種々経営あらせられると共に、傍ら将兵の労苦をいたわり、船艇、兵糧を補って御進発、やがて難波の港に」
と神武東征の旅程は美的にしかし簡略的に描かれる。
そして「降る者は、直ちにこれを許し給い、大義にそむいて手向かう者は、あくまでこれを討ち平らげて、神武の道を発揚あらせられた」と「大義」「神武」「臣道」など、現代日本語にはないか、あっても遣わない語彙が並ぶ。
ならば、神功皇后の三韓征伐はどのように描写されたのかと言えば、「国威の発揚」という小見出しの下、「新羅御遠征」となっている。
経過は「新羅は勢威を誇って(朝鮮)半島の平和を乱し、任那を圧するばかりか、わが九州の熊襲をそそのかすに至った。(中略)神功皇后は、神慮のまにまに新羅を御征討にあり、神国の威武を半島に輝し給うた」
戦後の歴史学の一部は神功皇后の存在を否定した。慈円の『愚管抄』は景行天皇のお后として従軍したあと、第十五天皇として皇統府に加えているが、現代の歴史書のことごとくは神功皇后を皇統譜にくわえておらず、第十六代天皇を仁?天皇としている。この論争に関しては別の機会に譲る。
ならば評者(宮崎)の次の関心事は「大化の改新」を、この教科書はどう教えようとしたのか、である。
世が乱れて承詔必謹の精神を忘れ、国民が国体の尊厳を忘却し、勅を揺るがせる乱世に聖徳太子は憲法と律令をもって安寧をもたらせようとした。
「儒教や仏教を国の制度に取り入れると、蘇我氏のように、外国の教えに惑わされて、道を誤る者」が出現したという見方が基礎にある。
したがって蘇我馬子から蝦夷となると「承詔必謹」の御教えにそむき、君臣の大義にもとるふるまいはやがて皇極天皇の御代における、孫入鹿の無道となった。「入鹿が(聖徳)大使の御子、山背大兄王の御声望をねたみ、兵を送って斑鳩宮を焼き、更に畏れ多くも王を法隆寺に害し奉った」
と書いている。
したがって中大兄皇子と中臣鎌足が板葺宮にて蘇我入鹿を斬る。これが大化の改新の始まりだが、近年の歴史学は「クーデター」と定義し、単に「乙巳の変」と述べるようになっている。
しかし当該教科書では、大化の改新には肯定的評価がなされ明治維新の大業に等しいとなる。文武天皇時代に定まった「大宝律令は、その後明治の初期まで、約千二百年の間、朝政の根本となった重要な法典である」とし、藤原不比等らが編纂したと詳しく書いている。
ならば、もう一つ。天智天皇の「白村江」の敗戦は?
半島情勢の説明のあとに「斉明天皇もまた、百済を助けて新羅を抑え、唐の勢いを防いで半島の平和を図ることを思し召し、御軍を率いて、親しく筑紫に行幸された。御稜威を仰いで、耽羅(済州島)が始めて(日本に)朝貢し、御軍の意気は大いに揚がった」
天智天皇は百済救援の軍事作戦を継続し筑紫に陣をはって即位の礼をさえ延期された。
しかし百済は滅びたため「(天智)天皇は、深く内外の形成をみそなわして、百済再興の望みをお絶ちになり、専ら内政の充実と国防の強化とに務め給うた。(中略)半島で示したわが軍の威武が、唐の将兵をおののかせ、その将帥が使節を以て(日本に)朝貢し、よしみを求めた事実のあることを忘れてはならない」と、ここでは白村江の「大敗」に関しての明言を避け、近江京への遷都に繋いでいるのである。
さらにもう一つ。『高等科国史』は、古事記と日本書紀をいかように評価しているのかを、この小欄の最後に見ておこう。
古事記は「すべて国語で記され、神生み給い神しろしめす上古の姿と、わが国固有の精神とが明らかにされた。編集にあたった安万呂が特に心を砕いたのは、その文章と文字の使い方とであるが、それも、上古の精神や姿をさながらに伝えるための努力だった」。
つまり「国語で記され、上古の精神」があるとしている。
日本書紀は「神代から持統天皇に至る皇室発展の跡を、漢文で詳しく記したもので、正確は記録を多く集めて、御代々々の御事歴を明らかにし、後世永く修史の模範と仰がれた」。
ここで重大なのは「漢文で」書かれ、後世の「修史の模範」と言っていることである。日本の戦前の教科書が精神を第一義とした姿勢はよく了解できたところで、小欄の紙幅が尽きた。
少しおかしなところもあるようですが、これも戦争中ということで分からなくもないですね。
それでも、歴史や神話を取り上げない戦後の文科省には到底及びもつかない教科書です。
今や、宮崎さんやねずさんなどが素晴らしい歴史を書いてくれています。それで、多くの日本人が目覚めてくれることを期待しますが、やはり教科書には敵わないでしょう。
一日も早い教育の改革が必要です。オリンピックを開催するかどうかより余程大事なことじゃないでしょうか。
ここに手を付けない政府・自民党は存在価値が無いと言っても過言ではないでしょう。
いい加減に目を覚まさんかい国会議員!










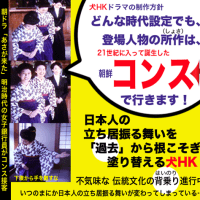
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます