これも全く知りませんでしたが、ねずさんに教えて もらって驚いたものです。その解釈に納得させられると共に戦後教育の劣化に呆れるしかありませんでした。
それにしても、朝鮮半島は本当に救いようのない国ですね。白村江の戦いで向こうに残った日本人は本当に気の毒です。
やはり、あの国と関わると碌なことにならないというのはあんな昔から実証されていたということです。何時までも隣と付き 合う必要があるなんて考えは一日も早く捨てましょう。
何時ものように全文をリンク元で読んでください。
ねずさんの学ぼう日本より 2021/09/12
山上憶良の貧窮 問答歌の真実
・・・略
万葉集の選者は、筑前の国司だった山上憶良が、民衆を心から愛していたこと。
そして憶良が、天皇の臣(おみ)であると書いているのです。
つまり、憶良のように
「民衆を心から愛する者」こそが、
「万世一系の天皇の家臣」であるという認識の上に立っています。
ちなみに、この歌にある「朝貌(あさがお)」は、いまでいう桔梗(キキョウ)のことです。
私たち現代人にとってのアサガオは、夏の早朝に咲く朝顔ですが、この花は熱帯アジア産で、渡来したのは平安中期以降のことだ からです。
山上憶良の時代には、まだ日本にアサガオはなかった。・・・中略
要するに『貧窮問答歌』は、かつて日本領であり、いまでは新羅によって蹂躙された半島の人々の困窮した生活の様子を、半島 の向かいに位置する筑前の国司であった山上憶良が長歌に描いた作品であったのです。
このような、ある程度社会経験を積んだ大人なら、少し考えたら誰にでもわかることを、意図して歪めて子らに教える。
それは、すくなくとも子らに対して、また教職という立場に対する、不誠実といえるのではないでしょうか。
このようなデタラメが、戦後にはじまり、そしていまだに行われ続けている。
それを立て直すためには、私たちいまを生きる大人たちが目覚めていくしかないのではないかと思います。
諸般の事情から、拙著『ねずさんの奇跡の国 日本がわかる万葉集』からはこの解説を削除しました。
しかし私個人としては、本日書いた内容が、この『貧窮問答歌』の真実であると確信しています。
この歌は筑前の国司が、いまでいう半島事情を詠(えい)じた歌です。
やはり、ねずさんの解釈は納得させられます。こうした歴史観を日本人全てが知るべきです。










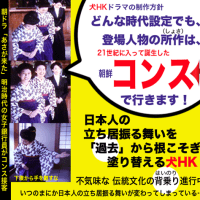
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます