ねずさんの話には涙なしには読め無いものが多い。その中でも一番と思えるのがあの白骨街道のインパール作戦です。
敗退する兵隊さん達が餓死しようとも現地の人達を襲ったり食料を奪うことなく死んで行ったという事実を知り、現代の劣化した日本人にこの真似は絶対に出来ないだろうと思い知らされすことほど辛いことは無い。
そんな方達が祀られる靖国を未だに参拝しないことが悔しくてなりません。
何時ものように全文をリンク元で読んでください。
ねずさんの学ぼう日本より 2020/11/21
インパールの 戦いから我々が学ぶべきこと
・・・略
諸外国のなかには「歴史認識」という虚構を通じてみなければ、恥ずかしくて生きていくことさえ難しくなってしまうような歴史を持った国や民族もあります。
けれども日本の歴史はまったく逆です。
標準化された「歴史認識」ではボロカスに言われていることでも、複眼的思考をもって歴史を振り返ると、そこにはまるで、トレジャーハンターが宝物を見つけたときのような衝撃と感動と日本人としての誇りをみることができます。・・・中略
昭和十八年九月の御前会議で、絶対国防圏として千島、小笠原、マリアナ、西部ニューギニア、スンダ、ビルマを含む圏域を定め、この外郭線において敵の侵攻を食い止めようという戦略が決定されました。
インパール作戦は、その基本戦略に反しています。
なぜなら、国防圏の外側にあるインドに、撃って出ようというのです。
どうしてこの時期にこういう作戦を立てたのでしょうか。
しかも、はじめは反対していた大本営も、当時日本に滞在していたインドの独立運動家、チャンドラ・ボースの強い要請を受けて、作戦の実施を認めたといいます。
もしかしたらインドの独立に火をつけることで、退勢が濃くなってきた大東亜戦争の戦争目的を改めて世界に訴える意味が重視されたのかもしれません。・・・中略
▼世界最高の軍紀を誇った日本軍
日本軍の軍紀は称賛に値すべきものでした。
餓鬼や幽鬼のような姿で山中を引き揚げる日本の将兵たちのだれ一人、退却途中の村を襲っていないのです。
すでに何日も食べていない。
負傷もしている。
病気にも罹っている。
そんな状態にもかかわらず、退路に点在していたビルマ人の村や民家を襲うどころか、物を盗んだという話さえ、ただの一件も伝えられていないのです。
これは普通では考えられないことです。
銃を持った敗残兵が民家を襲い、食糧を略奪するなどの乱暴をはたらくのは、実は世界史をみれば常識です。
戦場になったビルマですが、現地の人たちは戦中も戦後も、日本軍に極めて好意的です。
そは日本の軍人が、そういう不祥事を起こさなかったからです。
戦後、実際にインパール作戦に従軍された方々によって、たくさんのインパール戦記が刊行されたけれども、驚くことは、民家を襲わなかったことを誇る記述を、誰一人として残しておられないということです。
戦争に関係のない民家を襲わないなんて「あたりまえ」のことだったからです。
むしろ、退却途中でビルマの人に助けてもらった、民家の人に食事を恵まれたと感謝を書いている例が多い。
それが日本人です。そういう生き方が我々の祖父や父の若き日であったのです。・・・中略
実際、インパールで日本軍と戦ったあと、インド各地で起きた独立運動に対するイギリス駐留軍の対応は、当時の帝国主義国家の植民地対応と比べると、あまりにも手ぬるいものとなっています。
やる気がまるで感じられないのです。
ガンジーたちの非暴力の行進に対して、ほとんど発砲もしないで通しています。
以前のイギリス軍なら、デモ集団の真ん中に大砲を撃ち込むくらいのことは平気でした。
そして、戦後の東京裁判でイギリスは、インドがパール判事を送り、パールが日本擁護の判決付帯書を書くことについて口を出していません。
そこに私はインパール作戦が世界史に及ぼした大きな、真に大きな意義を感じるのです。・・・以下略
牟田口さんはこのねずさんの考察を読まれたら、やっと分かってくれたかと号泣されるのじゃないでしょうか。そうさせてあげたかった。
それにしても、先人は凄かった。イギリスの態度も騎士道を思い出させてくれます。










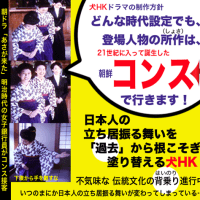
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます